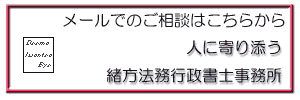�@�悭���鑊�k���e���L�ڂ��܂����B
�������A�⌾���ɂ��Ă̑��k
����P
���ƍȂɂ́A�q�������܂���B���̂��߁A�⌾�����Ȃ��Ă��A�S�Ă̍��Y�́A�Ȃ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����Q
�����͂͒�o���Ă��Ȃ��v�w�ł��A10�N�ȏ�ꏏ�ɕ�炵�Ă���ꍇ�ɂ́A�v���S���Ȃ����ꍇ�A�����͂��o���Ă���ȂƓ����悤�ɑ�����������ƒm�荇�����猾��ꂽ�̂ł����A�{���ł����B
����R
���Y�̑S���j�����ɑ������������̂ł����A�ǂ�Ȉ⌾�������������ł����B
����S
���j�̉łɂ���Y����ɂ́A�ǂ�ȓ��e�̈⌾���ɂ����炢���ł����B
|

�����c�����ɂ��Ă̑��k
����P�@
���Y���^��Ԏӗ��͗����葱��ł������ł��܂����B
����Q
�{���͗����葱��ł������ł��܂����B
����R
�����̍ہA���[���͕Ԃ��Ă��炦�܂����B
����S
���c������A�v�ɂ͎q���Ɖ�킹��������܂���B�{�������Ȃ���A�v�̖ʉ��F�߂Ȃ����Ƃ��ł��܂����B
����T
���{�l�̕v�Ɨ������鎞�O���l�̎������ɒ��ӂ��邱�Ƃ͉�������܂����B |

��VISA�@�d�v����@
�ݗ����i�̐\���ɍۂ��āA�R���̊�ƂȂ肤�锻����܂Ƃ߂܂����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
����10�N���畽��12�N�̍ݗ����i�\���Ɋւ��锻��
�E�����n���ٔ����@�����P�O�N�i�s�E�j��Q�R��
�E�����n���ٔ����@�����N10 �N�i�s�E�j��77��
�E�����n���ٔ����@����11�N�i���j��11859��
�E�����n���ٔ����@����12�N�i�s�E�j��211��
- �����n���ٔ���
�����P�O�N�i�s�E�j��Q�R��
�����P�O�N�P�Q���Q�T
�啶
��@�����̐��������p����B
��@�i�ה�p�́A�����̕��S�Ƃ���B
�����y�ї��R
���@�����̐���
�@�퍐�������ɑ��A������N��ꌎ�����t���ł����ݗ����i�F��ؖ����s��t�������������B
���@���Ă̊T�v
�@�{���́A�����i��p�j���Ђ�L����O���l�ŁA���{�l�j���ƍ����W�ɂ��錴�����A�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j�����̓��ꍀ�Ɋ�Â��A�퍐�ɑ��ݗ����i�F��ؖ����̌�t��\�������Ƃ���A�퍐����A�������@�����ꍀ�l���ɋK�肷������ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�E�ؖ�������t���Ȃ��|�̏����������߁A�������A�����s���Ƃ��āA�E�����̎���������߂Ă��鎖�Ăł���B
��@�W�@�߂̒��
�P�@�O���l�̏㗤���ێ��R
�@�@���ꍀ�́A�O���l�̖{�M�ւ̏㗤���ێ��R�ɂ��ċK�肵�Ă���Ƃ���A�����l���y�ю����Ɍf����ꂽ�㗤���ێ��R�́A���́i��j�A�i��j�L�ڂ̂Ƃ���ł���B
�i��j�l��
�@���{�����͓��{���ȊO�̍��̖@�߂Ɉᔽ���āA��N�ȏ�̒����Ⴕ���͋������͂����ɑ�������Y�ɏ�����ꂽ���Ƃ̂���ҁB�������A�����ƍ߂ɂ��Y�ɏ�����ꂽ�҂́A���̌���łȂ��B
�i��j����
�@���t���͂��̎����A���U�A���̏ꏊ�̒��̑����t�ɒ��ڂɊW������Ɩ��ɏ]���������Ƃ̂����
�Q�@�����R�����̐R��
�i��j�{�M�ɏ㗤���悤�Ƃ���O���l�i����������B�j�́A���̎҂��㗤���悤�Ƃ���o�����`�ɂ����āA�@���ȗ߂Œ�߂�葱�ɂ��A�����R�����ɑ��㗤�̐\�������āA�㗤�̂��߂̐R�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���i�@�Z��j�A�@�����ꍀ�́A�����R�����́A�E�̐\�����������Ƃ��́A���Y�O���l�����́i�P�j�Ȃ����i�S�j�L�ڂ̓����e���i�@��Z���ꍀ�̋K��ɂ��ē����̋������͖@�Z����̓�̘Z��ꍀ�̋K��ɂ���t��������s�ؖ������������ď㗤����O���l�ɂ��ẮA�ꍆ�y�юl���j�Ɍf����㗤�̂��߂̏����ɓK�����Ă��邩�ǂ�����R�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƒ�߂Ă���B
�i�P�j�ꍆ
�@���̏������闷���y�сA����K�v�Ƃ���ꍇ�ɂ́A����ɗ^����ꂽ�����L���ł��邱�ƁB
�i�Q�j��
�@�\���ɌW��{�M�ɂ����čs�����Ƃ��銈�������U�̂��̂łȂ��A�@�ʕ\���̉����Ɍf���銈���i�܂̕\�̉����Ɍf���銈���ɂ��ẮA�퍐�����炩���ߍ����������Ē�߂銈���Ɍ���B�j���͖@�ʕ\���̉����Ɍf����g���Ⴕ���͒n�ʁi�i�Z�҂̍��̉����Ɍf����n�ʂ������A��Z�҂̍��̉����Ɍf����n�ʂɂ��Ă͔퍐�����炩���ߍ����������Ē�߂���̂Ɍ���B�j��L����҂Ƃ��Ă̊����̂����ꂩ�ɊY�����A���A�@�ʕ\���̓�̕\�y�юl�̕\�̉����Ɍf���銈�����s�����Ƃ���҂ɂ��Ă͉䂪���̎Y�Ƌy�э��������ɗ^����e�����̑��̎�������Ă��Ė@���ȗ߂Œ�߂��ɓK�����邱�ƁB
�i�R�j�O��
�@�\���ɌW��ݗ����Ԃ��@����̓��O���̋K��Ɋ�Â��@���ȗ߂̋K��ɓK��������̂ł��邱�ƁB
�i�S�j�l��
�@���Y�O���l���@���ꍀ�e���̂�����ɂ��Y�����Ȃ����ƁB
�i��j�Ȃ��A�@����ɂ��A�E�i��j�L�ڂ̓����R�����̐R������O���l�́A�����ꍀ�ɋK�肷��㗤�̂��߂̏����ɓK�����Ă��邱�Ƃ����痧���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B
�R�@�ݗ����i�F��ؖ������x
�i��j�@�����̓��ꍀ�́A�퍐�́A�@���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A�{�M�ɏ㗤���悤�Ƃ���O���l�i�{�M�ɂ����Ė@�ʕ\���̎O�̕\�̒Z���؍݂̍��̉����Ɍf���銈�����s�����Ƃ���҂������B�j����A���炩���ߐ\�����������Ƃ��́A���Y�O���l���@�����ꍀ�Ɍf��������ɓK�����Ă���|�̏ؖ�������t���邱�Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B
�i��j�@�����̓��ꍀ�̋K����āA�@�{�s�K���Z���̓�́A�ݗ����i�F��ؖ������x�ɂ��ċ�̓I�ɒ�߂Ă���Ƃ���A�����܍��́A���̖{���ɂ����āA�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������ꍇ�ɂ́A�퍐�́A���Y�\�����s�����҂��A���Y�O���l���@�����ꍀ�Ɍf����㗤�̂��߂̏����ɓK�����Ă��邱�Ƃ𗧏����ꍇ�Ɍ���A�ݗ����i�F��ؖ�������t������̂Ƃ���|�K�肵�A���̂��������ɂ����āA�퍐�́A���Y�O���l���@�����ꍀ�ꍆ�A�O�����͎l���Ɍf��������ɓK�����Ȃ����Ƃ����炩�ł���Ƃ��́A�E�ؖ�������t���Ȃ����Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B
��@�O��ƂȂ鎖��
�i�ȉ��̎����̂����A�؋������f�L�������̈ȊO�́A�����ҊԂɑ������Ȃ������ł���B�j
�P�@�����̍��Г�
�@�����́A���l�N�i���a���N�j������ܓ��A�����i��p�j�ɂ����ďo�������A�����i��p�j���Ђ�L����O���l�����ł���B
�Q�@����ڋy�ё���ڂ̓����y�яo���̏�
�i��j�i�P�j�����́A���a�܋�N�Z������A�������N�@���掵�㍆�ɂ������O�̖@�i�ȉ��u���@�v�Ƃ����B�j�l���ꍀ�l���ɊY������҂Ƃ��Ă̍ݗ����i�i�ȉ��u�ݗ����i�l�|��|�l�v�Ƃ����B�j�y�эݗ����ԋ�Z���̏㗤�����Ė{�M�ɏ㗤�����B
�i�Q�j�����́A���̌�A�ݗ����ԍX�V�����Ė{�M�ɍݗ����A���a�܋�N��ꌎ��Z���A�O�v�ł�����{�l�j���ƍ������A���a�Z�Z�N�ꌎ����A�퍐����A���̍ݗ����i�����@�l���ꍀ��Z���y�ѕ�����N�@���ȗߑ��܍��ɂ������O�̖@�{�s�K������ꍆ�ɊY������҂Ƃ��Ă̍ݗ����i�i�ȉ��u�ݗ����i�l�|��|��Z�|��v�Ƃ����B�j�ɕύX���A�ݗ����Ԃ�Z�����Ƃ���|�̍ݗ����i�ύX�������B
�i�R�j�����́A���̌�A�Z��̍ݗ����ԍX�V�����Ė{�M�ɍݗ����Ă������A���a�Z��N�����A�O�v�Ƌ��c�������A���a�Z�O�N�Z���A�o�������B
�i��j�����́A���a�Z�O�N�܌����A�ݗ����i�l�|��|�l�y�эݗ����ԋ�Z���̏㗤�����Ė{�M�ɏ㗤���A�{�M�ɑ؍�A���N������ܓ��A�o�������B
�R�@��O��ڂ̓����y�ёދ����������o��
�i��j�����́A���a�Z�O�N��ꌎ���A�ݗ����i�l�|��|�l�y�эݗ����ԎO�Z���̏㗤�����Ė{�M�ɏ㗤���A���N������A���{�l�ł��邁�ƍ������A�������N�ꌎ�ꔪ���A�퍐����A���̍ݗ����i���ݗ����i�l�|��|��Z�|��ɕύX���A�ݗ����Ԃ�Z�����Ƃ���|�̍ݗ����i�ύX�������B
�i��j�����́A���ƍ�����A�V�������n�S���ȉ������ɂ����ē��l�Ɠ������A������N�O���ɓ��l�����S���ȉ������ɋ���X�܂�V�z���A���H�X���J�Ƃ�����́A���l�Ƌ��ɂ��̉c�Ƃɏ]�����Ă����Ƃ���A�����Ƃ��́A�E���H�X�̉c�ƂɊւ��A�����O�N�܌���Z�����납�畽���l�N��ꌎ�O�Z���܂ł̊ԁA�{�M�ɂ����ĕ�V���̑��̎��������������邱�Ƃ��ł���ݗ����i��L���Ȃ��O���l�����Z�����A�z�X�e�X�����t�w�Ƃ��ĕ�V���銈���ɏ]�������A�܂��A���N�l�����{���납�瓯�N��ꌎ�O�Z���܂ł̊ԁA�E�Z���̊O���l�������E����X�܂̓�K�ɋ��Z�����A�������̎w���ɂ��A�E�O���l����������Ĕ��t�s�ׂ��s�킹�Ă����i�b�l�A����A�٘_�̑S��|�j�B
�i�O�j�����Ƃ��́A�����l�N��ꌎ�O�Z���A�V�����x���Ìx�@���ɔ��t�h�~�@�ᔽ�̗e�^�őߕ߂���A�����ܔN�O�������A�V���n���ٔ����ɂ����āA�@�ᔽ�y�є��t�h�~�@�ᔽ�̍߂ɂ��A��������A������N�������y�є�����Z���~�A�����Y�ɂ����s�P�\�O�N�̗L�ߔ��������B
�i�l�j�����́A�O�L�i��j�L�ڂ̍ݗ����i�ύX��������A�l��ɂ킽���čݗ����ԍX�V�����Ă������A�l��ڂ̍ݗ����ԍX�V���ɌW��ݗ������ł��镽���l�N������o�߂�����́A�ݗ����ԍX�V�����邱�ƂȂ��{�M�ɕs�@�Ɏc�����Ă����Ƃ���A���������Ǘ��ǁi�ȉ��u�������ǁv�Ƃ����B�j�����x�����́A�����ܔN�O�������A�����ɂ��Ė@��l���l�����ɊY������Ƌ^���ɑ���鑊���ȗ��R������Ƃ��āA�������ǎ�C�R����������e�ߏ��̔��t���A��������A��������s���Č����𓌋����ǎ��e��Ɏ��e�����B
�i�܁j�������Ǔ����x�������猴���̈��n�������������Ǔ����R�����́A�R���̌��ʁA�����ܔN�O����l���A�����͖@��l���l�����y�уk�ɊY������|�̔F����s���āA����������ɒʒm�����B
�i�Z�j���̌�A�������Ǔ��ʐR�����ɂ������R���A�퍐�ɑ���ًc�̐\�o�̐R�����o�āA�����ܔN�Z����l���t���ŁA�����ً̈c�̐\�o�͗��R���Ȃ��|�̔퍐�ٌ̍�������A�������ǎ�C�R�����́A���N������O���A�����ɑ��A�E�ٌ������m����ƂƂ��ɁA�ދ������ߏ����t�����B
�i���j�������Ǔ����x�����́A�����ܔN������O���A�E�ދ������ߏ������s���āA�����𓌋����ǎ��e��Ɏ��e������A���������A�������H�c��`�����p�Ɍ����đ��҂����B
�S�@�ݗ����i�F��ؖ����s��t����
�i��j�����́A������N�܌���ܓ��A����㗝�l�Ƃ��āA�������ǂɂ����āA�퍐�ɑ��A�@�����̓��ꍀ�Ɋ�Â��A�������@�ʕ\���̓��{�l�̔z��ғ��̍ݗ����i�ɊY������|�̍ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����s�����B
�i��j�퍐�́A�E��t�\���ɂ��āA������N��ꌎ�����t���ŁA�������@�����ꍀ�l���ɋK�肷������ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�ݗ����i�F��ؖ�������t���Ȃ��|�̏����i�ȉ��u�{���s��t�����v�Ƃ����B�j�����A���ɂ��̎|�ʒm�����B
�O�@���_�y�ё��_�Ɋւ��铖���҂̎咣
�@�{���̑��_�́A�q�P�r�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\���ɂ��A���Y�O���l���@�����ꍀ�ꍆ�A�O�����͎l���Ɍf��������ɓK�����Ȃ����Ƃ����炩�ł���Ƃ��́A�E�ؖ�������t���Ȃ����Ƃ��ł���|��߂Ă���@�{�s�K���Z���̓��܍����������̋K�肪�A�@�����̓��ꍀ�ɂ��ϔC�͈̔͂���E���Ă���A��@�����Ƃ����ׂ����ۂ��i���_�P�j�A�q�Q�r�@�{�s�K���̉E�̋K�肪�L���ł���ꍇ�A�������@�����ꍀ�l���̏����ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�Ƃ��Ă��ꂽ�{���s��t�������A�s���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��i�ȉ��u�a�K��v�Ƃ����B�j�ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ���邩�ۂ��i���_�Q�j�ł���B
�@�E�e���_�Ɋւ��铖���҂̎咣�́A���̂Ƃ���ł���B
�P�@���_�P�ɂ���
�i�����̎咣�j
�@��ʂɈϔC���@�́A�@�����ʓI����̓I�ɈϔC�����͈͂ɂ����Ă̂݁A���̐��肪���������̂ł���A�ϔC���@�ɂ����Ď��������@���̗\�z���Ȃ���߂�u�����Ƃ́A������Ȃ����̂Ƃ����ׂ��Ƃ���A�ȉ��̂Ƃ���A�@�{�s�K���Z���̓��܍����������́A�@�����̓��ꍀ�̈ϔC�͈̔͂�����̂ł���A��@�����Ƃ����ׂ��ł���B
�i��j�@�����̓�́A�{�M�ɏ㗤���悤�Ƃ���O���l�ɂ��āA���炩���ߐ\�����������ꍇ�A���Y�O���l���@�����ꍀ�Ɍf��������ɓK�����Ă��邩�ۂ���R�����A�K�����Ă���ƔF�߂���ꍇ�ɁA���̎|�̏ؖ�������t����ݗ����i�F��ؖ������x���߂����̂ł���B���Ȃ킿�A�@�́A�ݗ����i�̓K�������ؖ����鐧�x�Ƃ��čݗ����i�F��ؖ������x���߂Ă���̂ł����āA�E�ؖ�������t����ɓ������Ă̐R���̑Ώۂ͍ݗ����i�̓K�����̗L���Ɍ����A���̓K�������F�߂���A�E�ؖ�������t�����ׂ����̂Ȃ̂ł���B
�@���̂��Ƃ́A�@�����̓��ꍀ���A�u�O���ꍀ��Ɍf��������ɓK�����Ă���|�̏ؖ�������t���邱�Ƃ��ł���v�ƋK�肵�Ă��邱�Ƃ��炢���Ă����炩�ł���A�܂��A�@�����̓��ꍀ�́u�@���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Ƃ̋K��́A�u���炩���ߐ\�����������Ƃ��́v�Ƒ����������炢���āA�@���ȗ߂ɍݗ����i�F��ؖ����̌�t�\���葱���߂邱�Ƃ݂̂��ϔC���Ă�����̂Ɖ������̂ł���B
�@�E�̂Ƃ���A�@�����̓��ꍀ�́A�@�{�s�K���Z���̓��܍������������K�肷��悤�ɁA�@�����ꍀ�l���Y�����̗L���i�@���Y�����̗L���j�ɂ��Ď��O�R�������邱�Ƃ܂ł��������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��邩��A�@�{�s�K���̉E�̋K��́A�@�����̓��ꍀ�̈ϔC�͈̔͂�����̂ł���B
�i��j���������A�@�̒�߂�葱�ɂ��A�@�����ꍀ�l������߂�㗤�����ɓK�����邩�ۂ��ɂ��ẮA�O���l����㗤�\�����������ꍇ�ɓ����R�������R�����邱�ƂƂȂ��Ă���A�E�̓����R�������s���㗤�R���ɂ��ẮA���ʐR�����ɂ������R����퍐�ɑ���ًc�̐\�o�Ƃ����@�̒�߂�K���葱���ۏႳ��Ă����A�ŏI�I�ɂ́A�퍐�ɂ��㗤���ʋ��i�@�����ꍀ�j�ւ̓����J����Ă���̂ł���B
�@�@�{�s�K���Z���̓��܍������������K�肷��悤�ɁA�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������i�K�ŁA�@�����ꍀ�l���Y�����̗L���ɂ��ĐR�����s�����Ƃ́A�����R�������s���㗤�����K�����̐R������肷�邱�Ƃɂق��Ȃ炸�A�E�̖@�̒�߂�K���葱���Ȃ�������ɂ�����̂ł���A�㗤���ʋ��ւ̓����ǂ���Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł����āA�������葱�I���`�ɔ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�i�퍐�̎咣�j
�i��j�@�����̓�̒�߂�ݗ����i�F��ؖ������x�̎�|�́A�E�ؖ����̌�t���邱�Ƃ��ł���A���Y�O���l���㗤�\���̍ۂɎ��痧���Ȃ���Ȃ�Ȃ��@�����ꍀ�ɒ�߂�㗤�������̍ݗ����i���ɌW��㗤�����ɂ��Ă̗����e�ՂƂȂ邱�Ƃɂ��A��A�̓����葱�̊ȈՐv�����y�ь�������}��Ƃ����_�ɂ�����̂ł���B
�@�@�����̓��ꍀ�̕������疾�炩�Ȃ悤�ɁA���K��Ɋ�Â����s�����ݗ����i�F��ؖ����̏ؖ����鎖���́A�@�����ꍀ�ɒ�߂�ݗ����i���ɌW��㗤�����ɓK�����Ă��邱�Ƃ݂̂Ɍ����A���̑��̏㗤�����ɓK�����Ă��邱�Ƃ܂ł��ؖ�������̂ł͂Ȃ����A�@�́A���̌�t�̗v���ɂ��Ă͓��ɋK�肵�Ă��炸�A�����@���ȗ߂̒�߂�Ƃ���Ɉς˂Ă���B
�@�������āA�ݗ����i�F��ؖ����̖ړI���O�L�̂悤�Ȃ��̂ł���ȏ�A���ɉE�ؖ����̌�t��\������҂��A�@�����ꍀ�ɒ�߂�������̂��̂ɂ͓K�����Ă���Ƃ��Ă��A�@���ꍀ�e���ɊY������ꍇ�ɂ́A���̎҂ɑ��Ă͍�����������Ȃ����Ƃ��\�z�����̂ł����āA���̂悤�ȏꍇ�ɍݗ����i�F��ؖ�������t���邱�Ƃ́A���ؖ������x�̖ړI�ɏƂ炵�ĉ���̕K�v�����Ȃ��A�������Ă����{���\�肵�Ă����ړI�ȊO�Ɉ��p�����댯�����ے肵���Ȃ��̂ł���B
�@���������āA�@�{�s�K���Z���̓��܍������������A�@�����ꍀ�ꍆ�A�O�����͎l���Ɍf��������ɓK�����Ȃ����Ƃ����炩�ł���Ƃ��́A�ݗ����i�F��ؖ�������t���Ȃ����Ƃ��ł���|�K�肵�Ă��邱�Ƃ́A�@�����̓��ꍀ�̋K��̎�|�E�ړI�ɓK�����A�����I�Ȃ��̂Ƃ������Ƃ��ł��A����E�K��̈ϔC�͈̔͂���E������̂ł͂Ȃ��B
�i��j�����́A�@�{�s�K���Z���̓��܍������������K�肷��悤�ɁA�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������i�K�ŁA�@�����ꍀ�l���Y�����̗L���ɂ��ĐR�����s�����Ƃ́A�����R�������s���㗤�����K�����̐R������肷�邱�Ƃɂق��Ȃ炸�A�E�̖@�̒�߂�K���葱���Ȃ�������ɂ�����̂ł���A�㗤���ʋ��ւ̓����ǂ���Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł����āA�������葱�I���`�ɔ�����|�咣����B
�@�������Ȃ���A�ݗ����i�F��ؖ����́A�O���l�����̔������邽�߂̕s���̕����ł͂Ȃ��A�E�ؖ����̌�t���Ȃ��Ƃ��A���ځA���̔�����\�����邱�Ƃ��ł�����̂ł���B���Ƃ��A���Y�O���l���@�����ꍀ�l���̒�߂�㗤�̂��߂̏����ɓK�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A��ʂɍ��͔������ꂸ�A���ǁA���̊O���l�͖{�M�ɓn�q���㗤�R���葱���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���̂��ƂƁA�ݗ����i�F��ؖ����̗L���Ƃ͉�����ʊW���Ȃ��̂ł���B
�@�E�̂Ƃ���A�@�{�s�K���Z���̓��܍����������ɂ��A�@�����ꍀ�l���̒�߂�㗤�����ɓK�����Ȃ��O���l�ɂ��āA�ݗ����i�F��ؖ�������t���Ȃ����ƂƂ��Ă��A����ɂ���ē��Y�O���l���㗤�R���葱���A�㗤���ʋ�����@���D����Ƃ����W�ɂ͂Ȃ��̂ł����āA�����̉E�咣�͎����ł���B
�Q�@���_�Q�ɂ���
�i�����̎咣�j
�@���a�l�N�㌎��������䂪���ɂ��Č��͂��Ă���a�K��́A�����ٔ����ɂ����čٔ��K�͂ƂȂ�A���K��Ɉᔽ���鍑���@���Ƃ��A���K��Ɉᔽ���鍑���@�ɂ��[�u����@�ƔF�肷�鍪���ƂȂ�Ƃ���A�ȉ��̂Ƃ���A�������@�����ꍀ�l���ɋK�肷������ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�Ƃ��Ă��ꂽ�{���s��t�����́A�a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ������̂Ƃ��āA��@�Ƃ����ׂ��ł���B�i��j�a�K���O���ꍀ�́A�u�Ƒ��́A�Љ�̎��R����b�I�ȒP�ʂł���A�Љ�y�э��ɂ��ی���錠����L����B�v�ƒ�߂Ă���B����́A�u�Љ�̎��R����b�I�ȒP�ʁv�ł���Ƒ������Љ�I�@�\�����F���A�Љ�x�Ƃ��Ă̍����y�щƑ��̕ی��ʂ��āA�Ƒ����\������l�̌�����ۏႷ����̂ł���B�܂��A�a�K��ꎵ���́A�Ƒ��ɑ��霓�ӓI���͕s�@�Ȋ����֎~���Ă���B
�i��j�@���ꍀ�l���͉ߋ��Ɉ��ȏ�̌Y�ɏ�����ꂽ���Ƃ��A���������͉ߋ��ɔ��t�s�ׂɊ֗^�������Ƃ��A���ꂼ��㗤���ێ��R�Ƃ��Ē�߂Ă��邪�A������`���I�ɓK�p�����ꍇ�A���������������v�Ɠ������邱�Ƃ͕s�\�ł���A�����͉i���ɉƑ��Ƃ̓��������ۂ���邱�ƂɂȂ�B
�@�������A�����鎖�Ԃ��A�Ƒ��̕ی���K�肵���a�K���O���ꍀ��Ƒ��ɑ��霓�ӓI���͕s�@�Ȋ����֎~�����a�K��ꎵ���Ɉᔽ���邱�Ƃ͖��炩�ł���A�@���ꍀ�e������߂�㗤���ێ��R�ɂ��ẮA�a�K��̉E�e�K��ɓK������悤�����I�ɉ��߂���K�v������Ƃ����ׂ��ł���B
�i�O�j������ɁA�퍐�́A�ߋ��̌Y�������̎��s�P�\���Ԃ̌o�߂Ƃ��̖@����̌��ʁA�����̕v�ł��邁�̉ƒ�̎���A�����������[���ߋ��̎����Ȃ��A�^�ʖڂɍē������邱�ƂĂ��邱�ƁA�������Ăѓ����ł���悤�Q�肷�鐔�����̓��{�l�����邱�ƂȂǁA�l�����ׂ����������l�������A�@���ꍀ�e������߂�㗤���ێ��R���`���I�ɉ��߂��āA�{���s��t�������������̂ł���A�E�����́A�a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�i�퍐�̎咣�j
�i��j�{���s��t�����́A�������@���ꍀ�l���y�ю����ɊY������҂ł��邱�Ƃ����炩�ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ĂȂ��ꂽ���̂ł��邪�A�{���s��t�����ƌ��������̔�������ꂸ�A�㗤�R���葱�����Ȃ����ƂƂ̊ԂɈ��ʊW���Ȃ����Ƃ́A�O�L�P�i�퍐�̎咣�j�i��j�L�ڂ̂Ƃ���ł���B
�@���������āA���������̕v�Ɩ{�M�ɂ����ē����ł��Ȃ����Ƃ́A�{���s��t�����̌��ʂɂ����̂ł͂Ȃ��̂ł����āA�{���s��t�������A�a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ����Ƃ��錴���̎咣�́A�������������ł���B
�i��j�݂̂Ȃ炸�A�ȉ��̂Ƃ���A�@���ꍀ�l���y�ю����́A�a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�ɉ���ᔽ������̂ł͂Ȃ�����A�������@���ꍀ�l���y�ю����ɊY������҂ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ĂȂ��ꂽ�{���s��t�������A�a�K��̉E�e�K��Ɉᔽ������̂łȂ����Ƃ����炩�ł���B
�i�P�j���@�����ꍀ�́A���{�����ɂ����鋏�Z�E�ړ]�̎��R��ۏႷ��ɂƂǂ܂�A�O���l���䂪���ɓ������邱�Ƃɂ��Ă͉���K�肵�Ă��Ȃ����̂ł���A���̂��Ƃ́A���ۊ��K�@��A���Ƃ͊O���l�������`�������̂ł͂Ȃ��A���ʂ̏�Ȃ�����A�O���l���������Ɏ���邩�ǂ����A�܂��A����������ꍇ�ɂ����Ȃ������t���邩���A���Y���Ƃ����R�Ɍ��肷�邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���Ă��邱�ƂƁA���̍l������������̂Ɖ������B
�@���������āA���@��A�O���l�́A�䂪���ɓ������鎩�R��ۏႳ��Ă�����̂łȂ����Ƃ͂������A�ݗ��̌����Ȃ������������ݗ����邱�Ƃ�v�������錠����ۏႳ��Ă�����̂ł��Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B
�i�Q�j������a�K��ɂ��Ă݂Ă��A�ړ��A���Z�A�o���A���̎��R��ۏႵ���a�K������́A���ׂĂ̏o���������R�ł���ׂ��Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�������y�ъO���l�̏o���i����j�Ǝ������̋A���̎��R�i�����l���j��ۏႵ�Ă���ɂƂǂ܂�B�����A�a�K���O���́A���@�I�ɒ��̗̈���ɂ���O���l�ɂ��Ă���A�@���Ɋ�Â��čs��ꂽ����ɂ���ē��Y�̈悩��Ǖ����邱�Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B�����āA�a�K�ɁA���ɊO���l�̓������錠����F�߂�K��͉���ݑ����Ȃ��B
�@�E�̂Ƃ���A�a�K��́A�O���l�̓����E�ݗ��܂ł������Ƃ��ĕۏႵ�Ă�����̂ł͂Ȃ��A���̓_�Ɋւ��Č��@�y�э��ۊ��K�@�ƋO����ɂ�����̂ł���B
�i�R�j�������{�I�ȍl�������炷��A�@���A���̓�����F�߂邱�Ƃ��䂪���ɂƂ��čD�܂����Ȃ��ƔF�߂�O���l�ɂ��Ĉ��̗ތ^���߁A���̗ތ^�ɓ�����O���l�́A�퍐�����ʂɏ㗤�������ׂ��������ƔF�߂�ꍇ�Ɍ���A�{�M�ɏ㗤���邱�Ƃ��ł���Ƃ��邱�Ƃ́A���猛�@���͂a�K�̑��̍��ۖ@�ɒ�G������̂ł͂Ȃ����A�@���ꍀ�l���y�ю����ɊY������悤�Ȏ҂��A��ʂɉ䂪���ɂƂ��čD�܂����Ȃ��ƔF�߂���O���l�ł���Ƃ��邱�Ƃɂ͍����������邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��A���̂悤�ȊO���l�ɂ��Ċ��Ԃ��߂邱�ƂȂ��A�����Ƃ��ď㗤�����ۂ��ׂ��ތ^�ɑ�����Ƃ��邱�Ƃ����猛�@���͂a�K�̑��̍��ۖ@�Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA�a�K��ꎵ���́A���R���I��{���ł���l�i���̈�Ƃ����v���C�o�V�[���̌����̕ۏ���K�肵�����̂ł���A�u���ӓI�ɎႵ���͕s�@�Ɋ����ꖔ�́c�c�s�@�ɍU������Ȃ��v�Ƃ́A�u�@�ɂ��K���Ȏ葱�ɂ�邱�ƂȂ��v�N�Q����Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ɖ�����Ă���A�܂��A�a�K���O���́A�Ƒ��������c�݁A���邢�͍������錠�����ɂ��Ď��R���I�����Ƃ��č��Ɠ��ɂ��N�Q����ی삳��邱�Ƃ��K�肵�����̂ł��邪�A������ی�Ȃ����ۏ�́A�䂪���ōݗ����Ă��邱�ƂR�̑O��Ƃ��Ă�����̂ł���B
�@���������āA�O�L�̂Ƃ���A�@�̋K�肪���@�y�тa�K��ɓK�����A�����I�Ȃ��̂ł���ȏ�A����ɑ����Č����̏㗤�����ۂ���邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��A�����̉E�̌����E���R��N�Q������̂Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A�@���ꍀ�l���y�ю����́A�a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ��̂ł���B
��O�@���ٔ����̔��f
��@���_�P�ɂ���
�P�@�O�L���̈�R�i��j�L�ڂ̂Ƃ���A�@�{�s�K���Z���̓��܍����������́A�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������ꍇ�ɂ����āA�퍐�́A���Y�O���l���@�����ꍀ�ꍆ�A�O�����͎l���Ɍf��������ɓK�����Ȃ����Ƃ����炩�ł���Ƃ��́A�E�ؖ�������t���Ȃ����Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���Ƃ���A�����́A�@�{�s�K���̉E�̋K��́A�ݗ����i�F��ؖ������x���߂��@�����̓��ꍀ�ɂ��ϔC�͈̔͂�����̂ł���A��@�����ł���|�咣����B
�Q�@�������Ȃ���A�����̉E�咣�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̗��R�́A���̂Ƃ���ł���B
�i��j�O�L���̈�Q�L�ڂ̂Ƃ���A�{�@�ɏ㗤���悤�Ƃ���O���l�́A���̏㗤���悤�Ƃ���o���`�ɂ����ē����R�����ɑ��㗤�̐\�������A�@�����ꍀ�ɋK�肷��㗤�̂��߂̏����ɓK�����邱�Ƃ����痧���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A�����ɋK�肷��ݗ����i�Y�������̍ݗ����i�ɌW������ɓK�����邱�Ƃɂ��ẮA�o�����`�ɂ����ĒZ���Ԃŗ����邱�Ƃ͕K�������e�Ղł͂Ȃ����Ƃ���A�����R���葱�̊ȈՐv�����ƌ�������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�@�����̓�́A�{�M�ɏ㗤���悤�Ƃ���O���l���炠�炩���ߐ\�����������ꍇ�ɁA���Y�O���l���@�����ꍀ�ɋK�肷��ݗ����i�ɌW������ɓK�����Ă��邩�ۂ���R�����A�K�����Ă���ƔF�߂���ꍇ�ɂ��̎|�̏ؖ�������t����ݗ����i�F��ؖ������x���߂����̂ł���B
�i��j�����āA�@�����̓��ꍀ�́A�u�@����b�́A�@���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A�c�c�ؖ�������t���邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肵�A�ݗ����i�F��ؖ������x�ɂ��Ă̋�̓I�Ȓ�߂�@���ȗ߂ɈϔC���Ă���Ƃ���A�O���̂Ƃ���A�@�{�s�K���Z���̓��܍����������́A�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������ꍇ�ɂ����āA�퍐�́A���Y�O���l���@�����ꍀ�ꍆ�A�O�����͎l���Ɍf��������ɓK�����Ȃ����Ƃ����炩�ł���Ƃ��́A�E�ؖ�������t���Ȃ����Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B
�@���Ƃ��A�ݗ����i�F��ؖ����́A���Y�O���l���@�����ꍀ�ɋK�肷��ݗ����i�ɌW������ɓK�����Ă��邱�Ƃ��ؖ�������̂ł����āA�����ɋK�肷�鑼�̏㗤�̂��߂̏����ɓK�����Ă��邱�Ƃ��ؖ�������̂ł͂Ȃ����A���Ƃ����Y�O���l���ݗ����i�ɌW������ɓK�����Ă���ꍇ�ł����Ă��A�R���̉ߒ��ɂ����āA���Y�O���l���㗤���ێ��R�ɊY������ȂǑ��̏㗤�̂��߂̏����ɓK�����Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ�A���Ƃ����Y�O���l���㗤�̐\���������Ƃ��Ă��㗤��������錩���݂��Ȃ��Ƃ����ꍇ�ɂ��Ă܂ŁA�ݗ����i�F��ؖ�������t���邱�Ƃ́A�O���̍ݗ����i�F��ؖ������x�̖ړI�ɏƂ炵����̕K�v�����Ȃ��A�������ĉE�ؖ�����{���\�肵���ړI�ȊO�Ɉ��p�����댯�����ے肵���Ȃ����Ƃ��l������A������ꍇ�ɍݗ����i�F��ؖ�������t���Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ����@�{�s�K���Z���̓��܍����������̋K��́A���e�I�ɂ݂āA�@�����̓��ꍀ�ɂ��ϔC�̎�|�ɔ�������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�O�j�܂��A�@�����̓��ꍀ�̋K����A�����I�ɂ݂��ꍇ�A�����́u�@���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Ƃ̕����́A�����̕����́u�c�c�ؖ�������t���邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ��������ɌW����̂Ɖ�����̂������ł���A�����́A���̈ϔC�̎�|�ɔ����Ȃ��͈͂ŁA�@���ȗ߂ɂ��ݗ����i�F��ؖ����̌�t�v���ɂ��Ē�߂邱�Ƃ����ϔC���Ă�����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̓_�Ɋւ��A�����́A�@�����̓��ꍀ�́A�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\���葱���߂邱�Ƃ݂̂�@���ȗ߂ɈϔC���Ă�����̂Ɖ������|�咣���邪�A�����̉E�咣�́A�����̕����ɉ���Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���A�����ł���B
�i�l�j����ɁA�����́A�@�{�s�K���Z���̓��܍������������K�肷��悤�ɁA�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������i�K�ŁA�@�����ꍀ�l������̏㗤�����ɓK�����Ă��邩�ۂ���R�����邱�Ƃ́A�����R�������s���㗤�����K�����̐R������肷�邱�Ƃɂق��Ȃ炸�A�㗤�R���Ɋւ��@����߂��K���葱���Ȃ�������ɂ��A�㗤���ʋ��ւ̓����ǂ���Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł����āA�������葱�I���`�ɔ�����|�咣����B
�@�������Ȃ���A�㗤�R���Ɋւ���葱���߂��@�̋K�肪�A�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������i�K�ŁA���Y�O���l���@�����ꍀ�l���̒�߂�㗤�����ɓK�����Ă��邩�ۂ���퍐���R�����邱�Ƃ��ւ����|�̂��̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���A�܂��A�퍐���咣����Ƃ���A�@�{�s�K���Z���̓��܍����������ɂ��A�@�����ꍀ�l���̒�߂�㗤�����ɓK�����Ȃ��O���l�ɂ��āA�ݗ����i�F��ؖ�������t���Ȃ����ƂƂ��Ă��A����ɂ���ē��Y�O���l���㗤�R���葱���A�㗤���ʋ�����@���D����Ƃ����W�ɂ͂Ȃ��̂ł��邩��A�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������i�K�ŁA�@�����ꍀ�l������̏㗤�����ɓK�����Ă��邩�ۂ���R�����邱�Ƃ��������葱�I���`�ɔ�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���������āA�葱�I���`�Ƃ����ϓ_����݂Ă��A�@�{�s�K���Z���̓��܍������������@�����̓��ꍀ�ɂ��ϔC�͈̔͂�����̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�܁j�ȏ�̂Ƃ���ł��邩��A�@�{�s�K���Z���̓��܍����������̋K��́A�@�����̓��ꍀ�ɂ��ϔC�͈͓̔��Œ�߂�ꂽ���̂ł���A�L���ȋK��Ƃ����ׂ��ł���B
��@���_�Q�ɂ���
�P�@�O�L���̓�L�ڂ̖{���̎����W�ɂ��A�����́A�@���ꍀ�l���́u���{�����͓��{���ȊO�̍��̖@�߂Ɉᔽ���āA��N�ȏ�̒����Ⴕ���͋������͂����ɑ�������Y�ɏ�����ꂽ���Ƃ̂���ҁv�y�ѓ��������́u���t���͂��̎����A���U�A���̏ꏊ�̒��̑����t�ɒ��ڂɊW������Ɩ��ɏ]���������Ƃ̂���ҁv�ɊY�����A�@�����ꍀ�l���ɋK�肷��㗤�̂��߂̏����ɓK�����Ȃ����ƂɂȂ邩��A�퍐�����̂��Ƃ𗝗R�Ƃ��čs�����{���s��t�����́A�@�����̓��ꍀ�y�і@�{�s�K���Z���̓��܍����������̋K��ɏ]�������̂Ƃ����ׂ��Ƃ���A�����́A�Ƒ��̕ی���K�肵���a�K���O���ꍀ��Ƒ��ɑ��霓�ӓI���͕s�@�Ȋ����֎~�����a�K��ꎵ���ɏƂ炵�A�@���ꍀ�e������߂�㗤���ێ��R�ɂ��ẮA����𐧌��I�ɉ��߂���K�v������A�������@�����ꍀ�l���ɋK�肷������ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�Ƃ��Ă��ꂽ�{���s��t�����́A�a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ����|�咣����B
�Q�@�������Ȃ���A�����̉E�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̗��R�́A���̂Ƃ���ł���B
�i��j���@�����ꍀ�́A���{�����ɂ����鋏�Z�E�ړ]�̎��R��ۏႷ��ɂƂǂ܂�A�O���l���䂪���ɓ������邱�Ƃɂ��Ă͉���K�肵�Ă��Ȃ����̂ł���A���̂��Ƃ́A���ۊ��K�@��A���Ƃ͊O���l�������`�������̂ł͂Ȃ��A���ʂ̏�Ȃ�����A�O���l���������Ɏ���邩�ǂ����A�܂��A����������ꍇ�ɂ����Ȃ������t���邩���A���Y���Ƃ����R�Ɍ��肷�邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���Ă��邱�ƂƁA���̍l��������������̂Ɖ������B���������āA���@��A�O���l�́A�䂪���ɓ������鎩�R��ۏႳ��Ă�����̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���i�ō��ُ��a���N�i���j��O�܋�l�����O��N�Z��������@�씻���E�Y�W��ꊪ�Z����Z�Z�O�ŁA�ō��ُ��a�܁Z�N�i�s�c�j����Z�����O�N��Z���l����@�씻���E���W�O��������O�ŎQ�Ɓj�B
�@������a�K��ɂ��Ă݂Ă��A���K��ɂ͊O���l�����R�ɓ������錠����L���邱�Ƃ��߂��K��͑��݂����A���K��ɂ����Ă��A�O���l�̓����̎��R�͕ۏႳ��Ă��Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�i��j���@�����̗p����O���l�̓����ɂ��ẲE�̂悤�Ȋ�{�I�ȍl�������炷��A�@���A���̓�����F�߂邱�Ƃ��䂪���ɂƂ��čD�܂����Ȃ��ƔF�߂�O���l�ɂ��Ĉ��̗ތ^���߁A���̗ތ^�ɓ�����O���l�́A�퍐�����ʂɏ㗤�������ׂ��������ƔF�߂�ꍇ�Ɍ���A�{�M�ɏ㗤���邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ��邱�Ɓi�@���ꍀ�A�����ꍀ�Q�Ɓj�́A���猛�@���͂a�K�̑��̍��ۖ@�ɒ�G������̂ł͂Ȃ����A�@���ꍀ�l���y�ю����ɊY������悤�Ȏ҂��A��ʂɉ䂪���ɂƂ��čD�܂����Ȃ��ƔF�߂���O���l�ł���Ƃ��邱�Ƃɂ͍����������邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��A���̂悤�ȊO���l�ɂ��Ċ��Ԃ��߂邱�ƂȂ��A�����Ƃ��ď㗤�����ۂ��ׂ��ތ^�ɑ�����Ƃ��邱�Ƃɂ��A���@���͂a�K�̑��̍��ۖ@�Ɉᔽ����_�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�i�O�j�a�K��ꎵ���́A�Ƒ��ɑ��霓�ӓI���͕s�@�Ȋ�����̕ی���K�肵�A�a�K���O���ꍀ�́A�Ƒ��̕ی���K�肵�Ă��邪�A�O���̂Ƃ���A�a�K��́A�O���l�̓����̎��R����ʓI�ɕۏႷ����̂ł͂Ȃ��A�܂��A�@���ꍀ�l���y�ю����̏㗤���ێ��R�̒�߂��A���ꎩ�̂Ƃ��č�������L������̂ł��邱�Ƃ��炷��A���ɕv�w�̈�����E�̏㗤���ێ��R�ɊY�����錋�ʁA���̕v�w���䂪���ɂ����ē������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ��Ă��A���̂��Ƃɂ�蒼���ɂa�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�ɂ��ۏႳ�ꂽ�����E���R���N�Q���ꂽ�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@���Ƃ��A�ʂ̎��Ăɂ���ẮA�@���ꍀ�l���y�ю����ɋK�肷��㗤���ێ��R�ɊY������O���l�ł����Ă��A�v�w���̉Ƒ��W�̕ی�Ƃ����ϓ_����A���̏㗤��F�߂邱�Ƃ𑊓��Ƃ��ׂ����ʂȎ������ꍇ������A���̂悤�ȏꍇ�ɓ��Y�O���l�̏㗤�������Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̑[�u���a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ����ƕ]�������ꍇ�����蓾�邪�A���̂悤�ȓ��ʂȎ���ɂ��ẮA���Y�O���l���獸�̔����\�����������ۂ�@��������ً̈c�̐\�o�i�㗤�����ɓK�����Ȃ��ƔF�肳�ꂽ�O���l�̔퍐�ɑ���ًc�̐\�o�j���������ۂɍl������Α������̂ł���A�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����������i�K�ɂ����āA�@���ꍀ�l���y�ю����̋K�肷��㗤���ێ��R�𐧌��I�ɉ��߂���K�v�͂Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�i�l�j�ȏ�̂Ƃ���ł��邩��A�������@�����ꍀ�l���ɋK�肷������ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�Ƃ��Ă��ꂽ�{���s��t�����ɁA�a�K��ꎵ���y�ѓ�O���ꍀ�Ɉᔽ����_�͂Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
��l�@���_
�@��������ƁA�������@�����ꍀ�l���ɋK�肷������ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�Ƃ��Ă��ꂽ�{���s��t��������@�ł���Ƃ������Ƃ͂ł����A�����̖{�������͗��R���Ȃ�����A��������p���邱�ƂƂ��A�i�ה�p�̕��S�ɂ��āA�s�������i�ז@�����A�����i�ז@�Z�����K�p���āA�啶�̂Ƃ��蔻������B
������R��
�@�i�ٔ����ٔ����@���]�@�ٔ����@���c���@�ٔ����@�c�����j
�����n���ٔ���
�����P�O�N�i�s�E�j��V�V��
�����P�P�N�P�P���P�P
�啶
��@�����̐��������p����B
��@�i�ה�p�͌����̕��S�Ƃ���B
�����y�ї��R
���@����
�@�퍐���A������Z�N�O���O�Z���t���Ō����ɑ��Ă����ݗ����i�ύX�������Ȃ��|�̏������������B
���@���Ă̊T�v
�@�{���́A�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j�ʕ\���́u���w�v�̎��i�Ŗ{�M�ɍݗ����Ă����O���l�ł��錴�����A�퍐�ɑ��A���\�́u�Z�p�v�ւ̍ݗ����i�̕ύX����\�������Ƃ���A�퍐����A�E�\����s���Ƃ��ꂽ���Ƃ���A�E�s�������̎���������߂����Ăł���B
��@�ݗ����i�ύX�ɌW��W�@�߂̊T�v
�P�@�ݗ����i��L����O���l�́A���̎҂̗L����ݗ����i�̕ύX���邱�Ƃ��ł��i�@��Z���ꍀ�j�A�ݗ����i�̕ύX���悤�Ƃ���O���l�́A�@���ȗ߂Œ�߂�葱�ɂ��A�퍐�ɑ��ݗ����i�̕ύX��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i����j�B
�Q�@�E�\�����������ꍇ�ɂ́A�퍐�́A���Y�O���l����o���������ɂ��ݗ����i�̕ύX��K���ƔF�߂�ɑ���鑊���̗��R������Ƃ��Ɍ���A����������邱�Ƃ��ł���i�����O���j�B
�@�ݗ����i�́A�@�ʕ\���y�ё��̏㗓�Ɍf����Ƃ���ł���A�ʕ\���̏㗓�̍ݗ����i�������čݗ�����҂́A���Y�ݗ����i�ɉ����A�{�M�ɂ����ē��\�̉����Ɍf���銈�����s�����Ƃ��ł���i�@����̓��j�B
�R�@�ݗ����i�̂����u�Z�p�v�̍ݗ����i�������čݗ�����҂́A�{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��čs�����w�A�H�w���̑��̎��R�Ȋw�̕���ɑ�����Z�p���͒m����v����Ɩ��ɏ]�����銈�����s�����Ƃ��ł���i�@�ʕ\���̓�j�B
��@�O��ƂȂ鎖��
���̊e�����͓����ҊԂɑ������Ȃ��B
�P�@�����̗����y�эݗ��̌o��
�i��j�@�����́A���a�l�ܔN�i��㎵�Z�N�j�Z�����A���ؐl�����a���i�ȉ��u�����v�Ƃ����B�j�ɂ����ďo�����A�����̍��Ђ�L����O���l�ł���B
�i��j�@�����́A�����l�N��������A�������Ǘ��ǁi�ȉ��u�����ǁv�Ƃ����B�j�ɂ����āA���s���l�Ԉꔪ�����݂̓��k�O������w�Z��ʂ��āA���Z�œ��{�������ē��{�̑�w�֓��w���������Ƃ̗��R�ōݗ����i�F��ؖ����̌�t��\�����A���N������Z���A�퍐����@�ʕ\���ɒ�߂�ݗ����i�u�A�w�v�ɌW��ݗ����i�F��ؖ����̌�t�����B
�i�O�j�@�����́A���N��ꌎ����A�{�M�V�������ۋ�`�ɓ������A���������Ǘ��ǁi�ȉ��u�������ǁv�Ƃ����B�j���c�x�Ǔ����R��������A�ݗ����i�u�A�w�v�y�эݗ����ԘZ����t�^����āA�{�M�ɏ㗤�����B
�i�l�j�@�����́A�����ܔN�l����O���y�ѓ��N��ꌎ����̊e���ɁA�����ǂɂ����āA�ݗ����ԍX�V���\�����s���A�e�����A���ꂼ��ݗ����Ԃ�Z���Ƃ���X�V�������B
�i�܁j�@�����́A�����Z�N�l����Z���A�����ǂɂ����āA���k��w����w���̌������ƂȂ������߁A�����Đ��̕����������Ƃ��āA�A�w�̍ݗ����i����A���w�̍ݗ����i�ւ̍ݗ����i�ύX���\�����s���A�������A�ݗ����i���u���w�v�A�ݗ����Ԃ���N�Ƃ���ݗ����i�̕ύX�������B
�i�Z�j�@�����́A�������N�l����l���A�������N�l����Z���y�ѕ�����N�l����Z���̊e���ɁA�����ǂɂ����āA�ݗ����ԍX�V���\�����s���A���ꂼ��A�������N�Z����Z���A�������N�Z�������y�ѕ�����N�܌������̊e���ɁA�ݗ����Ԃ���N�Ƃ���X�V�������B
�Q�@�{���s�������Ɏ���o��
�i��j�@�����́A������Z�N�ꌎ�Z���A��t�s���l�撷�ɑ��A���s����Z�|��܂����t�s���O�|�O�|�ꎵ�|�O�Z�Z�ɋ��Z�n�̕ύX�������Ƃ��āA���Z�n�ύX�o�^�������B
�i��j�@�����́A������l���A�������ǂɂ����āA���N�l��������瓌���s�i����O�ԘZ�����݂̃A�C�G�X�r�[���p�V�X�e��������Ёi�ȉ��u�A�C�G�X�r�[�v�Ƃ����B�j�ɏA�E���A�R���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�̃V�X�e���G���W�j�A�Ƃ��ĉғ��������Ƃ��āA�ݗ����i���u���w�v����u�Z�p�v�֕ύX�������|�̕ύX���\���i�ȉ��u�{���\���v�Ƃ����B�j�������B
�i�O�j�@�����́A���N�����A�{�錧����x�@���ɒ��쌠�@�ᔽ�e�^�őߕ߂���A���N�O���l���A���쌠�҂̋������Ȃ��ŃR���s���[�^�[�v���O�����̒��앨�����A���l�ɗL���ŔЕz���Ē��쌠��N�Q�����Ƃ��āA���@�ᔽ�̍߂Ő��n���ٔ����ɋN�i����A����ɁA������Z���A���l�̓��@�ᔽ�̍߂œ��ٔ����ɒNjN�i���ꂽ�i�ȉ��A�e�N�i���āu�{���N�i�v�Ƃ����A�E�̊e���쌠�@�ᔽ�퍐�������u�{���Y�������v�Ƃ����B�j�B
�i�l�j�@���̌�A�����́A������Z���A�����Z������s�È�O��|�ꏊ�݂̂����Ƃ��ĕێ߂��ꂽ�B
�i�܁j�@�퍐�́A���N�O���O�Z���A�{�M�ň���I�A�p���I�Ɂu�Z�p�v�̍ݗ����i�ɊY�����銈�����s������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�ݗ����i�̕ύX��K���ƔF�߂�ɑ���鑊���̗��R���Ȃ��Ɣ��f���āA�{���\����s���Ƃ��鏈���i�ȉ��u�{���s�������v�Ƃ����B�j�������B
�O�@�ݗ����i�ύX���\���ɑ��鋑�ۏ�������@�ƂȂ�ꍇ�@�́A�O�L�̂Ƃ���A�䂪���ɍݗ�����O���l�̍ݗ����i�̕ύX�ɂ��āA�퍐�������K���ƔF�߂�ɑ���鑊���̗��R������Ɣ��f�����ꍇ�Ɍ��苖���邱�ƂƂ��Ă���Ƃ���i�@��Z���ꍀ�A�O���j�A�E�̑����̗��R���������Ă��邩�ǂ����ɂ��ẮA�O���l�ɑ���o�����̊Ǘ��y�эݗ��̋K���̖ړI�ł��鍑���̎����ƑP�ǂ̕����̈ێ��A�ی��E�q���̊m�ہA�J���s��̈���Ȃǂ̍��v�̕ێ��̌��n�ɗ����āA�\���҂̐\�����R�̓��ۂ݂̂Ȃ炸�A���Y�O���l�̍ݗ����̈�̍s��A�����̐����E�o�ρE�Љ�̏�����A���ۏ�A�O���W�A���ۗ���ȂǏ��ʂ̎�������Ⴍ���A���X�ɉ������I�m�Ȕ��f�����Ȃ���Ȃ炸�A���̂悤�Ȕ��f�́A�����̐�����A�o�����Ǘ��s���̐ӔC���퍐�̍ٗʂɔC����̂łȂ���ΓK�Ȍ��ʂ����҂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł��邩��A�E�̑����̗��R���������Ă��邩�ǂ����ɂ��Ă̔퍐�̍ٗʌ��͈͍̔͂L�͂Ȃ��̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@���������āA�ݗ����i�̕ύX�̋��ۂ̔��f���ٗʌ��̈�E���͗��p�Ƃ��Ĉ�@�ƂȂ�̂́A�E���f���S�������̊�b���������͎Љ�ʔO�㒘�����Ó������������Ƃ����炩�ł���ꍇ�Ɍ�����Ɖ����ׂ��ł���B
�i�ݗ����i�ύX���\���ɑ��鋑�ۏ�������@�ƂȂ�͉̂E�̂悤�ȏꍇ�Ɍ����Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�{���̓����ҊԂɂ����Ă��A�������Ȃ��B�j�B
�l�@���_
�@�{���̑��_�́A�{���s�������ɌW��퍐�̔��f�ɍٗʌ��̈�E���͗��p���Ȃ��������A��̓I�ɂ́A�퍐�̔��f���A�S�������̊�b���������͎Љ�ʔO�㒘�����Ó������������Ƃ����炩�ł��邩�ۂ��ł���B
�܁@�����ґo���̎咣
�i�����̎咣�j
�@�퍐�́A�������{���Y�������ɂ��ċN�i���ꂽ���Ƃ���A�N�i�����悤�ȊO���l�͂��Ȃ킿�f�s���P�ǂłȂ��ƌ��߂��A�E�����Ƃ���ɕt�����鎖���������āA�{���s���������s�������̂ł���B
�@�������A�E�̂悤�Ȕ��f�Ɋ�Â��čs��ꂽ�{���s�������́A���̂Ƃ���A�S�������̊�b�������A�܂��A�����ɑ���]�����������������Ă��邱�Ƃ͖����ł��邩��A���������ׂ��ł���B
�P�@�{���N�i��{���s�������̔��f�̊�b�Ƃ��邱�Ƃɂ���
�i��j�@�����́A�{���Y�������̌��i�����Ƃ��ꂽ���쌠�@�ᔽ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
�@�����́A�ߕ߂ɓ��������x�@�����玩������������A�܂��ƍߎ��������ׂĔF�߂�Γ��k��w��w�@�ɂ������Ǘ��ǂɂ����Ȃ��Ɩ����Ȃǂ̗��v�U���������߁A�{���i�K�ɂ����āA�g�Ɋo�����Ȃ��ɂ�������炸�A�ƍs��F�߂鋕�U�̋��q���s�����B�������A�����́A�{���s���������ď��߂āA�E�x�@���̖����U�ł��������Ƃ����A���̌�͂���߂ł��邱�Ƃ��咣���Č��݂Ɏ����Ă���B
�i��j�@�ݗ����i�ύX�̋��ۂ̔��f�ɓ������āA�N�i���ꂽ���Ƃ������ĕs���v�Ɏ�舵�����Ƃ́A�Y���葱�ɂ����閳�ߐ���̌����i���@�O�����ꍀ�Q�Ɓj��j�邱�ƂɂȂ�A�䂪������y���Ă���s���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��i�ȉ��u�a�K��v�Ƃ����B�j�ɂ�������i���@�㔪��j�B
�@���ہA�O���l���N�i���ꂽ���Ƃ𗝗R�ɍݗ��̌�����D����ƂȂ�ƁA�s�@�؍݂̏�ԂŖh�䌠���s�g��������A�ɂ߂ĕs����ȏ�Ԃɒu����邱�ƂɂȂ�B�ꍇ�ɂ���ẮA�Y���퍐�l�ɑ��A�ٔ��̌o�߂Ɩ��W�ɁA�s�@�؍݂𗝗R�Ƃ��đދ���������������邱�Ƃ��l�����邪�A��������ƁA���̎҂����ߔ������Ă��ꂪ�m�肵���Ƃ��Ă��A���̌�ɍݗ����i�邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł���A���ǁA���̉ߌ�ɂ���čݗ�����D���錋�ʂƂȂ�A�퍐�l�̍ٔ����錠���i���@�O����j�͎���Ȃ����ƂɂȂ�B
�@���������āA�N�i�����ꂽ�Ƃ̈ꎖ�������čݗ����i�̔��f�̊�b�ɂ��邱�Ƃ́A�Љ�ʔO�㒘�����Ó������������Ƃ����炩�ł���B
�Q�@���̑��̗��R�ɂ���
�i��j�@�Z�p�҂Ƃ��Ă̓K�i���ɂ���
�@�����́A�{���̓��k�t�͑�w�y�щ䂪���̓��k��w��w�@�ŃR���s���[�^�[�ɂ�鍂�x�Ȑ��Z�p���C�߂����̂ł���A���x�Z�p�ҁi�V�X�e���G���W�j�A�j�Ƃ��ăA�C�G�X�r�[�ɏA�E�����肵�Ă������̂ł���B
�@�퍐�́A���������o���ꂽ���k�t�͑�w�̗��C�ؖ����ɂ���āA�����̋Z�p�҂Ƃ��Ă̓K�i���͐R�����A���ɗ����ς݂ł���������A�Z�p�҂Ƃ��Ă̓K�i�����{���s�������̗��R�ɂȂ�Ƃ͍l�����Ȃ��B
�i��j�@�{���\�������̌����̒ʋΉ\���ɂ���
�@�����́A�{���s�����������A�ێ߂̍ۂ̐����Z�������s���̂����ł��������߁A�A�C�G�X�r�[�̏��ݒn�ł��铌���s�i���ɒʋ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A����́A�ߕ߁A�N�i�Ɋ�Â��̕ω��ł����āA�\�����ɂ́A�\���ł��Ȃ��������Ƃł���B
�@�܂��A�Y���ٔ��̍s���ɂ���ẮA�������A�C�G�X�r�[�ɋΖ�����\���͂������̂ł��邩��A���̂��Ƃ��m���߂Ȃ��܂܂ɋ@�B�I�ɒʋΉ\���f�����͖̂��炩�Ɍ��ł���B
�i�퍐�̎咣�j
�P�@�{���s�������ɂ���
�@�퍐�́A���L�̊e�������𑍍��I�ɍl�����A�����ɂ��ẮA�{�M�ň���I�A�p���I�Ɂu�Z�p�v�̍ݗ����i�ɊY�����銈�����s������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ����Ƃ���A�ݗ����i�̕ύX��K���ƔF�߂�ɑ���鑊���̗��R���Ȃ��Ɣ��f�������̂ł���B
�@�@�@�L
�q�P�r�@�����́A�{���s�����������A���쌠�҂̋������Ȃ��ŃR���s���[�^�[�v���O�����̒��앨�����A���l�ɔЕz���Ē��쌠��N�Q�����Ƃ��ċN�i����Ă����̂ł���A���̂悤�ȗe�^�ŌY���i�ǂ���Ă���҂��䂪���ɂ����ăV�X�e���G���W�j�A�Ƃ��ĉғ�����͍̂D�܂����Ȃ��Ǝv��ꂽ����
�q�Q�r�@�����́A�{���\���܂ŁA���k��w��w�@�ŋ���S���w���U���Ă������̂ł���A���̓��e�́A�u�Z�p�v�̍ݗ����i�ɂ��F�߂��銈���̓��e�Ƃ͒������֘A���̒Ⴂ���̂ł���������
�q�R�r�@�{���\���ɍۂ��āA�����̋��Z�n�͐�t�s���O�|�O�|�ꎵ�|�O�Z�Z�Ƃ���Ă���A�����͂������瓌���s�i���Ə��݂̃A�C�G�X�r�[�܂ŒʋΗ\��ł������Ǝv����Ƃ���A�����̕ێߒ��̐����Z���͐��s�È�O��|�ꂁ���ƂȂ��Ă���A�E�����Z������A�C�G�X�r�[�܂Œʋ��邱�Ƃ͎����㍢��ł���ƔF�߂�ꂽ����
�Q�@�����̍ٗʌ��̈�E���͗��p�̎咣�ɑ��锽�_
�i��j�@�{���N�i���ݗ��ɌW��\���̋��ۂ̔��f�ɍl�����邱�Ƃ̉ۂɂ���
�i�P�j�@�����ɑ���{���Y�������ɂ��ẮA���n���ٔ����ɂ����āA�L�ߔ����������n����Ă���A�����ɂ��āA�V�X�e���G���W�j�A�Ƃ��Ċ������邱�Ƃ����e���ׂ��łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�i�Q�j�@���ߐ���̌����́A���̌Y�����̔����̉ۂ����Ƃ����Y���葱�ō̗p����Ă�����̂ł��邩��A���̌������A�Y���葱�Ƃ͂��悻���x�ړI���قɂ���o�����Ǘ��s���ɒ����ɓK�p�����Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�L�ߔ����m��O�ɍs��ꂽ�ݗ��ɌW��\���̋��ۂ̔��f�ɍۂ��A�\���҂ł���O���l�̍s��f����ɂ��ẮA�Y���葱�ɂ�����N�i�����́A�������m�肵�Ă��Ȃ��Ă��A���f�̏d�v�Ȏ����ƂȂ�͓̂��R�ł���A�Y���葱�ɂ����閳�ߐ���̌������A�ݗ��ɌW��\���̋��ۂ̔��f�ɂ����Ă��̂悤�Ȏ������l�����Ȃ��Ƃ��������܂Ŋ܂ނƂ��鍪���͂Ȃ��B
�i�R�j�@�܂��A�����́A�N�i���ꂽ���Ƃ𗝗R�ɍݗ��̌�����D����ƁA�ٔ��̌o�߂Ɩ��W�ɕs�@�؍݂𗝗R�ɑދ���������������邱�Ƃ��l�����A�����Ȃ�Ɣ퍐�l�̍ٔ����錠���͎���Ȃ����ƂɂȂ�Ǝ咣���邪�A�ݗ����i�ύX�葱�Ƒދ������葱�͕ʌ̎葱�ł��邩��A�E�̌����̎咣�́A�����\�z�����s����������䂷����̂ɉ߂����A���ꎩ�̎����ł��邵�A�Y���i�ǂ���Ă���O���l�ɂ��āA�������m�肷��O�ɑދ������������Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă��A����ɂ���Ē����ɔ퍐�l�̍ٔ����錠�����N�Q�������̂ł��Ȃ��B
�i��j�@�Ζ��n�y�ь������Z�n�ɂ���
�@�����́A�Y���ٔ���������Ƒ��������Ƃ��āA���s���Ɏw�肳�ꂽ�����Z���ȊO�̏ꏊ�ɕێ߂̐����Z����ύX����ӎv��L���Ă��Ȃ������B
�@�����āA�{���s���������ɂ����āA�����̕ێߒ��̐����Z�����A�������A�C�G�X�r�[�܂Œʋ��邱�Ƃ������㍢��Ƃ݂�����s���ɏ��݂���Z���ł��������Ƃ���A�������A�C�G�X�s�[�ɂ����ĉғ����邱�Ƃ͍���ł���ƔF�߂��̂ł���A���Ɍ����͓����ł̏A�E������������Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@���̂悤�Ȏ�����A�퍐���{���s�������ɂ����āA�{�M�ň���I�A�p���I�Ɂu�Z�p�v�̍ݗ����i�ɊY�����銈�����s���邩�ۂ��f����ہA���ɓI�Ȉ�v�f�Ƃ��čl�������Ƃ��Ă��A���Y���f�͎����̊�b���������̂Ƃ͂����Ȃ����A�����ɑ���]���������ɍ��������������̂Ƃ������Ȃ��B
�i�O�j�@���������āA�������A�{�M�ň���I�A�p���I�Ɂu�Z�p�v�̍ݗ����i�ɊY�����銈�����s����ɂȂ��������Ƃ́A���炩�ł���A�����̑f�s�⊈���̈��萫�E�p�����ɏd��Ȗ��_���F�߂��邱�Ƃ��炷��A�������A�����̑�w�ɂ����ăR���s���[�^�[�v���O���~���O�Ɋւ���P�ʂ��C�����Ă���Ƃ��Ă��A����ɂ���Ĕ퍐�̑O�L���f���������������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
��O�@���ٔ����̔��f
��@�퍐���ݗ����i�̕ύX�̋��ۂ̔��f�ɂ��čL�͂ȍٗʌ���L���Ă��邱�Ƃ͑O�L�̂Ƃ���ł���Ƃ���A�퍐�́A�{���\���ɂ��āA�O�L�u�퍐�̎咣�v�P�L�ڂ́q�P�r�Ȃ����q�R�r�̊e�������𑍍��I�ɍl�����A�����ɂ��ẮA�{�M�ň���I�A�p���I�Ɂu�Z�p�v�̍ݗ����i�ɊY�����銈�����s������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ����Ƃ���A�ݗ����i�̕ύX��K���ƔF�߂�ɑ���鑊���̗��R���Ȃ��Ɣ��f�������̂ł���Ǝ咣����B
�@�����ŁA�ȉ��A�{���\���ɑ���퍐�̉E�̔��f�������̎咣����悤�Ɏ����̊�b���������͎Љ�ʔO�㒘�����Ó������������̂ł��邩�ۂ����������邱�ƂƂ���B
��@�؋��i�b��A�����A����Z�A����O�A����l�A����A���O�A����A�����{�l�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�ȉ��̎������F�߂���B
�P�i��j�@�����́A�������N�i��㔪��N�j�A�{���̓��k�t�͑�w�}���`���f�B�A����w���ɓ��w���A�����l�N�i�����N�j��ꌎ�A�K�v�ȒP�ʂ��C�����āA����w�𑲋Ƃ������A���̒��ɂ́A�r�W���A���Z�p�W�ƃR���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�W�̒P�ʂ̗��C���܂܂�Ă����B
�@�������A����w�Ő�U�����}���`���f�B�A����́A�ŐV�̃}���`���f�B�A�Z�p�ɃR���s���[�^�[�Z�p���������āA�����ʓI�ȃp�\�R�����ނ�r�f�I���ނ̍쐬����������w��ł���A����w�ɂ����Ă͗��Ȍn�Ȗڂƈ����Ă���B
�i��j�@�����́A�䂪���̓��k��w��w�@�ɂ����Đ�啪��̌���������ɐi�߂邽�߁A�����l�N��ꌎ�A�䂪���ɓ������A���s���݂̓��k�O������w�Z�ɓ��w���ē��{����w�сA�����Z�N�O���ɓ��Z�𑲋Ƃ�����A���N�l���A���k��w����w���Ɍ������Ƃ��ē��w���A�������N�l���A����w��w�@����w�����Ȕ��m�O���ے��ɓ��w���āA����S���w���U�����B
�@���̌�A�����́A������N�ɂ͏C�m�����擾���āA���N�l���A�������Ȕ��m����ے��ɐi�w�����B
�@���������k��w�ɂ����Đ�U�����e�[�}�ł���}���`���f�B�A����̌����́A���̕��͂ɃR���s���[�^�[�����p���邱�Ƃ͂�����̂́A�����܂ŋ���w�I�Ȗʂ���̌����ł���A���l���A����w��w�@����w�����Ȕ��m�O���ے��𑲋Ƃ��A�C�m�����擾����ɍۂ��č쐬�����C�m�_���u�O�u����ɂ��r�f�I���ނ̊w�K���ʂɂ��Ă̌����v�́A�r�W���A�����ނ̎����O�Ɋw�K�҂ɑ��Ď����^�����ꍇ�A���̂悤�Ȏ����^���Ȃ��ꍇ�ɔ䂵�Ă�荂��������ʂ�������̂��ۂ����e�[�}�Ƃ��������_���ł������B
�Q�i��j�@�퍐�́A�O�L�̂Ƃ���A������Z�N�O���l���A���쌠�@�ᔽ�̍߂ŋN�i���ꂽ���A�{���Y�������ɌW����i�����́A�퍐�l�́A���̓̎҂Ƌ��d�̏�A�@��̏��O���R���Ȃ��A�����쌠�҂̋������Ȃ��ŁA�������N��ꔪ������y�ѓ�����ܓ��̑O����A���s�ē��ɂ����āA�A�����J���O���}�C�N���\�t�g�R�[�|���[�V���������쌠��L����v���O�����̒��앨�ł���u�}�C�N���\�t�g�E�I�t�B�X�E�t�H�[�E�E�C���h�E�Y��܁E�o�[�W�������E�Z�E�v���t�F�b�V���i���E�G�f�B�V�����v���V�[�f�B�[�A�[���O���ɕ������A���̂���A�����ɂ����āA�����s���ݏZ�̎O���̍w����]�҂ɑ��A���V�[�f�B�[�A�[���O����L���ŗX���Еz���A�����āA�E�}�C�N���\�t�g�R�[�|���[�V�����̒��쌠��N�Q�����Ƃ������̂ł���B
�i��j�@�����́A�ߕ߁A�����A�N�i�̊e�i�K�ɂ����ẮA���Ȃ̖��߂��咣���邱�Ƃ͂Ȃ��A�ێ߂�ۂɂ��A���l�ł��������A�{���s�������̌�ł���{���Y�������̑�������ɂ����āA���߂Ď��Ȃ̖��߂��咣����Ɏ������B
�i�O�j�@�������A�{���Y�������̑��R�ٔ����ł�����n���ٔ����́A���i������F�肵�A������Z�N���������A�����ɑ��A���쌠�@������ꍆ�A���O���ꍀ�ᔽ�ɂ��A������N�Z���A���s�P�\�O�N�̗L�ߔ����������n�����B
�i�l�j�@�����́A�E������s���Ƃ��āA�T�i���N�������A��䍂���ٔ����́A������Z�N���������A��������j�����A������Z���A���s�P�\�O�N�Ƃ��锻���������n�����B
�i�܁j�@�Ȃ��A�����́A�{���N�i��A���s�ŏ��݂̂����𐧌��Z���Ƃ��ĕێ߂��ꂽ���A���̌�A�ٔ����ɑ��ĉE�����Z���̕ύX��\�����Ă����Ƃ͂Ȃ������B
�R�@�����́A������Z�N���߂���A�r�W�l�X�\�t�g�E�F�A�̊J���ɏ]������\��œ����s�i���Ə��݂̃A�C�G�X�r�[����A�E�̓���������߁A�ݗ����i�u�Z�p�v���擾������œ��ЂɏA�E���A�R���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�̃V�X�e���G���W�j�A�Ƃ��ĉғ����悤�ƍl���A�{���\�����s�����ƂƂ������̂ł���B
�O�P�@�E�̔F�莖���y�ёO�L�����̂Ȃ������ɂ��A�{���s�����������A�������A���쌠�@�ᔽ�̍߂�Ƃ����Ƃ��Đ��n���ٔ����ɌY���i�ǂ���Ă������ƁA�������A�{���\���܂ŁA���k��w��w�@�ŋ���S���w���U���Ă������ƁA�����́A�{���Y�������ɂ����đߕߌ�������A���̌�ێ߂��ꂽ���A���̐����Z���́A���s�È�O��|�ꂁ���ƒ�߂��Ă������Ƃ́A��������q�ϓI�����ɕ������Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B
�Q�i��j�@�����āA�����́A�䂪���̊�Ƃɂ����āA�R���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�̃V�X�e���G���W�j�A�Ƃ��ĉғ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ė{���\���ɋy���̂ł���Ƃ���A�E�Y���i�ǂ������e�́A�R���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�쌠�҂ɖ��f�ŕ����y�єЕz�����Ƃ������쌠�@�ᔽ�̎����ł��邩��A�퍐���A���ɂ��̂悤�Ȍ��i�����ŌY���i�ǂ���Ă���҂ɑ��āA�ݗ����i��ύX���ĉ䂪���ɂ����ăV�X�e���G���W�j�A�Ƃ��ĉғ��ł���ݗ����i��V���ɕt�^���邱�Ƃ͍D�܂����Ȃ��Ɣ��f�������Ƃ��s�����ł���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��āA�����́A�ݗ����i�ύX�̋��ۂ̔��f�ɓ������āA�������N�i���ꂽ�Ƃ̈ꎖ�������ĕs���v�Ɉ������Ƃ͌��@�Ȃ����a�K��ɂ���ĊO���l�ɂ��ۏႳ��Ă��閳�ߐ���̌����ɔ�����Ǝ咣����B
�@�������A���ߐ���̌����́A���̌Y�����̔�����O��Ƃ���Y���葱�ɑÓ�������̂ł����āA���x�ړI���قɂ���ݗ����i�ύX���ۂ̔��f�ɂ����āA�N�i���ꂽ�Ƃ̎�������؍l�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ܂ʼn����ׂ������͑����Ȃ��B
�@�{���ɂ����Ă��A�퍐�́A�����ɑ��Ė{���N�i�����ꂽ���Ƃ��璼���Ɍ������E���i�����ɌW��ƍ߂�Ƃ������̂ł���Ƃ̎�����F�肵�Ă����{���\���ɑ��鋖�ۂ̔��f�̊�b�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�V�X�e���G���W�j�A�Ƃ��ĉғ����邱�Ƃ���]���čݗ����i�u�Z�p�v�ւ̕ύX��\�����Ă��錴�����A�{���s�����������A�R���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�쌠�҂ɖ��f�ŕ����y�єЕz�����Ƃ̓��e�̒��쌠�@�ᔽ�̌��i�����ŌY���i�ǂ��Ă���Ƃ����q�ϓI�������E�̔��f�̊�b�Ƃ��čl���������̂ł���ƔF�߂��A���̓_�Ɋւ���퍐�̔��f���L�����ʂ̎���𑍍��I�Ɋ��Ă��čs����ׂ����Ƃ��炷��A�퍐�����̂悤�Ȏ������E���f�̊�b�Ƃ������Ƃ����@���͂a�K��Ɉᔽ�����@�Ȃ��̂ł���Ɖ�����Ȃ��B
�i��j�@�܂��A���������k��w��w�@����w�����Ȍ�����m�ے��ɂ����Đ�U�����}���`���f�B�A����̌����̎傽��ړI�̓}���`���f�B�A�Z�p���𗘗p����������ʂ̌���ɂ���A�{���\���̒��O�܂ł̌������s���Ă��������̓��e���A�u�Z�p�v�̎��i�ɂ�茴�����]�����邱�ƂƂȂ�R���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�J���Ƃ͕K���������ڂȊ֘A��L���Ă����Ƃ܂ł͔F�߂��Ȃ�����A�E�̈Ӗ��ɂ����āA�퍐���A���̓_���A�{���\���ɑ��锻�f�ɂ�������ɓI�Ȏ����Ƃ��ĕ]���������Ƃ��s�����ł���Ƃ܂ł͂����Ȃ��B
�i�O�j�@����ɁA�����́A�{���s�����������A�ێߒ��ŁA���̐����Z���́A���s�È�O��|�ꂁ���ƒ�߂��Ă������߁A���Ȃ��Ƃ��{���Y�������̑��R�����������n�����܂ł́A�����́A�E�̐����Z�����瓌���s�i���Ə��݂̃A�C�G�X�r�[�֒ʋ��邱�Ƃ͎�����s�\�ȏ�Ԃɂ���A���̂悤�ȏ�Ԃ��A�����ɉ��������ƌ����܂��ɂ��Ȃ��������Ƃ͖��炩�ł��邩��A�퍐���A���̓_��{���\���ɑ��锻�f�ɂ�������ɓI�Ȏ����Ƃ��ĕ]���������Ƃ��s�����ł���Ƃ܂ł͂����Ȃ��B
�R�@�E�̂Ƃ���ł��邩��A�{���s�������ɓ������Ĕ퍐�����̔��f�̊�b�Ƃ����e�����ɂ��ẮA�����Ɍ�F������Ƃ��A���̕]�����������������������Ƃ������Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āA�{���ɂ����ẮA���������k�t�͑�w�݊w���Ƀr�W���A���Z�p�W�ƃR���s���[�^�[�\�t�g�E�G�A�W�̒P�ʂ𗚏C���Ă����Ƃ̎������l���ɓ���Ă��A�{�M�ň���I�A�p���I�Ɂu�Z�p�v�̍ݗ����i�ɊY�����銈�����s������̂Ƃ͔F�߂�ꂸ�A�ݗ����i�̕ύX��K���ƔF�߂�ɑ���鑊���̗��R���Ȃ��Ƃ��Č����̖{���\�����p�������퍐�̔��f�ɂ́A���ꂪ�S�������̊�b���������͎Љ�ʔO�㒘�����Ó������������Ƃ����炩�ł���Ƃ̎���͑����Ȃ�����A�퍐�ɍٗʌ��̈�E���͗��p������Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@�Ȃ��A�����́A�ݗ����i�̕ύX���F�߂��Ȃ���A���@�y�тa�K��ɂ��ۏႳ��Ă��錴���̍ٔ����錠�����N�Q�����Ǝ咣���邪�A�E�咣�͖{���s�������Ƃ͕ʌ̎葱�ł���ދ������葱���Ƃ��邱�Ƃɂ���Đ�����s���v��O��Ƃ����咣�ł���A�{���\�����F�߂��Ȃ����Ƃɂ���āA�����Ɍ����̍ٔ����錠�����N�Q����邱�ƂɂȂ�Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�l�@�ȏ�̎���ł��邩��A�����̖{�i�����ɂ͗��R���Ȃ��B
�@����āA�啶�̂Ƃ��蔻������B
������Q��
�@�i�ٔ����ٔ����@�s���z�T�@�ٔ����@��{���@�ٔ����@�����G���j
�����n��
���P�P�i���j�P�P�W�T�X��
����13�N5��14��
�啶
1�@�����̐���������������p����B
2�@�i�ה�p�͌����̕��S�Ƃ���B
�����y�ї��R
��1�@����
�@1�@�퍐����d�튔����Ћy�є퍐��o����́C�����ɑ��C500���~�y�т���ɑ��镽��13�N3��22������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�@2�@�퍐����d�튔����Ђ������ɑ��C����7�N3��20���t���ł������ق������ł��邱�Ƃ��m�F����B
�@3�@�퍐����d�튔����Ђ́C�����ɑ��C1599��1632�~�y�т���ɑ��镽��13�N3��21������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
��2�@���Ă̊T�v
�@1�@�{���́C�퍐����d�튔����Ёi�ȉ��u�퍐��Ёv�Ƃ����B�j�̏]�ƈ��ł������������C�q�P�r�@�퍐��ЂɋΖ����C�퍐��Ћy�т��̎�����ł������퍐��o����i�ȉ��u�퍐��o�v�Ƃ����B�j���瑼�̏]�ƈ��ɔ䂵�Ďx�����^�̍��ʂ����ꂽ���Ɠ��ɂ�葹�Q�����Ƃ��Ĕ퍐��ɑ����Q���������߁C�q�Q�r�@�퍐��Ђ̔z�]���߂����ۂ������߉��ق��ꂽ���C���ق͖����ł���Ƃ��āC�퍐��Ђɑ��C�]�ƈ��̒n�ʊm�F���тɖ������^���̎x�������߁C�q�R�r�@�\���I�ɁC�퍐��Ђ̂������ق��L���ł���Ƃ��Ă��C�����͔퍐��Ђ�����ق��ꂽ���Ƃɂ��2�N���̋��^�����z�̑��Q�����Ƃ��Ă��̔��������߂���̂ł���B
�@2�@�O��ƂȂ鎖���i�؋����f�������̂̊O�́C�����ҊԂɑ������Ȃ��B�j
�@�@(1)�@�퍐��Ђ́C�d��z�����i�����C�v���X�`�b�N���^���H��ړI�Ƃ��銔����Ђł���C�����s�i���q�ȉ����|�Ғ��r�ɖ{�ЍH����C�R�����k�����S�q�ȉ����|�Ғ��r�ɏ�쌴�H����C�R���s�q�ȉ����|�Ғ��r�ɎR���H���L����B
�@�퍐��o�́C�퍐��Ђ̂��Ə햱������ł���B
�@�@(2)�@�����́C�o���O���f�B�V�����Ђ�L���C���a61�N3���C�_�b�J��w��w�@�}�X�^�[�R�[�X�i�n���w�j�𑲋Ƃ�����C���a62�N1���ɉƑ��ƂƂ��ɗ������C�A�w�̍ݗ����i���擾���āC���N4������2�N�ԓ��{��w�Z�œ��{����w�сC�������N4������2�N�ԃR���s���[�^�[���w�Z�ŃR���s���[�^�[���w�B
�@�@(3)�@����3�N10��3������C�퍐��Ђ́C�������A�J�ł���ݗ����i���擾���邱�Ƃ������Ƃ��āC���������Ԃ̒�߂Ȃ��ٗp����_�����������i�ȉ��u�{���ٗp�_��v�Ƃ����B�j�B
�@�����́C���̂���C�{���ٗp�_��̓��e�y�ь����̐E�����e���ɂ��퍐��Ђ����̂Ƃ���L�ڂ��Č����Ɍ�t�����ٓ��ʒm���y�ѐE����������Y�t���āC�ݗ����i�ύX�\�����s�����i�b9��1�Ȃ���4�j�B
�@�@�@�A�@��{�����@����25���~
�@�����@�L��@���N1��4���@3�`5�p�[�Z���g
�@�@�@�C�@�E�����e
�@�i�A�j�@�|��
�@�o���O���f�B�V���̌o�ώ���y�ыƊE�����̖|��i�x���K���ꂩ����{��ցj
�@�i�C�j�@�C�O�Ɩ�
�@�o���O���f�B�V���ɗA�o�����B�B�̎����Ёi�W�����i�E�G���N�g���b�N�j���Ƃ̘A���Ɩ�
�@�i�E�j�@�f�ՋƖ�
�@�퍐��Б㗝�X�����Ɗ�����Ћy�ь��n�Ƃ̔̔����i�Ɋւ���Ɩ�
�@�i�G�j�@�v���X�`�b�N���^�@�B�y�ѕ��i�@�B�̌��C�R���s���[�^�[����̊e��@�B�̑���̕������Č��n�o���ɔ�����B
�@�@(4)�@�����Ɣ퍐��Ђ́C����3�N11�����猴�����ݗ����i�̕ύX����܂ł����ԂƂ���ŁC�������퍐��Џ�쌴�H��ɂ����Ď����v�Z�̃A���o�C�g�Ƃ��ăv���X�`�b�N���i�i�z�����j�̑g����Ƃɏ]��������e�̌ٗp�_�����������B
�@�@(5)�@�����́C����3�N12��17���C�u�l���m���E���ۋƖ��v�̍ݗ����i���擾�����B
�@�퍐��Ђ́C����4�N1��10���C���^�}�X�^�[�쐬�Ƒ肷�鏑�ʋL�ڂ̂Ƃ���C�����̋��^�̓�������̂Ƃ���Ƃ��i�q�؋����r�j�C���^��\�Ɋ�Â������̎��i������3������ʐEA�U����Ɉʒu�Â��i�q�؋����r�j�C����ɂ�錴���̋��^���z�͊�{�����v�z��22���ŏ�����9227�~�ƂȂ�|�ʒm�����B
�@�@�@�A�@��{�����v�@20��3000�~
�@��{���@6���~
�@���i�蓖�@0�~
�@�Ɩ��蓖�@6���~
�@���ʍ�Ǝ蓖�@3��8000�~
�@�����蓖�@4��5000�~
�@�@�@�C�@���Ύ蓖�@5000�~
�@�@�@�E�@�Ƒ��蓖�@2��2000�~
�@�@�@�G�@��ʎ蓖�@2���~
�@���x���z25���~
�@�@(6)�@�퍐��Ђ̏A�ƋK���ɂ́C���̂Ƃ���̋K�肪�u����Ă���B
�@�@�@��3���@�{�K���͑�2�͑�1�߂ɒ�߂��葱�ɂ��C��Ђ̏]�ƈ��Ƃ��Ă̐g�������������ׂĂ̎҂ɓK�p����B�����C�Վ��و��y�ю��p���̎҂��̑����̂̔@�����킸��Ђ̋Ɩ��ɏ]������҂ɂ��Ă͕ʂ̋K�����鑼�͂��̋K�������p����B
�@�@�@��6���@�]�ƈ��u�]�҂ɑ��Ă͕K�v�ɉ����đI�l�����y�эl�ۂ��s���I�l�̏�3�����Ԃ̎��p���Ԃ������B�i�����j���p���Ԃ͏ɂ��Z�k���͏ȗ�����B
�@�@�@��10���@��Ђ͋Ɩ��̓s����]�C�C�z�u�]���C�ЊO�Ɩ��̔h�����𖽂��鎖������B
�@�@�@��15���@�]�ƈ������L�̊e����1�ɊY������Ƃ���30���O�ɗ\�����邩�C���͕��ϒ�����30�������x�����đ������ق���B�A�����p���Ԓ��y�їՎ��ق��ɏA�i�}�}�j���Ă͂��̎葱����v���Ȃ��B
�@1�@��ނȂ��Ɩ��̓s���ɂ�鎞�B
�@2�@���_���͐g�̂̏�Q�C����V���ɂ��Ɩ��Ɋ������Ȃ��ƔF�߂�ꂽ�ꍇ�B
�@3�@�́C��\���y�ь��C�x���C���ނ̉r�����������̗��R�ɂ��Ɩ����s�ɕs�K���ƔF�߂�ꂽ�ꍇ�B
�@�@�@��16���@�]�ƈ������L�̊e����1�ɊY������Ƃ��͉��ٗ\�����s�킸�܂�30�����̕��ϒ������x���킸�ɑ������ق���B�A���s�������̔F��������čs���B
�@1�Ȃ���13���@��
�@14�@���Ȃ̉c�Ƃ��c�݁C���͐E���Ɋւ��s���s���̋��i���̑��̎��������Ђ��x����������߂Ȃ��ꍇ
�@15�@��
�@16�@�����ȗ��R�Ȃ��C�ٓ��~�i�}�}�j���̖��߂����ۂ����ꍇ�B
�@17�@������2��ȏ�́i�}�}�j�y�щ������̌������Ȃ��ꍇ�B
�@18�@���Ə��ނ���ꍇ�B
�@19�@���̑��O�e���ɏ�����s�ז��͗��R����ꍇ�B
�@�@�@��26���@��Ђ͋Ɩ��̓s����]�ƈ��ɐE��]���C�E��E�K�̕ύX�𖽂��鎖������B
�@�@�@��62���@�]�ƈ��̋��^�͕ʂɒ�߂鋋�^�K��ɂ��B
�@�@(7)�@�퍐��Ђ́C����5�N11��1���C�����ɑ��C����5�N12��1���ȍ~�̋��^�l�ʊ�\����t�������C�����ɂ����Ă͂���܂ł͏��Ј��Ƃ��Ă��������̒n�ʂ�Վ��Ј��Ƃ��C�����ɂ��Ă����ʍ�Ǝ蓖��3��8000�~����1��1000�~�Ɉ����������L�ڂ����C���N12��15���ɂ́C�����ɑ��C�ސE�Ɋւ���v���Ƒ肷�鏑�ʂ���t���đސE�����������i�q�؋����r�j�B
�@�����ŁC��������ϔC�����{�������㗝�l�ł���ێR���ٌ�m�i�ȉ��u�����㗝�l�v�Ƃ����B�j���퍐��Ђƌ��������ʁC����6�N2��21���C�����̋Ζ��Ɋւ��鍇�ӂ��������C���ʂ��쐬���ꂽ�i�b16�B�ȉ��u����6�N���Ӂv�Ƃ����B�j�B
�@�@(8)�@�퍐��Ђ́C����7�N1���C�����ɑ��C�����̏A�Əꏊ���C���N2��21���t���ŏ�쌴�H��Ƃ���|�̎��߂�ʒm���������i�ȉ��u�{���z�]���߁v�Ƃ����B�j�C�����͂�������ۂ����B
�@�@(9)�@�퍐��Ђ́C�����ɑ��C����7�N2��17���ɓ��B�������e�ؖ��X�ւɂ��C���N3��20���t���ʼn��ق���|�̈ӎv�\���������i�ȉ��u�{�����فv�Ƃ����B�j�B
�@3�@���_
�@�@(1)�@�����̔퍐��ɑ��鑹�Q�����������̑���
�@�@(2)�@�{�����ق̌��͋y�і����������������̑���
�@�@(3)�@�{�����ق��L���ł���ꍇ�̑��Q�����������̑���
�@4�@���_�Ɋւ��铖���ґo���̎咣
�@�@(1)�@����
�@�@�@�A�@�퍐��ɑ��鑹�Q��������
�@�i�A�j�@�{���ٗp�_��ɂ����ẮC�����̒�����25���~�ȏ�C�Ζ��ꏊ�͖{�ЍH��Ƃ��C�E�����e�̓R���s���[�^�[�W�Ɩ��Ƃ��鍇�ӂ�����Ă����B�����̍ݗ����i�\�����ނ̋L�ڂ͍ݗ����i�擾�̂��߂̕��ւɂ����Ȃ��������̂ł���B
�@�Ƃ��낪�C�퍐��Ћy�є퍐��Ђɂ����Č����̐l����S�����Ă����퍐���i�}�}�j�́C�{���ٗp�_��ɂ����鍇�ӂɔ����āC�q�P�r�@����4�N1���ȍ~�C�����̋Ζ��ꏊ�y�ыƖ���{�Ђ̃R���s���[�^�[�Ɩ��ł͂Ȃ��C��쌴�H��̃v���X�`�b�N���i�g����ƂƂ��C�q�Q�r�@�����̐g���𐳎Ј��łȂ����Ј��Ƃ��Ĉʒu�t���C���p���Ԍo�ߌ���C���������Ј��Ƃ��ċ��^�v�Z���@�������łȂ����������ɂ�鈵���Ƃ��C�q�R�r����5�N11���Ɍ����ɑ���t�������^�W���ނɂ����āC���Ј��Ƃ��Ă��������̒n�ʂ�����I�ɗՎ��Ј��Ƃ��C�����z�ɂ��Ă����ʍ�Ǝ蓖��3��8000�~����1��1000�~�Ɉ���I�Ɉ���������|�ʒm���C�ݗ����i�X�V�\���̂��߂̌ٓ��ʒm����������x�����@��������������ɕύX���ċL�ڂ��C�q�S�r�@�{���ٗp�_����������쐬�����ٓ��ʒm���ɂ́C���N4����3����5�p�[�Z���g�̖{���̏���������|�������Ă����̂ɒ���������s�킸�C�q�T�r�@�����̏ܗ^�ɂ��Ă��C�{���ٗp�_������̍ہC�ܗ^�̎x�������������C���̏]�ƈ��Ƌ�ʂ�����ʂ̍��ӂ����݂��Ȃ������ɂ�������炸�C����4�N7�����畽��6�N7���܂ł̊e�N7���y��12���̊e�x���ܗ^�ɂ��C���̏]�ƈ��ɂ͏]�ƈ����^�K��4�D5���ɂ���{���ƋƖ��������������̂Ɉ�茎�����悶�����@�Ōv�Z�������z���x�����Ă���i����5�N12�����т�1.55�����x���j�ɂ�������炸�C�����ɑ��Ă͊e2���~�݂̂����x�������C�����͑��̏]�ƈ��Ɠ���̌v�Z���@�ɂ��x�������ׂ��z�Ƃ̍��z83���~�̑��Q���C�q�U�r�@����5�N11��15������ސE�Ɋւ���v���Ƒ肷�鏑�ʂ���t���đގЂ�v�����C�q�V�r�@����ɁC�����̓��ӂȂ��ɕ���6�N1�������瓯�N4�����܂ł̎x�����^�Ɋւ����ʎ蓖������I��3��8000�~����1��1000�~�Ɍ��z���Ďx�����C�����͍��z��10��8000�~�̑��Q�����B
�@�i�C�j�@�����́C�퍐�炪�����ɑ��Ă�����L�̕s���ȏ����ɂ��C�{���x�������ׂ��K���ȋ��^�y�яܗ^����̂��邱�Ƃ��ł����C���̐��K�]�ƈ��ƍ��ʂ��ꂽ���Ƌy�уR���s���[�^�[�Ɩ��ɏ]��������ꂸ�C�P���g���č�Ƃɏ]��������ꂽ���߁C�R���s���[�^�[�W�Ɩ��ւ̓]�E�̋@���D��ꂽ���Ƃɂ�葽��Ȑ��_�I��ɂ��������̂ł���C���̑��Q���Ԏӂ���ɂ�500���~�������ł��邩��C�����́C�퍐��Ђɑ����s���s���͕s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����Ƃ��āC�܂��C�퍐��o�ɑ��Ă͔퍐��ЂƂ̋����s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����Ƃ��Ĕ퍐��ЂƘA�т���500���~�̑��Q�����̎x�������߂�B
�@�i�E�j�@�퍐��Ђ̖{���ٗp�_��ᔽ�ɂ���Č�������������Q�͍��s���s���Q�����������Ƃ��Ă͏��Ŏ������Ԃ�5�N�ł���Ƃ���C�����͕���11�N5��31���ɖ{���i�����N�������͒��f���ꂽ����C�퍐��Ђɑ�����s���s�Ɋ�Â����Q�����������ɂ����Ŏ����͊������Ă��Ȃ��B
�@�@�@�C�@�{�����ق̖����y�щ��ٌ�̒��������i��ʓI���������j
�@�i�A�j�@�{�����ق̖���
�@�@�q�P�r�@�{���z�]���߂́C�����Ɣ퍐��ЊԂ̕���6�N���ӂɈᔽ������̂ł��薳���ł���B����6�N���ӂ́C�����̏A�Əꏊ�𓌋��̖{�ЍH��Ƃ��邱�Ƃ������Ƃ��Č�������ύX�ɉ��������̂ŁC����C�A�Əꏊ��{�ЂƂ��鍇�ӂƒ�������̍��ӂƂ����݂ɑΉ��W�ɂ��������̂ł���C�{���z�]���߂́C�����̏A�Əꏊ�𓌋��̖{�ЍH��Ƃ��镽��6�N���ӂɔ�������̂Ŗ����ł��邩��C�����Ȕz�]���߂����ۂ������Ƃ𗝗R�Ƃ���{�����ق́C���ق̗v�������������ł���B
�@�@�q�Q�r�@�܂��C�{���z�]���߂͌������L����l���m���E���ۋƖ��̍ݗ����i�ȊO�̋Ɩ��ł���v���X��ƂɌ������]����������̂ł���C�����̍ݗ����i�y�і{���ٗp�_��Ɉᔽ������̂Ŗ����ł���B
�@�@�q�R�r�@�܂��C�퍐��́C�����ɑ���O�L�̂Ƃ���̍��ʓI�Ȉ������p�����čs������C����6�N���ӂ̓������猴������쌴�H��ɓ]�����邱�Ƃ�\�肵�Ă����ɂ�������炸�C�����̒��������������邽�߁C�����邵�Č����y�ь����㗝�l���\������6�N���ӂ���������C���������ق������̂ł���C�{�����ق͐M�`���ɔ�������̂Ŗ����ł���B
�@�@�q�S�r�@����ɁC�퍐��Ђ��咣������َ��R�̂����C�{���z�]���ߓ����C�퍐��ЂɌ����ɍs�킹�邱�Ƃ��ł���ݗ����i�ɓK������Ɩ������݂��Ȃ��������Ƃ͂Ȃ��C�������c�Ƌ����J���[�X���C�����̍Ȃ��o�c���Ă������̂ł���C�����͂��̉c�Ƌ��̖��`�l�ƂȂ��Ă������̂ɂ������C�������{�����ٓ����C�A�ƋK���Ɉᔽ���Ď��Ȃ̉c�Ƃ��c�����͂Ȃ��C�����̍�Ɣ\�����ቺ���C�Ɩ����s���s�K���ƂȂ��������͂Ȃ��B
�@�Ȃ��C�퍐��Ђ���U�荞�܂ꂽ�ސE���ɂ��Ă͂����a����ۊǂ��Ă���݂̂ł���B
�@�i�C�j�@���������y�і����ܗ^���������̑���
�@�����́C�{�����ٌ�C�����Ȗ{�����ق������퍐��Ђ̐ӂɋA���ׂ����R�ɂ��A�J���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̂ł��邩��C����������������Ȃ��B
�@�����́C�{�����ٓ����C��{���͘J����1��������9386�~�C�Ƒ��蓖�y�ѐ��Ύ蓖��1����������2��2000�~�y��3000�~�̍��v2��5000�~���x������Ă������̂ł���C�{�����ق̓��̗����ł��镽��7�N3��21�����畽��13�N3��20���܂ł�6�N�Ԃ̖����������v�z�́C1�N������̘J��������252���Ƃ���ƁC��{�����v1419��1632�~�i���z9386�~�~252���~6�N�j���тɉƑ��蓖�y�ѐ��Ύ蓖���v180���~�i���z���z�i�}�}�j2��5000�~�~12�����~6�N�j�̍��v1599��1632�~�ł���B
�@�i�E�j�@����āC�����́C�퍐��Ђɑ��{�����ق̖����m�F�����߂�ƂƂ��ɁC����7�N3��21���ȍ~����13�N3��20���܂ł̖����������v1599��1632�~�y�т���ɑ���ٍϊ��̌�ł��镽��13�N3��21������x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�܁i�}�}�j���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߂�B
�@�@�@�E�@�{�����ق��L���ł���ꍇ�̑��Q���������i�\���I���������j
�@���ɁC�������ݗ����i�ɓK������Ɩ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂɊ�Â��퍐��Ђ������ɑ��Ă����{�����ق��L���ł���Ƃ��Ă��C�����́C�퍐��Ђ������{�����قɂ�菫�����ׂ��肵���������������������̂ł���C���̑��Q�z�́C2�N�ԕ��̊�{�����v473��0544�~�i���z9386�~�~252���~2�N�j���тɉƑ��蓖�y�ѐ��Ύ蓖���v60���~�i���z���z�i�}�}�j2��5000�~�~12�����~2�N�j�̍��v�ł���������z533��0544�~�ł���B
�@����āC�����́C�퍐��Ђɑ��C���@415���Ɋ�Â����Q���������Ƃ���2�N���̒������z533��0544�~�y�т���ɑ��镽��13�N3��22������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߂�B
�@�@(2)�@�퍐��
�@�@�@�A�@�퍐��ɑ��鑹�Q�����������̕s����
�@�i�A�j�@�{���ٗp�_������̍ہC�퍐��Ђ́C�ݗ����i�ύX��̌����ɑ��鋋�^�z���ܗ^���܂ߔN��300���~�ƍ��ӂ������̂ł���C���̋��^�x���z���炷��ƁC�����́C�퍐��Ђ̏]�ƈ��Ɋւ��鋋�^��\�̓������i�ɂ��ẮC3�����̏��Ј��œ��������҂ɊY������B�����āC�퍐��Ђ́C�{���ٗp�_��ɂ����āC�����C�ܗ^�C�ސE���ɂ��č��ӂ����������͂Ȃ����C�����ɑ���ܗ^�̎x���y�я����͂��̓s�x�s���Ă���B
�@�i�C�j�@�����Ɣ퍐��ЊԂō��ӂ��������̐E�����e�́C�ݗ����i�擾�\�����L�ڂ̂Ƃ���ł���C�퍐��Ђ́C���{��w�Z�œ��{����w�сC�R���s���[�^�[�w�Z�����Ƃ��Ă���Ƃ��������ɖ|��Ɩ�����S�������邱�Ƃ�\�肵�Ă������C�����̏A�J�r�U�擾�܂ł̊ԃA���o�C�g�Ƃ��Čٗp���Ζ����J�n�����Ƃ���C�����́C���{��̏K���x���Ⴍ�C�����͓ǂ߂��C�Љ�������������x�ŕ������������ɂ͓ǂ߂Ȃ���ԂŁC�|��Ɩ�����{��̃R���s���[�^�[�Ȃǂ̑�����s�\�ł��邱�Ƃ��������C�܂��C�i�C�̒������퍐��Ђ̖f�ՋƖ��y�ъC�O�Ɩ����ᒲ�ƂȂ�C�����ɒS��������Ɩ����Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ���C�����̏A�J�r�U�擾����C�퍐��Ђ͌����ɃA���o�C�g�Ζ����Ɠ��l�̑g���Ɩ����p�����ĒS����������Ȃ��������̂ł��邪�C���g���Ɩ��͍ݗ����i���i�}�}�j���\�����ދL�ڂ̃v���X�`�b�N���^�@�B�y�ѕ��i�@�B�̌��C�ɖ��ڂɊ֘A����Ɩ��ł���C�܂��C�g����Ƃɏ]��������Ȃ������̂́C�O�L�̂Ƃ��茴�����g�̔\�́E�K�i�̌��@�ɂ����̂Ō����̐ӂɋA���ׂ����R�Ɋ�Â����̂ł��邩��C�퍐��̍��s���s���͕s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����ӔC�͐������Ȃ��B
�@�i�E�j�@�܂��C���ɔ퍐��Ђɍ��s���s���������Ƃ��Ă��C���s���s�ɂ�鑹�Q�����������́C�{���̐������Ɠ��ꐫ��L���C�������Ԃ͖{���̍��̐����ɂ���Č��܂�Ƃ���C�����̋��^���͏ܗ^�������̎������Ԃ͘J����@115���ɂ��2�N�ł��邩��C�e�x��������2�N�̌o�߂ɂ�莞�����ł��Ă���C�퍐��Ђ͏��Ŏ��������p����B����ɁC���ɁC�����ɁC�퍐��̕s�@�s�ׂɂ��Ԏӗ����������F�߂���Ƃ��Ă��C�{�����ق̓��ł��镽��7�N3��20������3�N���o�߂��Ă���C�����̈Ԏӗ��������ɂ��Ă͏��Ŏ������������Ă��邩��C�퍐��͏��Ŏ��������p����B
�@�@�@�C�@�{�����ق̗L����
�@�i�A�j�@�{���z�]���߂́C�Ɩ���̕K�v���Ɋ�Â������I�Ȃ��̂ł���B
�@�o�u���o�ϕ����C�z�����̐����̔��y�уv���X�`�b�N���^�Ƃ̉��i������������ɂ߁C�퍐��Ђ���41�����Z�ŐԎ��ƂȂ������߁C�o�c�������y�ьo��팸�̕K�v���������C�����������̂��߁C����6�N6���ɏ�쌴�H�ƒc�n�ɐV�H������݂��C���H��ŕ��i�̐����C���H�C���^�C�g���̈�э�Ƃ��s�����ƂɌ��肵�C�{�ЍH��̃v���X����ɂ��Ă���쌴�H��ɏW���邱�ƂƂ��C����7�N2���ɐV�H�ꂪ�������邱�Ƃɔ����C�{�ЍH��̃v���X����̏]�ƈ��S���ɑ��C�V�H��ւ̔z�u�]����ʒm�������̂ł���B
�@�퍐��Ђ́C�����ɑ��Ă�����7�N1����{�ɏ�쌴�V�H��ւ̔z�u�]���𖽂����Ƃ���C�����͓�������������������̂́C�����ɂȂ��āC���̏�����P�C�z�u�]�����߂ɏ]��Ȃ��������̂ł���B
�@�����́C�{���z�]���ߋ��ۂ̗��R�Ƃ��ĕ���6�N���ӂ̐������咣���邪�C����6�N���ӂ̎��_�Ō����̋Ζ��ꏊ�𓌋��Ɍ��肷�鍇�ӂ͐������Ă��炸�C�����̔z�]���ߋ��ۂ͔퍐��Ђ̏A�ƋK����16��16������̈ٓ��~���̖��߂����ۂ����ꍇ�̉��َ��R�ɊY��������̂ł���C�{�����ق͗L���ł���B
�@�i�C�j�@�܂��C�����́C����6�N10��12���C�����s�k�����ی���������H�X�c�Ƃ̋����Ď���J���[�X���o�c����悤�ɂȂ�C�J���[�X���J�Ƃ������N10��17���ȍ~�́C�x���C���ނ������Ȃ�C�ȑO�͎���c�Ƃ���]���Ă����ɂ�������炸�C�c�Ƃ�v�����Ă���������ۂ��C�Ζ����Ԓ��ɂ��g�C���ɍs���Ƃ��d�b�������Ă���Ȃǂƌ�����20�������߂�Ȃ�������C���f�ŐE��𗣒E����ȂNjΖ����т��s�ǂƂȂ������C����́C�퍐��Ђ̏A�ƋK����15��3������̋Ɩ����s�ɕs�K���̏ꍇ�y�ѓ���16��14������̎��Ȃ̋Ɩ����c�ꍇ�̊e���َ��R�ɊY������B
�@����ɁC�i�C�̌�މ��ɂ����āC�퍐��Ђ̋ƂƂ���z�����̐����̔��y�уv���X�`�b�N���^�Ƃɂ����鋣����������ɂ߂Ă���C�퍐��Ђ�����5�N��41�����Z����Ԏ����Z�ƂȂ�C�o�c�̍������y�ьo��̍팸�𔗂��邱�ƂƂȂ������߁C��쌴�y�юR���̊e�H��̑S�]�ƈ��ɑ��ސE����������ƂȂ�C�܂��C�������̈�Ƃ��ď�쌴�̋��H��p���ď�쌴�̍H�ƒc�n�ɐi�o���C�v���X����͐V�H��ɏW�C���i���H�C���^�y�ёg���̈�э�Ƃ��s���Čo��̍팸��}�铙�̏ƂȂ��Ă������̂ł���C�{���z�]���ߓ����C�퍐��Ђ̖{�ЍH��ɂ́C�O�L�̂Ƃ���̌����̓��{��̔\�͂��炵�Č������]�����邱�Ƃ̂ł���Ɩ��͂Ȃ��������̂ł���C�{�����ق́C�A�ƋK����15��1������̔퍐��Ђ̂�ނȂ��Ɩ��̓s���ɂ����̂Ƃ��Ă��L���Ȃ��̂ł���B
�@�i�E�j�@�ȏ�̂Ƃ���C�{�����ق́C�퍐��Ђ̏A�ƋK����15��1���y��3�����тɑ�16��14���y��16���Ɋ�Â����̂Ƃ��ėL���ł��邪�C�������C�{�����ٌ�C����7�N4��28���ɔ퍐��Ђ��x�������ސE��6���~���ًc�Ȃ���̂��Ă���C�������g�C�{�����ق��L���ł��邱�Ƃ����F���Ă�����̂ł��邵�C���Ɍ����̖��������y�яܗ^�����������݂����Ƃ��Ă��C���Ŏ������������Ă��邩�炱������p����B
�@�@�@�E�@�{�����ق��L���ł���ꍇ�̑��Q�����������̕s����
�@�O�L�̂Ƃ���퍐��Ђ������{�����ق͗L���ł���C�����̔퍐��Ђɑ�������������͑��݂��Ȃ��B
��3�@���_�ɑ��锻�f
�@1�@�؋��i�q�؋��E�l�ؗ��r�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��Έȉ��̎������F�߂���B
�@�@(1)�@�퍐��Ђ̋��^�̎x���ɂ��ẮC�A�ƋK��62�����āC�]�ƈ����^�K��i�q�؋����r�j�C���^�ב��Ȃ������^�x���ב��i�q�؋����r�j�y�ы��^��\�i�q�؋����r�j����߂��Ă���B
�@���a62�N4��21��������̏]�ƈ����^�K��i�ȉ��u���a62�N���^�K��v�Ƃ����B�j��2�D2���ɂ��C�퍐��Ђ̋��^�x�����́C�{�ЍH��͖������������Ƃ���C�R���H��y�я�쌴�H���10�������Ƃ���Ă���i�q�؋����r�j�B
�@�@(2)�@�����Ɣ퍐��ЊԂŖ{���ٗp�_���������������C�퍐��Ђɂ����ẮC���^��\�̒�߂鎑�i�����̂����C4�����ȉ��̎҂ɂ��ẮC�������������K�p����C5�����ȏ�̎҂ɂ͌��������K�p����Ă����i��16�j�B
�@�Ȃ��C�����́C���̓_�ɂ��C��L����16���Ɠ���|�̍ב����߂鉳17�́C�{����N��ɍ쐬���ꂽ�s�^���ȏ��ʂł���|�咣���邪�C���a62�N���^�K��ɂ��C3�D1���ɂ����āu���������\�v�Ɋւ��ċK���u���Ă��邱�ƁC�܂��C���a54�N4��1���t���������^�K���Ɋւ��ב����߂����^�x���ב��i��32�j�͂��ً̑̍y�ѓ��e����^���ȏ��ʂł���ƔF�߂��Ɓi�}�}�j����C�����ɂ����ẮC4�����ȉ��̈�ʍ�ƐE�͓������Ƃ���|��߂��Ă������Ƃ��F�߂���̂ł����āC����ɏƂ点�C�퍐��Ђɂ����ẮC�]�ƈ��̎��i�����ɉ����āC�قȂ�������͌��������K�p����Ă������̂Ƃ����ׂ��ł���C����16���̋��^�ב��́C����32���̍ב����C4�����ȉ��̏]�ƈ��ɂ��ė��v�ƂȂ�悤����������̋K��ł���ƔF�߂���̂ł����āC����17���Ɋւ��錴���̎咣�ɂ��O�L�F��͍��E����Ȃ��B
�@�퍐��Ђ̋��^��\�́C�{���C���i�蓖���̒����������ꗗ�\�̌`���ŋK�肵�Ă���C�N���Ƃɉ���������Ă���i�q�؋����r�j�B
�@�@(3)�@�퍐��Ђ̏��a62�N���^�K��ɂ͎��̂Ƃ���̋K�肪����Ă���B
�@2�D7���@�����́C���N4��1��������Ƃ���B�����z�́C�]�ƈ��̓K���\�͋Ζ����ыy�т��̊��Ԓ��̉�Ђ̉c�Ɛ��т������Ɋ��Ă��Ă��̓s�x���肷��B�Ȃ��C���ʂ̎���ɂ�肻�̎������ʂ�2�������Ȃ��͈͂ŌJ��グ�Ď��{����ꍇ������B�������C���̏����́C��N�����]�ƈ����i�}�}�j���]�ƈ��C���Ј��C�Վ��Ј��C����]�ƈ��ɂ͓K�p���Ȃ��B�i�㗪�j
�@4�D1���@�ܗ^�́C��Ђ̋Ɛтɂ���āC���N7���y��12����2��x�����邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�̎x���z�́C�e�l�̋Ζ��y�ыƖ����сC�ݐE���ԂƉ�Ђ̎��Ɛ��т��l�����C�x���z�����肷��B�i�㗪�j
�@4�D2���@��
�@4�D3���@�ܗ^�̌v�Z�����́C�Y�������O�̌��Z�ƐтɊ�Â��z���z�����߁C���̓s�x�v�Z����ς��Ďx�����邱�Ƃ��ł���B
�@4�D4���@�ܗ^�́C�Ζ����тɂ��Ζ��l�ۂ��s���C���̔���ɂ��e���̎x���z���߂�B
�@4�D5���@�x���v�Z�̂��߂̏旦�̊�́i�}�}�j�i��N�ҁC�����C���Ј��y�ѓ���̃P�[�X�ŏ������߂��]�ƈ��ɂ͓K�p���Ȃ��j�v�Z�̊�b�z�́C�i��{���~�旦�j�{�Ɩ��蓖�Ƃ���B�܂��C��Ђ̋Ɛтɂ������������Z���邱�Ƃ��ł���B
�@�Ȃ��C�퍐��Ђ̏A�ƋK���i�q�؋����r�j�ɂ́C���Ј��Ɋւ����`�K��͑��݂��Ȃ��B�܂��C�퍐��Ђ̕���11�N12��6���ɕi��J����ē��ɕύX��͂��o���]�ƈ����^�K��i�q�؋����r�j�ł́C�����y�яܗ^�Ɋւ���K��ɂ����ď��Ј��Ɋւ����߂͍폜����Ă���B
�@�@(4)�@�퍐��Ђ́C�퍐��Џ�쌴�H��ɃA���o�C�g�Ƃ��ċΖ����Ă��������̒m�l���猴�����퍐��ЂɏA�E����]���Ă���ƕ����C�����Ɩʐڂ��C�������_�b�J��w�𑲋Ƃ��C�������ē��{��w�Z��R���s���[�^�[���w�Z�Ŋw���Ƃ��Ă������Ƃ���C�����Ɩ{���ٗp�_�����������B
�@�@(5)�@�퍐��Ђ́C����������1200�~�̋��^�����ɂ��ٗp����_����������\��ł���Ƃ��čݗ����i�̕ύX���\�����ނ��쐬�����Ƃ���i��7�j�C�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@��7���1����2���̊���߂�ȗ߂ɂ��ƁC�A�J�̔F�߂���u�l���m���E���ۋƖ��v�̍ݗ����i���擾���邽�߂ɂ͌���25���~�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������������߁C�����̌�����25���~�Ƃ���ٓ��ʒm���i�b9��1�j���쐬���Č����Ɍ�t�������̂ł��������C�퍐��Ђ̒����������炷��ƁC25���~�Ƃ̌����̋��^���z�͐V���Ј��Ƃ��Ă͍��z�Ȃ��̂ł������B
�@�Ȃ��C�����́C����7���́C�b��9����1����ϑ��������̂ł���|�咣���邪�C�b��9����1�y�щ���7���́C����������M�ɂ��L����������̌��{�i�q�؋����r�j�ɂ��C���������������S���ŏ������ď������������̂��R�s�[���č쐬���ꂽ���̂ł��鎖�����F�߂��C�����̎咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@(6)�@�{���ٗp�_�������C�������퍐��Ђ���ʒm�������^�̓���ɂ��C�����́C���^��\�̂����̖{����\��C�������i����3�����̈�ʐE�ɊY�����C�����������ɂ�苋�^�̎x������҂ɓ�����i�q�؋����r�j�B
�@�����́C����3�N11������{�����ق܂ł̊ԁC�퍐��Ђ���ʎ����^�z�ꗗ�\�L�ڂ̊e�x�����Ԃɂ����āC�����������ɂ��C���^���z���L�ڂ̋��z�ɏo�Γ������悶�����z�ɉƑ��蓖�C���Ύ蓖�C���ԊO�蓖�y�ђʋΎ蓖�������Z�����x���z�̎x�������B�܂��C�����́C�퍐��Ђ���C�ʎ��ܗ^���x���z�ꗗ�\�e�L�ڂ̂Ƃ���̏ܗ^���̎x�������B
�@�@(7)�@�����́C�{���ٗp�_������O�͓����s�k��c�[�ɋ��Z���Ă������C�퍐��Ђ́C�������A���o�C�g�Ƃ��Čٗp������C��쌴�H��̗אڒn���݂̔퍐��o���g�p���Ă����Б��2�K�������ɑݗ^���邱�ƂƂ��C1�������̓d�C�E�K�X�E�����E�����̎g�p���̌����z�̖z��8000�~�����邱�ƂƂ����B
�@�@(8)�@�퍐��Ђł́C�������퍐��ЂŋΖ����邤���ɁC�����͊������S���ǂ߂��C�Љ�������������x�ŁC���������\���ɏ����Ȃ����x�̓��{��̏K�n�x�ł���C�����ɖ|�����{��̃R���s���[�^�[�̑���������邱�Ƃ͕s�\�ł��邱�Ƃ����������B���̂��߁C�퍐��ЂƂ��ẮC�������R���s���[�^�[�W�̋Ɩ��ɏA�J�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƍl���C��쌴�H��ɂ�����g����Ƃ����������S�������邱�ƂƂ����B
�@�����C�퍐��Ђ̖f�ՋƖ��́C�i�C�̌�ނ��������C�����ɒS�������邱�Ƃ�\�肵�Ă����o���O���f�B�V���Ƃ̖f�ՋƖ������s����Ȃ����ƂƂȂ����B
�@�@(9)�@����4�N7������C�����ɑ���ܗ^�x���z�����Ȃ����Ɠ��Ɋւ�����ɂ���������ϔC���������㗝�l�́C���N10��27���C�퍐��o�Ƌ��c���s���C���̌㓯�N11��4���t���̏��ʂɂ��C�퍐��Ђɑ��C�����㗝�l���C�{���ٗp�_��ɂ����Ԃ̒�߂̂Ȃ��ٗp�_��Ƃ��邱�ƁC��������{�l�]�ƈ��ƍ��ʂ��邱�ƂȂ�����Ɏ�舵�����Ƌy�т��̌�̎���̕ω��Ɋӂ����̒������ɂ��čċ��c�̏㌈�肵���ʉ����邱�Ƃ�\�����ꂽ�̂ɑ��C�퍐��Ђ͂������������Ă��ꂽ�Ƃ̔F���������C����ɁC�����̘J�������ɂ��ċ��c��i�߂����Ƃ̓��e�̐\������s�����i�q�؋����r�j�B
�@���̂���C�퍐��Ђ́C�����̍ݗ����i�X�V�̂��߂̐\�����ނƂ��āC�ܗ^�̎x���L��ƋL�ڂ��ꂽ���N11��14���t���̌ٓ��ʒm���������Ɍ�t�����i�q�؋����r�j�B
�@�@(10)�@�����́C����5�N�ɁC�Ƒ��̎���ɂ��C��쌴�̎Б���o�ē����ɖ߂肽���Ƃ̊�]���q�ׂ�悤�ɂȂ�C����5�N5���ɁC���Б�瓌���s�k��c�[�ɓ]�������B
�@�@(11)�@�o�u���o�ϕ����̌i�C�̌�މ��ɂ����āC�퍐��Ђ̋ƂƂ���z�����̐����̔��y�уv���X�`�b�N���^�Ƃɂ����鋣���͌������C�퍐��Ђ̌��Z������5�N��41�����Z����Ԏ��ƂȂ�C�o�c�̍������y�ьo��̍팸�𔗂��邱�ƂƂȂ������߁C�퍐��Ђɂ����ẮC��쌴�y�юR���̊e�H��̑S�]�ƈ��ɑ��ސE���������C�]�ƈ��̒��ɂ͂���ɉ����đސE����҂��o��ƂȂ����B
�@�퍐��Ђ́C�����ɑ��Ă�����5�N11��15������ސE�Ɋւ���v���Ƒ肷�鏑�ʂ���t���đސE���������i�q�؋����r�j�C�܂��C����5�N11���Ɍ����ɑ���t�������^�W���ނɂ����āC���Ј��Ƃ��Ă��������̒n�ʂ�Վ��Ј��ƋL�ڂ��C�����z�ɂ��ē��ʍ�Ǝ蓖��3��8000�~����1��1000�~�Ɉ���������|�ʒm���i�q�؋����r�j�C�ݗ����i�X�V�\���̂��߂̌ٓ��ʒm����C�����x�����@��������������ɕύX���ċL�ڂ����i�q�؋����r�j�B
�@�@(12)�@����ɑ��C��������ϔC���������㗝�l�́C�ސE�ɂ͉������Ȃ��Ƃ��Ĕ퍐��Ђƌ����s���C���ɓ��������퍐��o�ɑ��C�퍐��Ђɂ����Č����Ƃ̖{���ٗp�_��͊��Ԃ̒�߂̂Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��m�F���C�ܗ^���̘J�������͑��̏]�ƈ��ƍ��ʂ����ɓ���Ɏ�舵���悤���߂��B
�@����ɑ��C�퍐��Ђ́C����6�N1��20���t���̏��ʂɂ��C�퍐�̕���5�N�̋��^���z25��7000�~�i����5�N4��������j��12�������y�яܗ^2���~��2�̎x�����э��v312��4000�~���Z��̊�b�Ƃ��C�����ŏܗ^�̎x�������{���y�ыƖ��蓖�̍��v�z�ɑ����̏旦���|������@�ɂ��Ƃ���ƁC����5�N12���ɏ旦�Ƃ��č̗p���ꂽ1.55���旦�Ƃ����18��6000�~�ɂȂ�Ƃ��C����2���v37��2000�~��O�L�x�����э��v312��4000�~����T�����C�����12�����ŏ�����22��9333�~�����Ă��ċ��^���z��23���~�Ƃ��C���̓�����C��{�����C�Ƒ��蓖���C�ʋΎ蓖���y�ѐ��Ύ蓖�����Ƃ��鋋�^�ύX�ɂ��Ē�Ă��s�����i�q�؋����r�j�B
�@�Ȃ��C�퍐��Ѝ쐬�̓���ď��ʂɂ́C�NjL�Ƃ��āC�퍐��Ђ̏ܗ^�x���Ώۊ��Ԃ́C7���x�������O�N12��1�����瓖�N5��31���܂ŁC12���x���������N6��1������11��30���܂łł���Ƃ���C�����ɑ��镽��5�N12�������^�͂��łɕ���6�N7���̏ܗ^�x���z�ύX�ɂ�����炸25��7000�~���x���ς݂ł��邩��C���z2��7000�~�͕���6�N7���̏ܗ^�x�����ɐ��Z����Ƃ̋L�ڂ�����Ă����B
�@�܂��C�퍐��o�́C�����ɑ�����ʍ�Ǝ蓖�����z3��8000�~����1��1000�~�Ɉ��������C���^���z��23���~�Ɉ��������邱�Ƃ��Ă������C�����㗝�l�͂���ɑ��C���ʍ�Ǝ蓖��2��1000�~�Ƃ��邱�Ƌy�ѓ��������Ɏx������Ă�����ʎ蓖��2���~�ł��������C���������쌴�H��ɒʋ��Ă��������̌�ʔ���������Ă������Ƃ���C�����̋Ζ��ꏊ��{�ЍH��Ƃ���ʔ������x�����邱�Ƃ����߂��B
�@�@(13)�@�ȏ�̌����o�āC�����C�����㗝�l�y�є퍐��Ђ́C����6�N2��21���C�����̋Ζ��Ɋւ����̂Ƃ���L�ڂ��ꂽ���ӏ��ʂ��쐬���ĕ���6�N���ӂ����������B�����ӏ��ʂ̕��ʂ́C�����㗝�l�����Ă��쐬�������̂ł������B
�@�u1�@�����̘J���_����Ԃ́C������߂Ȃ����ƂƂ���B
�@2�@�퍐��Ђ́C�����̏����E�ܗ^�ɂ��C���̈�ʏ]�ƈ��ƍ��ʂ����C�����Ɏ�舵�����̂Ƃ���B
�@3�@�퍐��Ђ́C����6�N3����������C�����̏A�Əꏊ��{�ЍH��Ƃ��C�����͂���ɏ]���B
�@4�@�O���ɂ���Č����̏A�Əꏊ��{�ЍH��ɕύX�����ȍ~�̌����̋��^
�@�i����6�N�x�����O�j�́C���̂Ƃ���Ƃ���B
�@�{���@6���~
�@���i���@0�~
�@�Ɩ��蓖�@6���~
�@����蓖�@2��1000�~
�@�����蓖�@5��2000�~
�@���Ύ蓖�@5000�~
�@�Ƒ��蓖�@2��2000�~
�@���v22���~
�@��ʔ�@����S�z�x��
�@5�@�퍐��Ђ́C��L�ȊO�̌����̘J�������ɂ��Ă��C��ʏ]�ƈ��Ƌ�ʂ��������Ɉ������̂Ƃ���B
�@6�@�퍐��Ђ́C��L�ȊO�̌����̘J�������ɂ��Ă��C��ʏ]�ƈ��ƍ��ʂ��������Ɉ������̂Ƃ���B�v
�@�Ȃ��C��ʔ����z��1��0350�~�ƂȂ����B
�@�@(14)�@�퍐��Ђ́C����6�N1������4���܂ł̌����ɑ��鋋�^���z��23���~�Ƃ��Ďx���������C���̌�C�퍐��Ђ͕���5�N12�������̋��^���z25��7000�~��23���~�Ƃ̍��z2��7000�~��4������10��8000�~�������ɑ���c�Ǝ蓖������1��4478�~�ɉ��Z�������v12��2478�~���C4�������^�̎x�����ł���5��10���Ɂu�O���������v�Ƃ̎x����ڂɂ�茴���ɑ��Ďx�������i�b2��34�j�B
�@�@(15)�@�����́C����6�N9���C�ȂɃA���o�C�g�̎d�����Ȃ��̂ŃT�����[�}������ٓ̕������J�������Ƃ̑��k��퍐��Ђɂ��Ă������C���̌�C���N10��12���t���ŁC�������c�Ǝ҂Ƃ�����H�X�̉c�Ƌ����擾���i�q�؋����r�j�C���N10��17������C�J���[�X�̉c�Ƃ��J�n���ꂽ�B
�@�@(16)�@�����́C�퍐��Ђ̖{�ЍH��ɂ����ăv���X��Ƃ�S�����Ă������C�퍐��Ђ́C�����ɑ��C���䑕�u�t���v���X�@�B�̑���Z�p���K�������邽�߁C����6�N10��31���C�v���X��Ǝ�C�ҋZ�p�u�K����u�����C�����́C���N11��28���C��C�u�K�I���̌�t���C��C�҂Ƃ��Ă̎��i���i�q�؋����r�j�B
�@�@(17)�@�퍐��Ђ́C�i�C��މ��ɂ����Ă���Ɍo�c�������y�ьo��팸���s�����߁C��쌴�H�ƒc�n�ɐV�H������݂��C���H��ŕ��i�̐����C���H�C���^�C�g���̈�э�Ƃ��s�����Ƃ����肵�C�{�ЍH��̃v���X����ɂ��Ă���쌴�H��ɏW���邱�ƂƂ��C����7�N2���̐V�H��̊����ɔ����C�{�ЍH��̃v���X����̏]�ƈ��S���ɑ��C�V�H��ւ̔z�u�]����ʒm�������C����7�N1��9���C�{���z�]���߂��������́C��������͓��ӂ������̂́C�����C����6�N���ӂ𗝗R�Ƃ��Ă�������ۂ���Ɏ������B
�@2�@�ȏ�F�肵�������y�ёO�L�����̂Ȃ������ɂ�葈�_�ɂ����f����B
�@�@(1)�@�����̔퍐��ɑ��鑹�Q�����������̑���
�@�@�@�A�@�����́C�{���ٗp�_��ɂ����錴���̐E�����e�́C�R���s���[�^�[�W�Ɩ��Ƃ��鍇�ӂ�����Ă����̂ɁC�퍐��Ђ͌����Ƀv���X�`�b�N���i�g����Ɠ��̒P����Ƃ݂̂����������s���s���͕s�@�s�ׂ����݂���Ǝ咣����B
�@����ɑ��C�퍐��Ђ́C�{���ٗp�_������ɍۂ��C�O�L�F��̂Ƃ��茴���̖{���ł���o���O���f�B�V���̉�ЂƂ̎�����g�傷�邱�Ƃ���]���Ă������̂ł���C�������ݗ����i�̕ύX������ɂ́C�������ʖ�Ƃ��Ă̋Ɩ���S�����邱�Ƃ��܂߂Ė{���ٗp�_�����������������F�߂���̂ł���C�{���ٗp�_��̓�������P����Ƃɏ]�������邱�Ƃ�\�肵�Ă����悤�Ȏ���͔F�߂�ꂸ�C���̌㌴�����퍐��ЂŋΖ�����ԂɁC���������{��̔\�͂ɕs�����Ă��邱�Ƃ������������Ƃ���C�����\�肵�Ă����E���̒S�����ł��Ȃ��Ȃ����������F�߂���B
�@�����́C�퍐��Ђ������ɑ������ɃR���s���[�^�[�W�Ɩ�����x���S�������Ă��Ȃ��ɂ������C�����͂����S������\�͂�����|�咣���邪�C�����͖{���i�ׂɂ�����{�l�q��ɂ����Ă��ʖ�l��ʂ��Ēq���s�������Ă���C���炪�ʖ�Ɩ����s�����Ƃ͕s�\�ł���ƔF�߂��C����ɁC�������lj��ł��Ȃ���Ԃł́C�퍐��Ђɂ����ăR���s���[�^�[�W�Ɩ���S�����邱�Ƃ��s�\�ł���Ƃ��킴��Ȃ��B
�@��������ƁC�퍐��Ђ������ɑ��p�����ăv���X�`�b�N���i�g����Ɠ���S�����������Ƃ������Ĕ퍐��Ђ̐ӂɋA���ׂ����s���s�ł���Ƃ��s�@�s�ׂɊY�����鎖����F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�����C�퍐��Ђ́C�{�ЍH��ɂ����Č����Ƀv���X��Ƃ�S���������ۂɂ́C���Ɩ����s�����߂̌��C�������Ď��i���Ƃ邱�Ƃ��ł���悤�}��ȂǁC�����̔\�͂ɉ������\�͊J�����s���Ă������̂ƔF�߂���B
�@�@�@�C�@�����́C�퍐��Ђ������̐g���𐳎Ј��łȂ����Ј��Ƃ��Ĉʒu�t���C���p���Ԍo�ߌ���C���������Ј��Ƃ��ċ��^�v�Z���@�������łȂ����������ɂ�鈵���Ƃ������Ƃ��s���Ȉ����ł���Ƃ��邪�C���̂����C�퍐��Ђɂ�����u���Ј��v�̒n�ʂɂ��Ă͏A�ƋK���㖾�m�ł͂Ȃ����̂́C�퍐��Ђ̋��^�K��ɂ��C�����͓����������̓K�p����Ј��ɊY�����邱�Ƃ͑O�L�F��̂Ƃ���ł��邩��C�퍐��Ђ������ɂ��ē�����������K�p�������Ƃɂ͈�@�̓_�͂Ȃ����̂ƔF�߂��C�܂��C���Ј��Ƃ��Ĉʒu�Â������Ǝ��̂ɂ�茴�������Q���������͔F�߂��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���i�����ɑ��鏸���y�яܗ^�Ɋւ��鈵���ɂ��Ă͌�L�̂Ƃ���ł���B�j�B
�@�@�@�E�@�퍐��Ђ������ɑ��C����5�N11��1���Ɍ�t�������^�l�ʊ�\�ɂ����āC���Ј��Ƃ��Ă��������̒n�ʂ�Վ��Ј��Ƃ��C�����z�ɂ��Ă����ʍ�Ǝ蓖��3��8000�~����1��1000�~�Ɉ���������|�ʒm�����_�ɂ��ẮC�퍐��Ђ́C���̌�C�����㗝�l�ƁC�����̋Ζ������Ɋւ�������s���ƂƂ��ɁC����5�N12�������^�ɂ��ẮC�����ɏ]���ǂ���̋��^���z25��7000�~�̊�ɂ��x�������Ă��鎖�����F�߂��C�����ɏƂ点�C�퍐��Ђ̂������^�l�ʊ�\�̋L�ڂ́C�o�c�������y�ьo��ߌ����}���ƂȂ��Ă���퍐��Ђɂ����āC�ސE�����ƕ����āC�������ɂ��Ă������������߂�\��������s�����ɂƂǂ܂���̂Ƃ����ׂ��ł���C�O�L�̎����W�̉��ŁC���̂悤�Ȑ\������s�������Ǝ��̂����s���s���͕s�@�s�ׂɊY��������̂Ƃ͔F�߂�ꂸ�C�܂��C�ٓ��ʒm���Ɏx�����^������ƋL�ڂ������Ƃɂ��Ă��C����ɂ�茴���ɑ��Q����������������F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B
�@�@�@�G�@�퍐��Ђ̍쐬�����ٓ��ʒm���i�b9��1�j�ɂ́C���N4���ɁC3����5�p�[�Z���g�̖{���̏���������ƋL�ڂ���Ă������C�����ɂ��ẮC���N�����蓖�̑��z�ɂ�鋋�^�z�̑����͂��������̂́C����5�N4���܂Ŗ{���̏���������Ȃ��������Ƃɂ��C�퍐��Ђ̏��a62�N���^�K��2�D7���ɂ��C�]�ƈ��̏����ɂ��ẮC���N4��1��������Ƃ��邪�C�����z�́C�]�ƈ��̓K���\�͋Ζ����ыy�т��̊��Ԓ��̉�Ђ̉c�Ɛ��т������Ɋ��Ă��Ă��̓s�x���肷��Ƃ���Ă���C���K��ɏƂ点�C�ٓ��ʒm���̕����́C����ɂ���̓I�ȏ����܂ł�������e�̂��̂Ƃ͔F�߂�ꂸ�C�퍐��Ђ�����5�N4���܂Ō����ɑ������蓖���z���̏����݂̂������Ȃ��������Ƃɂ����s���s���͕s�@�s�ׂ�����������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@�@�@�I�@�������C�ܗ^�x���Ɋւ����ʓI�Ȏ�舵�������Ƃ���_�ɂ��Ă��C�퍐��Ђ̏��a62�N���^�K��4�D1���C4�D3���Ȃ���4�D5���̓��e���炷��C�X�̏]�ƈ����퍐��Ђɑ����^�K��Ɋ�Â���̓I�ܗ^��������L������̂Ƃ͔F�߂�ꂸ�C�����ɂ��ẮC�O�L�̂Ƃ���C�u�l���m���E���ۋƖ��v�̍ݗ����i���擾���邽�߂ɁC�����\�肵�Ă��������ɂ�鋋�^�̎x���łȂ��C���̏]�ƈ��ɔ䂵�đ��ΓI�ɍ��z�ƂȂ鋋�^���z���x�����邱�ƂƂȂ������ƁC�Ђ��ẮC�x������鋋�^�z�ɉ������Ζ����e���\���ɒB�����邱�Ƃ������ɋ��߂��Ă����Ƃ����ׂ��Ƃ���C�����͓��{��̔\�͂��s�����Ă������߁C�{���ٗp�_��ɂ����ė\�肵�Ă����ʖ�Ɩ��y�уR���s���[�^�[�W�Ɩ�����S���ł��Ȃ����ƂƂȂ��āi�}�}�j���̂ł���C�����̎����W�̉��ɂ����āC�퍐��Ђ������ɑ���ܗ^�Ƃ��Ĉ��z��2���~�̏ܗ^�̎x���������ł���Ɣ��f�������Ƃɂ��C��@���͕s���ȓ_��������̂Ƃ͔F�߂�ꂸ�C���̌�̕���6�N���ӂɊւ�����o�܂ɂ����Ă��C�������͌����㗝�l����ߋ��̏ܗ^�x���z�Ɋւ���V���ȍ��ӂ͋��߂Ȃ��������̂ł���C�������g������5�N12���܂ł̎x���ܗ^�ɂ��ẮC�������Ă������̂ƔF�߂���B
�@�@�@�J�@�퍐��Ђ��C����5�N11��15������C�����ɑ��ސE�������������Ƃ͑O�L�F��̂Ƃ���ł��邪�C���̂���C�퍐��Ђ͌i�C��މ��ŁC�퍐��Ђ̊e�H��̏]�ƈ��ɑ��ސE���������Ă����������F�߂��C���̂悤�ȏɂ����āC�퍐��Ђ������ɑ����ʂőސE���������������������āC�����ɑ���s���ȍ��s���s���͕s�@�s�ׂł���ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@�@�L�@����ɁC�퍐��Ђ��C�����̓��ӂȂ��ɕ���6�N1�������瓯�N4�����܂ł̎x�����^�Ɋւ����ʎ蓖������I��3��8000�~����1��1000�~�Ɍ��z���Ďx�����C�����͍��z��10��8000�~�̑��Q�����Ƃ���_�ɂ��ẮC����6�N���Ӑ��������̔퍐��Ђ̔F���Ƃ��ẮC�����ɑ���ܗ^�x���z����̓I�ɒ�߂鍇�ӂ�����ɂ��ẮC���^���z�̌��z��v����ƍl���C���̌��ʁC�N�Ԃ̑��x���z�����z�ƂȂ�Ȃ��悤��������^���z�Əܗ^�\��z�ƂɊ���t�������z��V���ȋ��^���z�y�яܗ^�\��z�Ƃ���C���Ȃ킿�C���^���z�̌��z�����ܗ^�Ƃ��Ďx������邱�ƂɂȂ�̂Ɠ��l�̕ύX�����ӂ����Ɏ��������̂ł���Ƃ���C�퍐��Ђ́C���Ӑ����O���炱�̂悤�ȍl���Ɋ�Â��C����5�N12�����͂��łɏ]�O�̌��z���^25��7000�~����Ƃ��Ďx����������C����6�N7���̏ܗ^�Ő��Z�����߂�|���ď��i�q�؋����r�j�ɒNjL���Ă���C����ɑ��Č������͌����㗝�l����ًc�̂Ȃ��܂ܕ���6�N���ӂ������������Ƃ���C�퍐��Ђ́C�����̓����̖{�ЍH��Ζ���4������ƂȂ������C���^���z�Əܗ^�Ƃ̊��t�͍��ӂ̂Ƃ���ύX�����ƔF�����āC�����̋��^���z�ƂȂ�23���~�Ƃ̍��z2��7000�~���ܗ^���Ƃ��Č��z���Ďx���������̂ƔF�߂���B�����āC�퍐��Ђ͂��̌㌴�����猸�z���̎x�������߂��đ��₩�Ɏx�����Ă��鎖�����F�߂��邱�Ƌy�ь������g���퍐��Ђ̂�������6�N1��������4�����܂ł̋��^���z�̌��z�x���ɂ��āC��������6�N���ӂ̓��e�Ɉᔽ����Ȃǂً̈c���q�ׂĂ��Ȃ����Ƃ��炵�Ă��C�퍐��Ђ̂������z�x��������6�N���ӂɔ������@�C�s���ȍs�ׂł��鎖����F�߂�ɂ͑���Ȃ��B
�@�@(2)�@�{�����ق̌��͋y�і����������������̑���
�@�@�@�A�@�O�L�O��ƂȂ鎖���L�ڂ̂Ƃ���C�퍐��Ђ̏A�ƋK���ɂ́C�퍐��Ђ��Ɩ��̓s����C�]�ƈ��ɓ]�C�C�z�u�]���C�ЊO�Ɩ��̔h�����𖽂��鎖������ƋK�肳��Ă��邱�Ƃ��炷��C�퍐��Ђ͋Ɩ���̕K�v�ɉ����C���̍ٗʂɂ�茴���̋Ζ��ꏊ�����肷�邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ��ł��邪�C���Y�]�Ζ��߂ɂ��Ɩ���̕K�v����������ꍇ�ł����Ă����̕s���ȓ��@�E�ړI�������Ă��ꂽ���̂ł���Ƃ��Ⴕ���͘J���҂ɒʏ�Îׂ����x����������s���v�킹����̂ł���Ƃ��ȂǁC���i�̎���̑�����ꍇ�́C���Y�]�Ζ��߂͌����̗��p�ɂȂ�Ɖ����ׂ��ł���i�ō��ٔ�����@�쏺�a61�N7��14�������E�����1198��149�ŎQ�Ɓj�B�����ŁC�{���z�]���߂ɂ��퍐��Ђ������ɑ��Ė������z�]�̌��͂ɂ���������B
�@�@�@�C�@�{���z�]���߂͌����ɑ���쌴�H��ł̋Ζ��𖽂�����̂ł��邪�C�{���ٗp�_������̓����C�����̋Ζ��n��퍐��Ж{�ЂɌ��肷�鍇�ӂ����ꂽ�����͂����F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B
�@�����́C����6�N���ӂ́C�����̏A�Əꏊ�𓌋��̖{�ЍH��Ƃ��邱�Ƃ������Ƃ��ċ��^���z�̕ύX�ɉ��������̂ł���C�Ζ��ꏊ�̌���Ƌ��^�̕ύX�͑Ή��W�ɂ��邩��C�{���ٗp�_��ɂ����Č����̏A�Əꏊ��{�ЂɌ��肷����͂�L������̂ł���|�咣����B�������Ȃ���C����6�N���ӂ́C���̖�����C�{���ٗp�_��ɂ��ċΖ��ꏊ������P�v�I�ɖ{�ЍH��Ɍ��肷����e�ł�����̂Ƃ͔F�߂�ꂸ�C�����ɂƂ��āC�����{�Ђ��Ζ��ꏊ�Ƃ��邱�Ƃ��C�x�����^�̕ύX�Ƃ���ΑΉ��W�ɂ������Ƃ��Ă��C����͕���6�N���ӂɍ��ӂ��邩�ǂ����̖��ł����āC����6�N���ӂɂ���Ė{���ٗp�_��ɂ��Č����̋Ζ��ꏊ�𓌋��̖{�ЍH��Ɍ��肷��|�̍��ӂ����ꂽ������F�߂�ɂ͑���Ȃ��B
�@�܂��C�����́C�{���z�]���߂́C�������L����l���m���E���ۋƖ��̍ݗ����i�ȊO�̋Ɩ��ł���v���X��ƂɌ������]����������̂ł���C�����̍ݗ����i�y�і{���ٗp�_��Ɉᔽ������̂Ŗ����ł���|�咣���邪�C�O�L�F��̂Ƃ���C�����͖{�ЍH��ɂ����Č��Ƀv���X��Ƃ�S�����Ă������̂ł���C���̍�ƒS�������������s�����ƂƂ���{���z�]���߂������ƂȂ�Ƃ��錴���̎咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�@�E�@�����āC�퍐��Ђ́C�i�C��ނɑ���Ή���Ƃ��Ă̌o�c�������y�ьo��ߌ�����̈�Ƃ��āC�������܂ޖ{�ЍH��̃v���X��ƒS���ґS���ɑ��C�z�]���߂��Ȃ������̂ł���C�O�L�F�莖���y�ёO��ƂȂ鎖���𑍍�����C�{���z�]���߂ɂ͋Ɩ���̕K�v��������C�������ɒ������s���v�킹����̂ł���悤�Ȏ�����F�߂��Ȃ�����C�{���z�]���߂͗L���Ȃ��̂ł���Ƃ����C��������ۂ��������̍s�ׂ͏A�ƋK��16��16���̉��َ��R�ɊY�����C�{�����ق͉��ٌ��̗��p�ɂ͊Y�������C�L���Ȃ��̂ƔF�߂��邩��C�����Ɣ퍐��ЊԂ̖{���ٗp�_��͖{�����قɂ��I�������Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@(3)�@�{�����ق��L���ł���ꍇ�̑��Q�����������̑���
�@�O�L(2)�F��̂Ƃ���C�퍐��Ђ̂����{�����ق͗L���ł���ƔF�߂��C�O�L�F�莖���̉��ŁC�퍐��Ђ̂����{�����قɂ��C���������̌�퍐��ЂɋΖ����Ă���Γ���ꂽ���^�������z�̎x�������Ȃ������Ƃ��Ă����̎x�������߂鐿��������b�Â��鎖���͔F�߂�ꂸ�C�����̎咣�͎����ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�@3�@�ȏ�̂Ƃ���ł��邩��C�啶�̂Ƃ��蔻������B
�@�i�ٔ����@����a�q�j
�i�ʎ��j�@���^�z�ꗗ�\
�ܗ^���x���z�ꗗ�\
�����n���ٔ���
�����P�Q�N�i�s�E�j��Q�P�P��
�����P�T�N�O�X���P�X��
- �啶
�P�@�퍐���������Ǘ��ǎ�C�R�����������P�Q�N�U���R�O���t���Ō����`�A���a�A���b�y�ѓ��c�ɑ��Ă����e�ދ������ߏ����t��������������������B
�Q�@������̔퍐�@����b�ɑ���e�i������������p������B
�R�@�i�ה�p�͔퍐��̕��S�Ƃ���B
�����y�ї��R
��P�@����
�P�@�啶��P�����|
�Q�@�퍐�@����b�������P�Q�N�U���R�O���t���Ō����`�A���a�A���b�y�ѓ��c�ɑ��Ă����A�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�S�X���P���Ɋ�Â��e�����ً̈c�\���o�͗��R���Ȃ��|�̊e�ٌ�����������������B
��Q�@���Ă̊T�v
�P�@���Ă̗v�|
�@�{���́A��������C�����E�C�X�������a���̍��Ђ�L���A�ݗ����Ԃ�k�߂��Ė{�M�ɂ�����ݗ��𑱂��邱�ƂƂȂ��������`�i�ȉ��u�����v�v�Ƃ����B�j�A���̍Ȃł��錴���a�i�ȉ��u�����ȁv�Ƃ����j�A���̎q�ł��錴���b�i�ȉ��u���������v�Ƃ����B�j�y�ь����c�i�ȉ��u���������v�Ƃ����B�j���A�퍐�@����b�������P�Q�N�U���R�O���Ɍ�����ɑ��Ă����o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�S�X���P���Ɋ�Â��e�����ً̈c�\���o�͗��R���Ȃ��|�̊e�ٌ��i�ȉ��u�{���e�ٌ��v�Ƃ����B�j�y�є퍐��C�R�����������ɍs�����e�ދ������ߏ����t�����i�ȉ��u�{���e�ޗߔ��t�����v�Ƃ����B�j�͂��������@�ł���Ƃ��Ă��̎���������߂���̂ł���B
�Q�@���f�̑O��ƂȂ鎖���i�F�荪�����f�L���Ȃ������͓����ҊԂɑ������Ȃ��B�j
(1)�@������
�@�����v�́A�P�X�U�R�N�W���Q�R�����܂�̃C�����E�C�X�������a���i�ȉ��A�P�Ɂu�C�����v�Ƃ����B�j���Ђ�L����j���ł���A�����ȂƂ����B�j�́A�P�X�U�U�N�P�Q���Q�Q�����܂�̓������Ђ�L���鏗���ł����āA���l�́A�v�w�ł���B���������i�P�X�W�W�N�T���V�����܂�j�y�ь��������i�P�X�X�U�N�X���X�����܂�j�́A������������v�ƌ����Ȃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�����ł���A�������Ђ�L����҂ł���B
(2)�@������̓����y�эݗ��̌o��
�A�@�����v�́A�����Q�N�T���Q�P���A�C�����̃e�w��������C�����q��@�Ő��c��`�ɓ������A�������ǐ��c�x�Ǔ����R�����ɑ��A�O���l�����L�^�̓n�q�ړI�̗��Ɂu�a�����������������v���ƁA���{�؍ݗ\����Ԃ̗��Ɂu�X�c�`�x�r�v�ƋL�ڂ��ď㗤�\�����s���A�������R��������o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i�������N�@����V�X���ɂ������O�̂��́B�ȉ��u���@�v�Ƃ����B�j�S���P���S���ɒ�߂�ݗ����i�y�эݗ����ԂX�O���̋����A�{�M�ɏ㗤�����B
�@�����v�́A�ݗ����i�̕ύX���͍ݗ����Ԃ̍X�V�̋��\�����s�����ƂȂ��A�ݗ������ł��镽���Q�N�W���P�X�����Ė{�M�ɕs�@�c��������Ɏ������B
�C�@�����Ȃ́A�����R�N�S���Q�U���A���������ƂƂ��ɃV���K�|�[������V���K�|�[���q��@�Ő��c��`�ɓ������A�������ǐ��c�x�ǐR�����ɑ��A�O���l�����L�^�̓n�q�ړI�̗��Ɂu�s�n�t�q�h�r�s�v�A���{�؍ݗ\����Ԃ̗��Ɂu�n�m�d�@�v�d�d�j�v�ƋL�ڂ��ď㗤�\�����s���A���ꂼ�ꓯ�����R��������o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j�ʕ\�P�ɋK�肷��ݗ����i�u�Z���؍݁v�y�эݗ����ԂX�O���̋����A�{�M�ɏ㗤�����B
�@�����ȋy�ь��������́A�ݗ����i�̕ύX���͍ݗ����Ԃ̍X�V�̋��\�����s�����ƂȂ��A�ݗ������ł��镽���R�N�V���Q�T�����Ė{�M�ɕs�@�c������Ɏ������B
�E�@�����ȋy�ь��������́A�����U�N�P���T���ɁA��ʌ��{���s���ɑ��A���Z�n����ʌ��{���s�����|���|���Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â��V�K�o�^�\�����s���A���N�P���Q�S���A�O���l�o�^�ؖ����̌�t�����B
�@�����v�́A�����V�N�S���P�P���ɍ�ʌ��{���s���ɑ��A���Z�n����ʌ��{���s�����|���|���Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â��V�K�o�^�\�����s���A���N�T���P�V���O���l�o�^�ؖ����̌�t�����B
�G�@���������́A�����W�N�X���X���A�Q�n�������s���݂̍��ݎY�w�l�ȏ����Ȉ�@�ɂ����āA�����v�y�ь����Ȃ̊Ԃɏo���������A�ݗ����i�̎擾�̐\�����s�����ƂȂ��o������U�O�����o�߂��������W�N�P�P���W�����Ė{�M�ɍݗ����A�s�@�c������Ɏ������B
�I�@���������́A�����X�N�T���Q�Q���ɌQ�n�������s���ɑ��A���Z�n���Q�n�������s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â��V�K�o�^�\�����s���A�����A�O���l�o�^�ؖ����̌�t�����B
�J�@�����Ȃ́A�����W�N�P�O���R�P���A�Q�n�������s���ɑ��A���Z�n���s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â����Z�n�ύX�o�^�������i���Q�O�j�B
�L�@�����v�́A�����P�P�N�P���P�R���y�ѓ��N�P�P���P�V���ɁA��ʌ��{���s���y�ьQ�n�������s���ɑ��A���Z�n�����ꂼ���ʌ��{���s�����|���|���y�ьQ�n�������s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â����Z�n�ύX�o�^�������B
�@���������́A�����P�P�N�P�P���Q�T���A�Q�n�������s���ɑ��A���Z�n���s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â����Z�n�ύX�o�^�������i���R�W�j�B
(3)�@������̑ދ������葱�̌o��
�A�@������́A�����P�P�N�P�Q���Q�V���A�������Ǒ�Q���ɂɏo�����A�s�@�c�������ɂ��Đ\�������B
�C�@�������Ǔ����x�����́A�����P�Q�N�P���Q�V�������v�y�ь����Ȃɂ��āA���N�Q���P�T�������Ȃɂ��Ĉᔽ���������{�������ʁA�����炪�@�Q�S���S�����i�s�@�c���j�ɊY������Ƌ^���ɑ���鑊���̗��R������Ƃ��āA���N�Q���Q�Q���A������ɂ��A�퍐��C�R����������e�ߏ��̔��t���A�����Q�S���A���ߏ������s���āA������𓌋����ǎ��e��Ɏ��e���A�����v�y�эȂ�@�Q�S���S�����Y���e�^�҂Ƃ��ē������Ǔ����R�����Ɉ����n�����B�퍐��C�R�����́A�����A������ɑ��A�����Ɋ�Â������Ƃ��������B
�E�@�������Ǔ����R�����́A�����P�Q�N�Q���Q�S���y�ѓ��N�R���V�������v�ɂ��Ĉᔽ�R�������A���̌��ʁA���N�R���V���A�����v���@�Q�S���S�����ɊY������|�̔F������A�����v�ɂ����ʒm�����Ƃ���A�����v�́A�����A�������Ǔ��ʐR�����ɂ������R���𐿋������B
�G�@�������Ǔ����R�����́A�����P�Q�N�Q���Q�S���y�ѓ��N�R���P�T���A�����ȁA���������y�ь��������ɂ��Ĉᔽ�R�������A���̌��ʁA���N�R���P�T���A�O�L�e�������@�Q�S���S�����ɊY������|�̔F������A�O�L�e�����ɂ����ʒm�����Ƃ���A�O�L�e�����͓����A�������Ǔ��ʐR�����ɂ������R���𐿋������B
�I�@�������Ǔ��ʐR�����́A�����P�Q�N�S���Q�S���A�����v�ɂ��āA�����R�������A���̌��ʁA�����A�����R�����̑O�L�F��͌�肪�Ȃ��|���肵�A�����v�ɂ����ʒm�����Ƃ���A�����v�́A�����A�퍐�@����b�ɑ��A�ًc�̐\�o�������B�퍐�@����b�́A�����P�Q�N�U���Q�U���A�����v����ً̈c�̐\�o�ɂ��ẮA���R���Ȃ��|�ٌ����A���ٌ��̒ʒm�����퍐��C�R�����́A���N�U���R�O���A�����v�ɓ��ٌ������m����ƂƂ��ɁA�ދ������ߏ��t�����B
�J�@�������Ǔ��ʐR�����́A�����P�Q�N�S���Q�U���A�����ȁA���������y�ь��������ɂ��Č����R�������A���̌��ʁA�����A�����R�����̑O�L�F��͌�肪�Ȃ��|���肵�A��������ɂ����ʒm�����Ƃ���A��������́A�����A�퍐�@����b�ɑ��A�ًc�̐\�o�������B�퍐�@����b�́A�����P�Q�N�U���Q�U���A�����ȁA���������y�ь�����������̊e�ًc�̐\�o�ɂ��Ă͗��R���Ȃ��|�ٌ����A���ٌ��̒ʒm�����퍐��C�R�����́A���N�U���R�O���A��������ɓ��ٌ������m����ƂƂ��ɁA���ꂼ��ɑ��ދ������ߏ��t�����B
��R�@�����҂̎咣
�P�@�퍐
(1)�@�{���e�ٌ��̓K�@���ɂ���
�A�@������̑ދ��������R
�@�����v�A�ȋy�ь����������A���ꂼ��̍ݗ����Ԃ��ĕs�@�c���������Ƌy�ь����������A�{�M�ŏo���������̂́A�ݗ����i�̎擾�̐\�����s�����ƂȂ��A�o������U�O�����o�߂��������ĕs�@�c�����Ă������Ƃ͖��炩�ł���A�����炪�ދ��������R�ɊY�����邱�Ƃ�F�߂����ʐR�����̔���ɉ�����͂Ȃ��B
�C�@�ݗ����ʋ��ɌW��@����b�̔��f�̓K�@��
(�A)�@�@����b�̍L�͂ȍٗʌ�
�@�@����b�́A�ًc�̐\�o�ɑ���ٌ��ɓ������āA�ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��ƔF�߂�ꍇ�ł��A���ʂɍݗ��������ׂ��������ƔF�߂�Ƃ��́A���̎҂̍ݗ�����ʂɋ����邱�Ƃ��ł���Ƃ���i�@�T�O���P���R���j�A���̂悤�ȍݗ����ʋ��́A�ދ��������R�ɊY�����邱�Ƃ����炩�ŁA���R�ɖ{�M����̑ދ������������ׂ��҂ɑ��A���ʂɍݗ���F�߂鏈���ł����āA���̐����́A���b�I�Ȃ��̂ł���Ƃ����ׂ��ł���B�����āA�ݗ����ʋ��̔��f������ɓ������ẮA���Y�O���l�̌l�I����݂̂Ȃ炸�A���̎��X�̍����̐����E�o�ρE�Љ�̏�����A�O�𐭍�A���Y�O���l�̖{���Ƃ̊O���W���̏��ʂ̎���𑍍��I�ɍl�����ׂ����̂ł��邱�Ƃ���A�ݗ����ʋ��ɌW��@����b�̍ٗʂ͈̔͂͋ɂ߂čL�͂Ȃ��̂ł����āA���Y�ٗʌ��̍s�g����@�ƂȂ�̂́A�@����b�����̕t�^���ꂽ�����̎�|�ɖ��炩�ɔw���čٗʌ����s�g�������̂ƔF�ߓ���悤�ȓ��ʂ̎������ꍇ���A�ɂ߂ė�O�I�ȏꍇ�Ɍ�����B
(�C)�@�{���e�ٌ��ɍٗʌ��̈�E���͗��p���Ȃ�����
�@�����v�A�����ȋy�ь��������́A�C�����ŏo���E���炵�A��������܂ʼn䂪���Ƃ͉���̂������̂Ȃ��������̂ł��������A�n�q�ړI���U���Ė{�M�ɏ㗤���A�����v�y�ь����Ȃ́A���̌�Ԃ��Ȃ��s�@�A�J���J�n���Ă���Ƃ���A�s�@�c���Ɏ������o�܂͋ɂ߂Čv��I�ł����āA�s�@�A�J���s�������Ԃ������A�o�����Ǘ��s����ʼn߂�����̂�����B�����v�y�ь����Ȃ̐e�Z��́A�C�����{���ɍݏZ���A�{���e�ٌ������ɂ́A�s�@�A�J�œ������K�Ŗ{���Ɏ���܂ōw�����Ă���̂ł����āA�����炪�C�����ɋA�������Ƃ��Ă��{���ł̐����Ɏx��͂Ȃ����̂Ƃ����ق��Ȃ��B�܂��A�����q��́A�����Y���ɕx�ޔN��ɂ���A���ɓ����͌������K���̖ʂő����̍���������邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��i���n�ł̐������o�����邱�Ƃ��������K����g�ɂ���őP�̕��@�ł���A���e�Ƃ̖{�M����̑ދ�����ނȂ����̂ł���ȏ�A���̔N��ɂ��݂�ƁA�ꍏ�������A�����]�܂��Ƃ����ׂ��ł���B�j�A���e�ƂƂ��ɋA������̂��q�̕������͍őP�̗��v�ɓK���Ƃ���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A���̐e���̍ݏZ����C�����ł̐����Ɋ���e���ނ��Ƃ͏\���ɉ\�ł���ƌ����܂��̂ł����āA������ɂ��āA�{�M�ւ̍ݗ���F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ʂȎ�����݂���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@�m���ɁA������́A�{�M�ɕs�@�Ɏc������ԂɈ��̈��肵��������Ԃ��`���������̂Ƃ����Ȃ����Ȃ����A�ō��ُ��a�T�S�N�P�O���Q�R����R���@�씻���́A��P�O�N�O�ɕs�@���������O���l�j���A��P�R�N�O�ɕs�@�������������l�����y�і{�M�ɂ����ďo�����������Ԃ̎q��Q���ɑ��A�@����b���ݗ����ʋ���^���Ȃ��������Ăɂ��āu�{�M�ɕs�@�������A���̂܂܍ݗ����p������O���l�́A�o�����Ǘ��߂X���R���̋K��ɂ�茈�肳�ꂽ�ݗ����i�������čݗ�������̂ł͂Ȃ��̂ŁA���̍ݗ��̌p���͈�@��Ԃ̌p���ɂق��Ȃ炸�A���ꂪ�����ԕ����Ɍp�����ꂽ����Ƃ����Ē����ɖ@�I�ی����؍����̂��̂ł͂Ȃ��v�Ɣ������Ă���A����́A�{���ɂ����Ă����Ă͂܂���̂Ƃ�����B���������s�@�c���́A�����̑ΏۂƂȂ��@�s�ׂł���A�����v�y�ь����Ȃ��{�M�ɂ����Ē����ԕs�@�A�J�������s�����Ƃ��������́A��@�s�ׂ������Ԃɋy���Ƃ��Ӗ�������̂ł��邩��A�퍐�@����b��������̍ݗ����ʋ��̉ۂf�����ŁA���Y������L���Ȏ���Ɖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͂Ȃ��̂ł���A�ނ���A�����ɂ킽��s�@�c��������s�@�A�J���������ݗ����ʋ��̔��f�ɂ����ď��ɓI�v�f�Ƃ��ĕ]�������ׂ����̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ȏ�������l������A�@����b���{���e�ٌ��ɓ������ĕt�^���ꂽ�����̎�|�ɖ��炩�ɔw���čٗʌ����s�g�������̂ƔF�ߓ���悤�ȓ��ʂ̎�����݂���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
(�E)�@�����̎咣�ɑ��锽�_
���@������̏o�g���ł���C�����̋���╟�����ɌW����݂Ă��A�����̐������i�̖�肪����ƔF�߂�ꂸ�A�����q��𑗊҂��邱�Ƃ��ݗ����ʋ��̌�����@����b�ɔF�߂���|�ɔ������l���I�Ȃ��̂ł���Ƃ���������͉��瑶���Ȃ����肩�A�C�����Ɏ�����w�����������܂ł́A�C�����ɋA������ӎv��L���Ă������A�������w�Z�Q�N���ł����������������A����������Ȃ��������߁A���̂܂ܕs�@�c�����p������Ɏ������|���q���Ă���A�A����O��Ƃ��������v�����Ă����Ƃ����ׂ��ł���B
���@���ۘA���́A�����Q�N�P�Q���P�W���u���ׂĂ̈ڏZ�J���҂Ƃ��̉Ƒ��\�����̌����ی�Ɋւ��鍑�ۏ��v���̑����A���̂R�O���́A�ڏZ�J���҂̎q�������w�Z�ŋ�����錠����L���邱�Ƃ��߁A���̂悤�Ȍ����́A�ڏZ�J���҂ł��闼�e���͂��̑؍݂��K�@�łȂ����Ƃ𗝗R�ɋ��ۖ��͐�������Ȃ��|�̋K��������Ă��邪�A�����ɂ��Ă͎��ꍑ���̌��O�������A�̑�����P�O�N�ȏ�o�߂��������P�S�N���ɂ����Ă��A������y�����Q�O�J���ɒB���Ă��Ȃ����ߌ��͂̔����ɂ������Ă��炸�A�������A���̂悤�ȏ��ł����A��L�R�O���̂悤�ȋK��͕s�@�ɑ؍݂��邱�̍ݗ��̓K�@���Ɋւ��錠�����܂ނ��̂Ɖ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���̂ł��邩��i�����R�T���j�A���ۓI�ɂ��s�@�A�J�҂̎q����������̍��ɂ����ċ�����闘�v�Ă���Ƃ��Ă��A������̍�������𗝗R�ɓ��Y�s�@�A�J�ҋy�т��̎q���̍ݗ���K�@�����ׂ��ł���ȂǂƂ������ӂ�����Ă�������݂��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
���@�C�X�����Љ�ɂ����Ă��A�j���̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A�����̐���؏��i��������j���C�X�������k�̋`���Ƃ��錩���͂��������ł���A��������͖k���A�t���J�A���A�t���J�A�A���r�A������}���[�V�A�̈ꕔ�ȂǂɌ��肳�ꂽ�K���ł���Ƃ���A�C�����̍�����Ɋւ���p���ږ��ǂ̕��́A�u�����̋s�҂ɂ��Ēm��ꂽ�ތ^�͂Ȃ��v�Ƃ��A��������ɂ��ĉ���G��Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�C�����ɂ����ď������炪�@�I���͎Љ�I�ɋ`���Ƃ���Ă��������Ƃ͔F�ߓ�B
���@������Ɠ��l�A�o���\���������w���������q��L����s�@�c���O���l�̉Ƒ��ɂ��čݗ����ʋ������ꂽ��͂��邪�A�����A������ƂƂ��ɁA�����P�P�N�P�Q���Q�V���ɓ������ǂɏo���\�������s�@�c�����̃C�����l�T�Ƒ��ɂ��Ă͌�������܂ނS�Ƒ����ݗ����ʋ����邱�ƂȂ��ދ������ߏ����t�������Ă���B
�@���������A�ݗ����ʋ��͏��ʂ̎���𑍍��I�ɍl��������ŌʓI�Ɍ��肳���ׂ����b�I�[�u�ł����āA���̋��ۂ��S������s�����Ȃ�����`�I�A�Œ�I��Ȃ���̂͑��݂��Ȃ��̂ł����āA�{���e�ٌ�����@�ɂȂ�Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A���ɁA�{���e�ٌ��������ɔ�������̂ł���Ƃ��Ă��A�O�L(�A)�̍ٗʂ̖{���������ɂ���ĕύX�������̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ��ē��s���̖�肪������ɂ����Ȃ��B
���@�s�@�c���҂𒆐S�Ƃ���s�@�A�J�҂��䂪���ɑ������݂���͎̂����ł��邪�A����͑����̕s�@�A�J�҂��V���ɔ����������Ă��錋�ʂł����āA�s�@�A�J�������䂪���̎Љ�ɗe�F����Ă��邩��ł��Ȃ���A���i�Ȏ���肪�s���Ă��Ȃ�����ł��Ȃ��B������̋��Z�n�ł���Q�n���ł��s�@�A�J�������e�F����Ă���ȂǂƂ��������͂Ȃ��A�����P�Q�N�̌Q�n���c��ɂ����Ắu��ʂ̕s�@�؍ݎ҂����݂���Ƃ������Ƃ́A�����O���l�ɂ��ƍ߂̉����ƂȂ��Ă���B�v�u�����Ǘ��ǂƂ̍��������Ƃ������Ƃɏd�_��u���āv����Ƃ��āA�����P�P�N�ɂ͂S�P�l���P�Q�N�ɂ͂P�P�����܂łɂR�U�U�l��E�����ĕs�@�؍ݎ҂̒蒅���̑j�~�ƌ�����}���Ă��邱�Ƃ�����Ă���A�����P�Q�N�ɑS���Ōx�@�Ɍ������ꂽ�@�ᔽ�҂͂T�W�U�Q�l�ł���B�Q�n���ɂ����Ė@�ᔽ�҂̓E�����ϋɓI�ɍs���Ă��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�܂��A�����P�Q�N�ɑދ������葱���̂����s�@�A�J�҂S���S�P�X�O�l���A�Q�n���ʼnғ����Ă������̂͂P�V�U�X�l�A�����P�R�N�ɑދ������葱���̂����s�@�A�J�҂R���R�T�O�W�l���A�Q�n���ʼnғ����Ă����҂͂P�S�S�W�l�ƂȂ��Ă���A��������S���s���{�����W�ʂƂȂ��Ă���B����ɁA�����P�S�N�P�P���ɑS���̒n�������Ǘ��������s�����@�ᔽ�O���l�̈�ēE���ɂ����ēE�����ꂽ�@�ᔽ�҂W�T�T�����A�Q�n���œE�����ꂽ�҂͂T�W���ł���A����́A���A�����A��ʂɂ��đS���s���{�����S�ʂƂ����������ʂƂȂ��Ă���̂ł���A������ƁE���Ƃ𒆐S�Ɂu�P���J���ҁv��]�ސ��������A���{���{�͌��i�Ȍ`�ŊO���l�J���҂ɂ��s�@�A�J�̎������s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
(�G)�@�ȏ�̂Ƃ���A�@����b���{���e�ٌ��ɓ������ĕt�^���ꂽ�����̎�|�ɖ��炩�ɔw���čٗʌ����s�g�������̂ƔF�߂���悤�ȓ��ʂ̎�����݂���Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�{���e�ٌ��ɉ���̈�@���͂Ȃ��B
(2)�@�{���e�ޗߔ��t�����̓K�@���ɂ���
�@�ދ������葱�ɂ����āA�@����b����u�ًc�̐\�o�͗��R���Ȃ��v�Ƃٌ̍��������|�̒ʒm�����ꍇ�A��C�R�����́A�ދ������ߏ��t����ɂ��ٗʂ̗]�n�͂Ȃ�����A�{���e�ٌ�����@�ł���Ƃ����Ȃ��ȏ�A�{���e�ޗߔ��t�������K�@�ł���B
�@�ݗ����ʋ��̔��f������ɓ������ẮA���Y�O���l�̌l�I����݂̂Ȃ炸�A���̎��X�̍����̐����E�o�ρE�Љ�̏�����A�O�𐭍�A���Y�O���l�̖{���Ƃ̊O���W���̏��ʂ̎���𑍍��I�ɍl�����ׂ����̂ł��邱�Ƃ͑O�L�̂Ƃ���ł��邩��A�@����b����u�ًc�̐\�o�͗��R���Ȃ��v�Ƃٌ̍��������|�̒ʒm������C�R�����́A���@���킷�邱�ƂȂ��A���₩�ɑދ������ߏ����t���������Ȃ���Ȃ炸�A�����ł��邩�炱���A�@�S�X���T�����u���݂₩�ɓ��Y�e�^�҂ɑ��v�E�E�E�u�ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����̂ł����āA�ދ������ߏ��̔��t�����ɂ��Ď�C�R�����ɍٗʌ�������Ƃ͂����Ȃ��B
�@�@�́A�@����b���ݗ����ʋ��̌������s�g���邩�ۂ��̔��f���s���ߒ��ɂ����Ă̂݁A�ދ��������R�ɊY������O���l�̍ݗ����O�I�ɔF�߂�ٗʂ�F�߂Ă���A�ًc�̐\�o�����@����b���A�ݗ����ʋ��Ɋւ��錠���������A�ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��Ƃٌ̍����s�����ꍇ�ɂ́A����͉䂪�������ƂƂ��ē��Y�O���l��ދ��������ׂ��Ƃ���ŏI�I�Ȉӎv������������Ƃ��Ӗ�������̂ł����āA�㋉�s���@�ւł���@����b�̈ӎv�����b�̎w���ē��鉺���s���@�ւł����C�R�������A���̓Ǝ��̔��f�Ɋ�Â��ĕ����A���邢�͂��̓K�p�������l���ł���Ƃ��邱�Ƃ͍s���g�D�@��̊ϓ_���炵�čl����ꂸ�A�@�����̂悤�ȗ��@������̗p���Ă���Ƃ͍l�����Ȃ��B�܂��A�@�́A�ݗ����i�̂Ȃ��O���l���{�M�ɓK�@�ɍݗ�����
���Ƃ́A�����Œ�߂�ꂽ��O�������ė\�肵�Ă��Ȃ��Ƃ���A��C�R�������ٗʂɂ��ދ������ߏ��t���Ȃ��ꍇ�ɁA���Y�O���l�����������{�M�ɍݗ����邽�߂̖@�I�n�ʂ��߂�葱�K��͑��݂��Ȃ��̂ł����āA�@�́A��C�R�����̍ٗʂɂ��ދ������ߏ��t���Ȃ��Ƃ������Ԃ�z�肵�Ă��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@���������āA��C�R�����ɑދ������ߏ��t���邩�ۂ��ɌW��ٗʌ���������|�̌�����̎咣�ɂ͗��R���Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�Q�@������
(1)�@�{���e�ٌ��̓K�@���ɂ��āi��ʓI�咣�j
�A�@�ٌ����̕s�쐬
�@�@�{�s�K���S�R���́A�u�@��S�X���R���ɋK�肷��@����b�ٌ̍��́A�ʋL��U�P���l���ɂ��ٌ����ɂ���čs�����̂Ƃ���B�v�ƒ�߂Ă���B�����́A�P�Ɍ����ōs��ꂽ�ٌ��̑��݂��m�F�E�L�^���邱�Ƃ����߂Ă���̂ł͂Ȃ��A�ٌ����ٌ����Ƃ������ʂɂ���Ă���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁA�܂�A�ٌ������ʂɂ��l���s�ׂł��邱�Ƃ��߂Ă���̂ł���B
�@�Ƃ���ƁA�ٌ������쐬����Ă��Ȃ��{���e�ٌ��ɂ͋ɂ߂ďd�傩�����Ȏ葱������r������A�{���e�ٌ��̎�����͖Ƃ�Ȃ��B
�C�@�{���e�ٌ��̍ٗʈᔽ
(�A)�@�@����b�̍ٗʌ��͈̔͂ɂ���
�@���{�����@�́A����������̍ō��@�ւƒ�߂Ă��邱�Ƃ���A���Ƃ̍ٗʂ́A���`�I�ɂ͍���ɑ�������̂Ƃ��ė��@�ٗʂɌ���邱�ƂƂȂ�B���̗��@�ٗʂ̌��ʂƂ��āA����̏ꍇ�ɂ͊O���l�ɓ����E�ݗ��������ׂ��s�����ɋ`���Â������邱�Ƃ�����A�s�����ɍٗʂ�^���A�����e�ɐ����t�����Ƃ�����B�����āA���@�̐��_��u�@���ɂ��s���̌����v���炷��A�s�����ɑS���̎��R�ٗʂ��t�^����邱�ƂȂǂ��蓾�Ȃ��̂ł����āA���̍ٗʌ����^����ꂽ�Ƃ��Ă��A���̍����ƂȂ�@���̖ړI�y�ю�|���ɂ�����J���ٗʂƂȂ�̂ł���B���̓_�A�@�́A�u�o�����̌����ȊǗ��v��ړI�Ƃ��Ă���i�P���j�A�u�o�����̌����ȊǗ��v�Ƃ́A�����̎�����J���s��̈���Ȃnj��v���тɍ��ۓI�Ȍ������A�Ó����̎����y�ь��@�A���A���ۊ��K�A�𗝓��ɂ��F�߂���O���l�̐����ȗ��v�̕ی���͂��邽�߂̊Ǘ����Ӗ�����B�@�T�O���P���̎�|���A���̌��v�ړI�ƊO���l�̐����Ȍ����E���v�̒�����}�邱�Ƃɂ���A�@����b�̍ٗʌ������̎�|�͈͓̔��ŔF�߂���ɂ����Ȃ��B
�@�퍐�̎咣�́A���̓_���ʼn߂��A���Ƃ̍ٗʌ��Ɩ@����b�̍ٗʌ��Ƃ������������̂Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�܂��A��L�̂Ƃ���A�@�̖ړI�y�і@�T�O���P���̎�|���J���������̂ł���A�@���������N�̖@�����ɂ���Ċe�ݗ����i�Ɋւ���R������ȗ߂Œ�߂Č�t���A�s���̍ٗʂ̕������������悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ł���A�ݗ����ʋ��̐��x�ɉ��b�I�Ȗʂ�����Ƃ��Ă��A��������@����b�́u�ɂ߂čL�͂ȍٗʌ��v�����������̂ł͂Ȃ��B
(�C)�@�{���ɂ�����ٗʈᔽ
���@�����v�́A�C�����ł̐������ێ�����̂�����ɂȂ�A��ނȂ������������̂ł���A�C�����͂��܂�������o�Ϗ��s����i�C���������̎��Ɨ��͂Q�T�����邱�Ƃ��m���ł���Ƃ����B�j�ł���A�������P�O�N�ȏ������Ă��������v�������ŐV���ȐE��̂͋ɂ߂č���ł���B�܂��A�����̎Љ�i�o������ł��铯���ɂ����āA�����Ȃ��E�邱�Ƃ͂���ɍ���ł����āA��������ƁA�������Ƃ͘H���ɖ������ƂƂȂ�B����ɁA���{�ŏ\���N�������������v�w���A�C�����ɋA�����ꍇ�ɃC�����̊��ɓK���ł��Ȃ��Ȃ��Ă���\��������B
�@�܂��A�C�����́A�P�X�V�X�N�̃C�X�����v���Ȍ�A�C�X�������̐��T�ł���R�[�������ō��@�K�ƂȂ�ȂǁA�C�X�����������Ƃ����䂪���Ƃ͂������ꂽ�����������A�C�X���������̒��ł����Ɍ��i�ȋK�����d�鍑�ł����āA��{�I�l���̕ۏ�ɂ����Ă��A���������݂��A���ɏ����͒j���Ɣ�r���č��ʂ��ꂽ�n�ʂɂ�����Ă���B����A���������͏o�������A�������������S�t���Ȃ��Q�˂̂Ƃ�����䂪���ɋ��Z�������A���{����g�p���A���{�̕����ɂȂ��l�i�`�����s���A�䂪���̌��@�ŕۏႳ�ꂽ�j�������A���a��`�A���R��`�Ɋ�Â�������Ă���Ƃ���ł���A����A�����K���A�������̓_�ʼn䂪���Ƃ��܂�ɂ��������ꂽ�C�����ł̐����ɂȂ��ނ��Ƃ����ɍ���ł��邱�Ƃ͖����ł���B���������́A���{���p�����w�K�ɂ��A���̋��琧�x�ɓK�����Ă��̒��ŗD�G�Ȑ��т��グ�A����ɂ͍���������邱�Ƃ�]�݁A���̏����ɂ����Ă͒ʖ̐E�ƂɏA�����Ƃ��v���`���Ă�����̂ł���A���������y�ю������C�����ɋA�������ꍇ�A��L�̂悤�ȍ���Ȏ��Ԃ������邽�߂ɁA�����������w�K���p�����邱�Ƃ͕s�\�ł���A���̂��߂Ɍ��������͐��_�I�Ɋ�@�I��Ԃɒu����A���E�̊댯�����������˂Ȃ��B
���@������̋��Z�̎��R�̐N�Q
�@�O���l�́A�䂪���ɍݗ����錠����ۏႳ�����̂ł͂Ȃ����A�O���l�ł����{���ɂ����Ă��̎匠�ɕ����Ă�����̂Ɍ����Ă͋��Z�E�ړ]�̎��R���y�Ԃ��̂Ƃ���i�ō��ُ��a�R�Q�N�U���P�X����@�씻���E�Y�W�P�P���U���P�U�U�R�Łj��̂ł��邩��A�ݗ����i��L���Ȃ��҂��A�ދ������̍������̔��f�Ȃ��ɜ��ӓI�ɏZ���̑I����W�Q����Ȃ����������@��ۏႳ��Ă���Ƃ����ׂ��ł���Ƃ���A�@����b�ɂ��{���e�ٌ��́A�����炪���{�ɐ����̊�Ղ�L���Ă��鎖�����l�������A���Z�̎��R��N�Q�����@�Ȃ��̂ł���A���̓_�ɍٗʌ��̗��p�Ȃ�����E������B
���@�����̌����Ɋւ�����i�ȉ��u�q�ǂ��̌������v�Ƃ����B�j�ᔽ
�@�q�ǂ��̌������R���́A�u�����Ɋւ��邷�ׂĂ̑[�u���̂�ɓ������ẮA���I�Ⴕ���͎��I�ȎЉ�{�݁A�ٔ����A�s�����ǖ��͗��@�@�ւ̂�����ɂ���čs������̂ł����Ă��A�����̍őP�̗��v����Ƃ��čl���������̂Ƃ���B�v�ƋK�肵�Ă��邱�Ƃ�A�O�L���̏ɂ��݂�A�䂪���ɍݗ����邱�Ƃ��u�őP�̗��v�v�ɂ��Ȃ����̂ł���A�{���e�ٌ��́A�q�ǂ��̌������R���Ɉᔽ������̂ƂȂ�B
���@������ɍݗ����i��F�߂邱�Ƃ����獑�v�Ȃ�Ȃ�����
�@���̓_�́A��L(2)�C(�C)(��)�ɋL�ڂ̂Ƃ���ł���B
���@���������ᔽ
�@������ɐ旧���A�����P�P�N�X���P�P���ɍݗ����ʋ������߂ďW�c�o�������O���l�Ƒ��̒��ɂ́A������Ɠ��l�A���w�U�N�ɍ݊w���̒����ƂT�˂̒��j���܂ރC�����l�Ƒ����܂܂�Ă���A���̉Ƒ��ɂ͕����P�Q�N�Q���ɔ퍐�@����b���ݗ����ʋ����t�^����Ă���Ƃ���A�Ƒ��\������{�ł̑؍݊��ԓ��������قړ����Ƒ��ɂ����ĈقȂ������f���������̂́A�����̌����ɔ�����Ƃ��킴��Ȃ��B
(2)�@�{���e�ޗߔ��t�����̓K�@���ɂ���
�A�@�{���e�ٌ��̈�@�����p���邱�Ƃɂ���@
�@�O�L�̂Ƃ���A�{���e�ٌ�����@�ł���ȏ�A����Ɋ�Â��Ă��ꂽ�{���ޗߔ��t��������@�Ȃ��̂Ƃ������ƂɂȂ�B
�C�@�{���e�ޗߔ��t�����Ǝ��̈�@���i�\���I�咣�j
(�A)�@�ދ������ߏ����t�������ٗʍs�ׂł��邱��
���@�@�Q�S���̋K��
�@�@�Q�S���́u���̊e���̂P�ɊY������O���l�ɂ��ẮA���͂ɋK�肷��葱�ɂ��A�{�M����̑ދ����������邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肵�A�����́A�P�ɑދ��������R������ɂ����Ȃ��Ɖ�����̂͑����łȂ��A��̓I�ȒS���s�����̌����s�g�̂�������������ɋK�肵�Ă���ƂƂ炦��ׂ��ł���B
�@�����āA�����̕������A�u���邱�Ƃ��ł���v�ƋK�肳��Ă��邱�Ƃɂ��A�ٗʂ̕��������Ȃ���̂��͂Ƃ������A�Q�S���e���ɊY������O���l�ɂ��āA�ދ������葱���J�n���ŏI�I�ɑދ����������t���邩�ɂ��ẮA���@�҂��s�����ɑ��Ĉ��̕��̌��ʍٗʂ�F�߂����̂Ƃ����ق��Ȃ��B�܂��A�{���e�ޗߔ��t�����̂悤�ɐN�Q�I�s���s�ׂł����āA����������O�҂ɑ���W�ł���v�I�ȑ��ʂ������Ȃ����̂ɂ��ẮA�ٗʂ͈͎̔��͓̂��Y�s���s�ׂ̖ړI���ɏ]���Ď����ƒ�܂�ɂ��Ă��A��L�̖@���̕������ٗʂ��������̂Ɖ����邱�Ƃɉ���x�Ⴊ�Ȃ��B
���@�s���@�̓`���I���߂���̐���
�@�s���@�̉��߂ɂ����ẮA�`���I�Ɍ��͔����v�����[������Ă���ꍇ�s�����͂�����s�g���Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ̍l�����i�s���X��`�j����ʓI�ł���A���ɁA�O���l�̏o�����Ǘ����܂ތx�@�@�̕���ɂ����ẮA��ʂɍs�����̌����s�g�̖ړI�͌����̈��S�ƒ������ێ����邱�Ƃɂ��邩��A���̌����s�g�͂�����ێ����邽�߂̕K�v�ŏ����x�ɂƂǂ܂�ׂ��ł���ƍl�����Ă���i�x�@���̌����j�Ƃ���ł���A�ދ������ߏ����t�ɂ��ĒS���s�����ɍٗʂ��^������Ƃ������Ƃ́A�`���I�ȉ��߂ɉ������̂ł���B
���@�ދ������ߏ����t�����ɂ��Ă̍ٗʂ̕K�v��
�@���ہA�ދ������ߏ��̔��t�ɍٗʌ���F�߂Ȃ��ƁA�{���y�юs�����̂��鍑�ɑ��҂��邱�Ƃ��ł����A��������O���ւ̓��������Ă��Ȃ��O���l�ȂǑދ������ߏ��t���Ă����s���s�\�ł��邱�Ƃ����炩�ȏꍇ�ɂ��A��C�R�����͑ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w������B
���@�葱�̎���
�@�@��T�͂̎葱�K�������ƁA��C�R�����̍s���ދ������ߏ��̔��t���A���Y�O���l���ދ������������ׂ����Ƃ��m�肷��s�������Ƃ��ċK�肳��Ă���i�@�S�V���S���A�S�W���W���A�S�X���T���j�A�ދ������ɂ��Ă̎��̋K��ł���@�Q�S���̔F�߂�ٗʂ́A��̓I�ɂ́A�ދ������Ɋւ����L�K�����Ď�C�R�����ɗ^�����Ă���Ƃ����ׂ��ł���B
���@���̋@�ւ̍ٗʂƂ̊W
�@�ދ������̊e�i�K�ŁA���v��u���~�����v��u���̑��v�Ƃ��������ނ�����鎖�Ă����݂���Ƃ���A�ދ������葱���J�n���ꂽ����Ƃ����āA�K�������ދ������ߏ����t�Ȃǖ@�̒�߂�I�Ǐ������s��Ȃ��Ă��悢�ꍇ������A�ᔽ�����̒i�K�A�ᔽ�R���̒i�K�A�����R���̒i�K�A�ٌ��̒i�K�Ƃ������ދ������葱�̊e�i�K�ɂ����āA���ꂼ��̒S���҂��ٗʌ���L���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�ދ������葱�ɂ����ẮA�ދ������̎��s���@��Ґ�̎w������߂čs���A�{�M����ދ����ׂ��`������̓I�Ɋm�肷����̂Ɖ������_�ŁA��A�̎葱�ɂ����Ė@���e�s�����ɑ��ė^�����ٗʂ��W�Ă�����̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����̎���ɂ��A�ދ������葱��i�s�����邩�ǂ����ɂ��ẮA���Ƃ̍ٗʌ�������A���̊e�i�K�ɂ����Ă��S���҂ɍٗʌ������邱�Ƃ���A���̍ŏI�i�K�ł���ދ������ߏ��̔��t�̒i�K�ł���C�R�����ɍٗʂ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B��C�R�����ɂ́A�ދ������ߏ��t���邩�ۂ��i���ʍٗʁj�A���t����Ƃ��Ă���������t���邩�i���̍ٗʁj�ɂ��A�ٗʂ��F�߂��Ă���A��ጴ���Ɉᔽ���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ̋K�͂��^�����Ă���̂ł���B
(�C)�@��ጴ���ᔽ
���@��ጴ��
�@��ጴ���ᔽ�́A�@�����ƌ����A��{���̕ۏᓙ�������Ƃ��錛�@��̖@�����ł���A�ߏ�ȍ��ƓI�N�Q���玄�l�̖@�v��h�䂷�邱�Ƃɂ���A�䂪���ł��A���̍����ɂ͏���������̂́A���͍s����ʂɂ��ēK�p����邱�Ƃɂ��Ă͈٘_���Ȃ��Ƃ���Ă���B��̓I�ɂ́A�K�����̌����i�ړI��B�����邽�߂̎�i���Ӑ}�����ړI�B���̌��ʂ��������邱�Ɓj�A�K�v���̌����i�ړI��B�����邽�߂̎�i�������҂ɂƂ��čł����S�̏��Ȃ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ����Ɓj�A���`�̔�ᐫ�i��i�ƖړI�Ƃ̋ύt�����Ă��邱�ƁA�v����ɁA���Y��i��p���邱�Ƃɂ���ē����闘�v�����Y��i�ɂ���đ��Ȃ��闘�v�������Ă��邱�Ɓj�������e�ƂȂ�B
���@�{���ɂ������ጴ���ᔽ
(��)�@�{���e�ޗߔ��t�����ɂ�葹�Ȃ��闘�v
�@�{���e�ޗߔ��t�����ɂ��A�O�L(1)�C(�C)���̂Ƃ���A�����炪�C�����ɋA��������Ȑ������������邱�ƁA���������E���������S�t���Ă��犵��e���䂪���̕����Ƃ͂������ꂽ�C�����ł̐������s�����ƂƂȂ邱�Ɠ��A�{���e�ޗߔ��t�����ɂ�葹�Ȃ��闘�v�͋ɂ߂đ傫���Ƃ��킴��Ȃ��B
(��)�@�{���e�ޗߔ��t�����ɂ�蓾���闘�v
�@������́A������A�{���e�ޗߔ��t�����̌����ƂȂ����@�ᔽ�ȊO�ɂ͉���@��Ƃ����Ƃ͂Ȃ��A�P�ǂȎs���Ƃ��Ēn��Љ�ɂƂ��������𑗂��Ă������̂ł���A������̖{�M�ɂ�����ݗ����i��F�߂邱�Ƃɂ��A���{�̑P�ǂȕ����E�����ɍD�e����^���邱�Ƃ�������A���e�����y�ڂ����Ƃ͑z�肵��B���Ȃ킿�A������͌`���I�ɂ͖@�ᔽ�Ƃ�����@����тт��s�ׂ��s���Ă͂�����̂́A�����I�Ȗ@�v�N�Q�ɋy�����͂Ȃ��A��������Ǘ��ǂɏo�����Ĉᔽ������\���������̂ł���A���̂悤�Ȏ҂ɍݗ����i��t�^���邱�Ǝ��̂������ɍݗ����e���x�̍�����h�邪���Ƃ͍l�����Ȃ��B�܂��A�O���l��������u�P���J���v���s���J���͂Ƃ��Ď����K�v���͍����A�A�����J�A�t�����X�A�C�^���A�Ƃ��������O�����K�؍ݎ҂̑�K�͂Ȑ��K�����s���Ă���Ƃ���ł���A������ɍݗ����i��F�߂Ȃ����Ƃɂ���ĕی삳���ׂ����̗��v�͉��瑶�݂��Ȃ��Ƃ�����B
(��)�@����
�@�ȏ�ɂ��A�{���e�ޗߔ��t�����ɂ���đ��Ȃ��闘�v�Ɠ����闘�v�Ƃ��r�t�ʂ���ƁA�O�҂̕����͂邩�ɑ傫���͖̂��炩�ł���A�{���e�ޗߔ��t�����ɂ͔�ጴ���ᔽ������Ƃ�����B
��S�@���_�y�т���Ɋւ���ٔ����̔��f
�@�{���̑��_�́A�q�P�r�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���ٌ��̏������y�ёދ������ߏ����t�����ɂ������C�R�����̍ٗʂ̑��ہA�q�Q�r�{���e�ٌ��ɂ�����ٗʌ��s�g�̗��p�E��E�̑��ہA�q�R�r�{���e�ޗߔ��t�����̈�@���̑��ۂł���B
�P�@���_�P�i�ٌ��̏������y�ёދ������ߏ����t�����ɂ������C�R�����̍ٗʂ̑��ہj
(1)�@�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���ٌ��̏�����
�A�@�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�����@����b�́A���ًc�̐\�o�ɗ��R�����邩�ǂ������ٌ����āA���̌��ʂ���C�R�����ɒʒm���Ȃ���Ȃ炸�i�@�S�X���R���j�A��C�R�����́A�@����b����ًc�̐\�o�����R����Ƃ����|�̒ʒm�����Ƃ��́A�����ɓ��Y�e�^�҂���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����Łi�����S���j�A�@����b����ًc�̐\�o�����R���Ȃ��ƍٌ������|�̒ʒm�����Ƃ��́A���₩�ɓ��Y�e�^�҂ɑ����̎|��m�点��ƂƂ��ɁA�@�T�P���̋K��ɂ��ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ���Ă���i�@�S�X���T���j�B
�@�����̋K��ɂ��A�@�́A�@����b�ɂ��ٌ��̌��ʂ́A�ًc�̐\�o�ɗ��R������ꍇ�y�ї��R���Ȃ��ꍇ�̂�����ɂ����Ă��A���Y�e�^�҂ɑ��Ăł͂Ȃ���C�R�����ɑ��Ēʒm���邱�ƂƂ��Ă����A�@����b���ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��ƍٌ������ꍇ�ɂ́A�@����b����ʒm������C�R���������Y�e�^�҂ɑ��Ă��̎|��ʒm���ׂ����ƂƂȂ��Ă��邪�A�@����b���ًc�̐\�o�ɗ��R������ƍٌ������ꍇ�ɂ́A���Y�e�^�҂ɑ����̎|�̒ʒm�����ׂ����Ƃ��K�肵�Ă��炸�A�P�Ɏ�C�R���������Y�e�^�҂���Ƃ��ׂ����Ƃ��߂�݂̂ł����āA������̏ꍇ���A�@����b�����̖��ɂ����Ĉًc�̐\�o���������Y�e�^�҂ɑ����ډ������邱�Ƃ͗\�肵�Ă��Ȃ��i�Ȃ��A�����P�R�N�@���ȗ߂V�U���ɂ�������̖@�{�s�K���S�R���Q���́A�@�S�X���T���ɋK�肷���C�R�����ɂ��e�^�҂ւ̒ʒm�́A�ʋL�U�P���̂Q�ɂ��ٌ��ʒm���ɂ���čs�����̂Ƃ���ƒ�߂Ă��邪�A���̋K��͂����܂Ŏ�C�R�������e�^�҂ɑ��Ēʒm����������߂����̂ɂ������A�@�̒�ߎ��̂ɕύX���Ȃ��ȏ�A���̋K�������������Ė@����b���e�^�҂ɒ��ډ������邱�ƂƂȂ����Ƃ͍l�����Ȃ��B�j�B���������@�̒�ߕ����炷��A�@�S�X���R���ٌ̍��́A���̈ʒu�Â��Ƃ��Ă͑ދ������葱��S������s���@�֓��̓����I���ٍs�ׂƉ�����̂������ł����āA�s�����ւ̕s���\���Ăɑ��鉞���s�ׂƂ��Ă̍s�������i�ז@�R���R���́u�ٌ��v�ɂ͓�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�C�@���̂��Ƃ́A�@�̉����̌o�܂ɏƂ炵�Ă����炩�ł���B���Ȃ킿�A�@��T�͂̒�߂�ދ������̎葱�́A�@�̑O�g�ł���o�����Ǘ��߁i���a�Q�U�N���߂R�P�X���j�̐���̍ۂɁA���̂���ɑO�g�ł���s�@�����ғ��ދ������葱�߁i���a�Q�U�N���ߑ�R�R���j�T���Ȃ����P�X���̋K�肷��葱���p�������̂ƍl�����A���葱�߂ɂ����ẮA�����R���������t�����ދ������ߏ��ɂ��Ēn���R����ɕs���\���Ă����邱�Ƃ��ł��i�X���j�A�n���R����̔���ɂ��s��������ꍇ�ɂ͒����R����ɕs���̐\���Ă����邱�Ƃ��ł��i�P�Q���j�A�����R����́A�s���̐\���Ăɗ��R�����邩�ǂ����肵�āA���̌��ʂ��o�����Ǘ��������i�ȉ��u�����v�Ƃ����B�j�ɕ��邱�ƂƂ���A���������́A�����R����̔�������F���邩�ǂ����𑬂₩�Ɍ��肵�A���̌��ʂɊ�Â��A�����̍��߂����͑ދ������ߏ��̔��t�����҂̑������ƎႵ���͑ދ������𖽂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���Ă����i�P�S���j���̂ŁA���̒����̏��F���A�@�S�X���R���ٌ̍��ɕς�������̂ƍl������B�����āA�����̏��F�́A�����R����̕��čs������̂Ƃ���Ă��āA�ދ������ߏ��̔��t�����҂������ɑ��ĕs����\�����Ă邱�Ƃ͉���\�肳��Ă��炸�A�����̏��F�E�s���F�́A�ދ������葱��S�����鑤�̓����I���ٍs�ׂɂق��Ȃ�Ȃ��B���������āA�����x���p�������̂ƍl������@�S�X���R���ٌ̍��ɂ��Ă��A�ދ������ߏ��̔��t�����҂ً̈c�\�o��O��Ƃ���_�ɂ����ĈقȂ���̂́A���̎҂ɑ��钼�ڂ̉����s�ׂ�\�肵�Ă��Ȃ��ȏ�A��{�I�ɂ͓��l�̐��i�̂��̂ƍl����̂����R�ȉ��߂Ƃ������Ƃ��ł���B
�E�@�܂��A��L�̉��߂́A�@�S�X���P�����A�s�����ɑ���s���\���Ăɂ��Ă̈�ʓI�Ȗ@�ߗp��ł���u�ًc�̐\���āv��p�����ɁA�u�ًc�̐\�o�v�Ƃ̗p���p���Ă��邱�Ƃ�������t������B���Ȃ킿�A���a�R�V�N�ɑi��@��p�~����ƂƂ��ɍs���s���R���@�i���a�R�V�N�@��P�U�O���j�����肳�ꂽ���A���@�́A�s�����ɑ���s���\���Ă��u�ًc�\���āv�A�u�R�������v�y�сu�ĐR�������v�̂R��ށi���@�R���P���j�ɓ��ꂵ�A����ɔ����A�s���s���R���@�̎{�s�ɔ����W�@���̐������Ɋւ���@���i���a�R�V�N�@����P�U�P���j�́A����܂Ŋe�s���@�K����߂Ă����s���\���Ă̂����A�s���s���R���@�ɂ�邱�ƂƂȂ����s�������ɑ���s���\���Ă͔p�~����ƂƂ��ɁA�s�������ȊO�̍s����p�ɑ���s���\���Ă͏�L�R��ވȊO�̖��̂ɉ��߁A�����������̂̈�Ƃ��āu�ًc�̐\�o�v��p���邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@�����A�@�̑ΏۂƂ���O���l�̏o�����ɂ��Ă̏����͍s���s���R���̑Ώۂ���͏��O����Ă���i���@�S���P���P�O���j�Ƃ͂����A��L�̂Ƃ���s���s���R���@�̐���ɍۂ��Čʂɕs���\���葱�ɂ��ċK�肷�鑽���̖@�߂ɂ��Ă��s���\���Ăɂ��Ă̖@�ߗp��̓��ꂪ�}��ꂽ�̂ɁA�@�S�X���P���Ɋւ��ẮA�]�O�ǂ���u�ًc�̐\�o�v�Ƃ̗p�ꂪ�p����ꂽ�܂܉��������ꂸ�A�@�ɂ��Ă͂��̌�������ɂ킽���ĉ��������ꂽ�ɂ�������炸�A��͂�@�S�X���P���́u�ًc�̐\�o�v�Ƃ̗p��ɂ��Ă͉���������Ȃ������B�����āA���݂ɂ����ẮA�@�ߗp��Ƃ��Ắu�ًc�̐\�o�v�Ɓu�ًc�̐\���āv�͒ʏ��ʂ��ėp�����A�u�ًc�̐\�o�v�ɑ��Ă͉����`�������Ȃ����A���͉����`���������Ă��\���l�ɕۏႳ��Ă���̂͌`���I�v���̕s���𗝗R�Ƃ��ĕs���ɐ\�o��r�˂���邱�ƂȂ����炩�̎��̔��f���邱�Ƃ����ł���ꍇ�ɗp������p��ł���̂ɑ��A�u�ًc�̐\���āv�́A���e�I�ɂ��K�@�ȉ�������n�ʁA���Ȃ킿�葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂƂ��Ă̐\�����Ȃ����\������F�߂�ꍇ�ɗp������p��Ƃ��Ē蒅���Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B���������āA�����ɂ킽��������o�Ă��Ȃ��u�ًc�̐\�o�v�̗p�ꂪ�p�����Ă���@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�́A����ɂ��A�@����b���ދ������葱�Ɋւ���ē������邱�Ƃ𑣂��r��Ă�����̂ł͂��邪�A���ًc�̐\�o���̂ɑ��ẮA�퍐�̉����`�����Ȃ����A���́A�����`���������Ă��A�`���I�v���̕s���𗝗R�Ƃ��ĕs���ɐ\�o��r�˂���邱�ƂȂ����炩�̎��̔��f���邱�Ƃ��ۏႳ��邾���ł���A�\�o�l�Ɏ葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂƂ��Ă̐\�����Ȃ����\�������F�߂��Ă�����̂Ƃ͉�����Ȃ��i�ō��ّ�P���@�씻�����a�U�P�N�Q���P�R�����W�S�O���P���P�ł́A�y�n���ǖ@�X�U���̂Q��T���y�тX���P���ɋK�肷��ًc�̐\�o�ɂ��A���|�̔��������Ă���B�j�B
�@����āA�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ��Ă����@�S�X���R���́u�ٌ��v�́A�s���\���l�ɂ��������葱�I�����Ȃ����n�ʂ����邱�Ƃ�O��Ƃ���u�R�������A�ًc�\���Ă��̑��̕s���\���āv�ɑ���s�����ٌ̍��A���肻�̑��̍s�ׂɂ͊Y�������A�s�������i�ז@�R���R���ٌ̍��̎���̑i���̑ΏۂƂȂ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�G�@����ɁA�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɂ��ẮA��L�̂Ƃ���A�\�o�l�ɑ��Ė@�̋K��ɂ��葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂƂ��Ă̐\�����Ȃ����\�������F�߂��Ă�����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��邩��A�ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��|�ٌ̍������������葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂɕϓ�����������̂Ƃ������Ƃ͂ł����A���ٌ����s�������i�ז@�R���Q���́u�����v�ɓ�����Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��i�O�L�E�̍łP�����Q�ƁB�j�B
�I�@�ȏ�ɂ��A�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���@����b�ٌ̍��͓����I���ٍs�ׂƂ����ׂ����̂ł���A�s�������i�ז@�R���P���ɂ��������͂̍s�g�ɂ͊Y�����Ȃ��Ƃ����ׂ����̂ł���B�퍐�́A���ٌ��ɂ��čٌ������쐬����Ă��Ȃ����Ƃ�F�߂Ă���Ƃ���ł���A���̂悤�Ȏ����戵�����O�L�̋K�������Ɏ���܂Œ��N�ɂ킽���Čp������Ă������Ƃ́A���ٔ����Ɍ����Ȏ����ł���Ƃ���A���̓_���A�ٌ����������ٍs�ׂł��邱�Ƃ���b�t������̂Ƃ�����i�ނ���A��L���߂Ƃ͋t�ɍٌ����s�������i�ז@�R���P���ɂ��������͂̍s�g�ł���Ɨ��������ꍇ�A�ٌ����s�쐬�̓_��K�@�Ƃ���͍̂���ł���Ƃ��킴��Ȃ��B�j�B
(2)�@�ދ������ߏ����t�����ɂ������C�R�����̍ٗ�
�@�@�Q�S���́A�����e���̒�߂�ދ��������R�ɊY������O���l�ɂ��ẮA�@��T�͂ɋK�肷��葱�ɂ��A�u�{�M����̑ދ����������邱�Ƃ��ł���v�ƒ�߂Ă���B�����āA�����Ȃ�ꍇ�ɂ����čs�����ɍٗʂ��F�߂��邩�̔��f�ɂ����āA�@���̋K�肪�d�v�Ȕ��f�����ƂȂ邱�ƂɈ٘_�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�@���̕������s��������̂Ƃ��āu�E�E�E���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ̋K��������Ă���ۂɂ́A���̍ٗʂ̓��e�͂Ƃ������A���@�҂��s�����ɂ��镝�̌��ʍٗʂ�F�߂��|�ł���Ɖ����ׂ����̂ł����āA�������ދ������Ɋւ�����̋K��Ƃ��āA�ދ��������R�ɊY������O���l�ɑ��đދ����������邩�ۂ��ɂ��Ă͂����S������s�����ɍٗʂ����邱�Ƃ��K�肵�Ă���͖̂��炩�ł���A�@��T�͂̎葱�K��ɂ����ẮA��C�R�����̍s���ދ������ߏ��̔��t���A���Y�O���l���ދ������������ׂ����Ƃ��m�肷��s�������Ƃ��ċK�肳��Ă���i�@�S�V���S���A�S�W���W���A�S�X���T���j�Ɖ�����邱�Ƃ��炷��A�ދ������ɂ��Ď��̋K��ł���@�Q�S���̔F�߂�ٗʂ́A��̓I�ɂ́A�ދ������Ɋւ����L�葱�K�����Ď�C�R�����ɗ^�����A���̌��ʁA��C�R�����ɂ́A�ދ������ߏ��t���邩�ۂ��i���ʍٗʁj�A���t����Ƃ��Ă���������t���邩�i���̍ٗʁj�ɂ��A�ٗʂ��F�߂��Ă���Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̂悤�ȉ��߂́A�s���@�̉��߂ɂ����ē`���I�ɔF�߂���s���X��`�A���Ȃ킿���͔����v�����[������Ă���ꍇ�ɂ��s�����͂�����s�g���Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ̍l������A�x�@���̌����A���Ȃ킿�A�x�@�@����ɂ����ẮA��ʂɍs�����̌����s�g�̖ړI�͌����̈��S�ƒ������ێ����邱�Ƃɂ���A���̌����s�g�͂�����ێ����邽�ߕK�v�ŏ����Ȃ��̂ɂƂǂ܂�ׂ��ł���Ƃ̍l�������肩�A���@�P�R���̎�|���Ɋ�Â��A���͓I�s����ʂɔ�ጴ����F�߂�l�����ɂ���Ă��m�肳���ׂ����̂ł���B
�@���̂悤�Ɏ�C�R�����ɍٗʌ���F�߂邱�Ƃɑ��A�퍐�́A�@�S�V���S���A�S�W���W���y�тS�X���T�����A��������u��C�R�����́E�E�E�i�����j�E�E�E�ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�Ă��邱�Ƃɔ�����|�咣����B�������A�ދ������葱�́A�����Ƃ��ėe�^�҂ł���O���l�̐g�������e�ߏ��ɂ��S�����Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă��邽�߁A���̎葱��S������҂����̍l�����Ȃ��܂܂Ɏ葱�𒆒f���A���u���邱�Ƃ������Ȃ��悤�ɁA�@�S�V���P���A�S�W���U���y�тS�X���S���ɂ����āA���ꂼ��e�^�҂��ދ��������R�ɊY�����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�Ɂu�����ɂ��̎҂���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���Ƃ��߂�ƂƂ��ɁA�@�S�V���S���A�S�W���W���y�тS�X���T���ɂ����ẮA�ދ������Ɍ����Ď葱��i�߂�ꍇ�ɂ����Ă��A�u�ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ď�C�R�����̋`���Ƃ��ċK������������̂Ɖ�����A�����̋K��Ɩ@�Q�S�������킹�ĉ��߂���A���̋K��ł���@�Q�S���ɂ����đދ������ɂ��đO�L���ʍٗʋy�ю��̍ٗʂ�F�߂Ă���ȏ�A��C�R�����ɂ����āA���������ٗʂ̔��f�v�f�ɂ��ď\���l�����Ă��Ȃ��ދ������葱��i�߂�ׂ��ł���Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A���Ɩ��͑ދ��Ɏ���Ȃ��܂葱����u�����A�@�̒�߂鎟�̎葱�ɐi�ށi�ދ������ߏ��t����j�ׂ����Ƃ��߂����̂Ɖ����ׂ��ł���A���̂悤�ɖ@�̊e�K������̈ʒu�Â��ɉ����ĉ��߂���A��C�R�����ɑދ������ߏ����t�ɂ��Ă̍ٗʂ�F�߂邱�Ƃ́A�@�S�V���S���A�S�W���W���y�тS�X���T���̊e�K��Ɖ��疵��������̂ł͂Ȃ��B
�@�܂��A�퍐�́A�㋉�s���@�ւł���@����b�̈ӎv�����b�̎w���ē��鉺���s���@�ւł����C�R�������A���̓Ǝ��̔��f�Ɋ�Â��ĕ����A���邢�͂��̓K�p�������l���ł���Ƃ��邱�Ƃ͍s���g�D�@��̊ϓ_����l�����Ȃ��|�̎咣�����邪�A�O�L�̂Ƃ���ٌ����s�������ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�s���@�֓����ɂ����錈�َ葱�ɂ����Ȃ��Ɖ����ׂ��ł��邩��A���̌��ق̎�|���ދ������ߏ��̔��t�𖽂����|�ł���Ƃ��Ă��A����͑g�D�@��̋`����������ɂƂǂ܂�A����ɂ�蓖�Y���t�������K�@�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��A�q�ϓI�ɍٗʈᔽ�Ȃ�����ጴ���ᔽ�̎���������ꍇ�ɂ͓��Y�����͈�@�Ƃ��킴��Ȃ��B���̂��Ƃ͏����������O�ɏ㋉�s�����̌��ق��čs�������������ꍇ��ʂɐ����邱�Ƃł���A���̂悤�Ȍ��ق��s��ꂽ�Ƃ��Ă��A�ٗʌ��s�g�̎�̂́A�����܂ł����Y�s���������s���s�����ł���A�㋉�s�����ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��̂ł���B
(3)�@�ȏ��O��Ƃ���A�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���ٌ��ɂ����̎���������߂�i�ׂ́A�Ώۂ̏������������s�K�@�Ȃ��̂Ƃ��킴��Ȃ����ƂƂȂ�A��L(2)�̂Ƃ���A�ދ������ߏ����t�����ɂ����ʍٗʁA���̍ٗʂ��F�߂��Ă��邱�Ƃɂ��A�ދ������ߏ����t�����̎���������߂�i�ׂɂ����āA�ދ��������R�̗L���ɉ����A���̍ٗʂ̈�E���p�ɂ��Ă��������̈�@���R�Ƃ��Ď咣�����邱�ƂƂ��ׂ��ł���Ɖ����ׂ��ł���B���̂悤�ȉ��߂ɂ��A�O�L�����̉��߂ɂ��@�S�X���R���̖@����b�ٌ̍��ɂ��Ɨ����ēK�@�Ɏ���i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ邪�A�@�S�X���R���ٌ̍��̎���i�ׂŖ��Ƃ��ꂽ�@����b�̍ٗʌ��s�g�̓K�ۂ́A�ދ������ߏ����t�ɂ������C�R�����̍ٗʌ��s�g�̓K�ۂɂ����Ă��قړ���̓��e�ŐR���̑ΏۂƂȂ�ׂ����̂ł����āA�O���l���ދ�����������邱�Ƃ𑈂��@������߂���̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�ނ���A�ݗ����ʋ������邩�ۂ��̔��f�����܂��ܖ@�S�X���ٌ̍��ɓ������Ă����Ƃ̐��x���̗p����Ă��邱�Ƃ݂̂𑨂��A�{���S���ʌ̐��x�ł���ݗ����ʋ��̔��f�i�@�T�O���R���́A�ݗ����ʋ����A���ދ��������R�ɊY�����邩�ۂ��f���Ă����@�S�X���ٌ̍��Ƃ͖{���I�ɈقȂ鐧�x�ł��邱�Ƃ���A�ݗ����ʋ������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����āA�����@�S�X���S���̓K�p�ɂ��ًc�̐\�o�ɗ��R������|�ٌ̍��Ƃ݂Ȃ��|���߂Ă���B�j�̓��ۂ�@�S�X���R���ٌ̍��̈�@���R�Ƃ��Ď咣�����邱�Ƃ�F�߂�Ƃ��������̂�����߂��̗p����K�v���Ȃ��Ȃ���̂ł���B
(4)�@����
�@�ȏ�ɂ��A�{���i���̂����A�����炪�퍐�@����b�������{���e�ٌ��̎���������߂镔���͑Ώۂ̏������������s�K�@�Ȃ��̂Ƃ����ׂ��ł���B�����āA�����ł���ȏ�A���_�Q�ɂ��Ă̔��f�͕s�v�Ƃ������ƂɂȂ�A�ȉ��A���_�R�i�ދ������ߏ����t�����̓K�@���j�ɂ��Ĕ��f���邱�ƂƂȂ邪�A�@�́A��C�R�����̍s���ׂ���̓I�ȍٗʊ���߂Ă��Ȃ����A����܂ł̎����ɂ����Ă͔퍐�炪�咣����Ƃ����C�R�����ɂ͑S���ٗʂ̗]�n���Ȃ��Ƃ̍l�������Ƃ��Ă����̂ł��邩��A�s���������ɂ����Ă��ٗʊ���͍��肳��Ă��Ȃ��B�����Ƃ��A�@�́A�ދ��������R�̂���҂�K�@�ɍݗ�������B��̐��x�Ƃ��čݗ����ʋ��Ƃ������x��݂��Ă���̂ł��邩��A���̎�|���炷��ƁA��C�R�����͍ݗ����ʋ������ׂ��҂ɂ��đދ������ߏ��t���邱�Ƃ͋�����Ȃ����ʁA�ދ������ߏ��t���Ȃ����Ƃ��������͍̂ݗ����ʋ������ׂ��҂Ɍ�����Ɖ����ׂ��ł���B��������ƁA���_�R�ɂ��Ă̔��f���e�́A���_�Q�ɂ��Ĕ��f�����ꍇ�̔��f���e�ƑS����v���邱�ƂƂȂ�B�܂��A�퍐��́A��C�R�����ɂ͍ٗʌ����Ȃ��Ƃ̎咣�����Ă��邽�߁A�{���e�ޗߔ��t�����ɓ������Ăǂ̂悤�ȍٗʔ��f�����ꂽ�̂����咣���Ȃ��B������`���I�Ɏ�舵���ƁA�퍐��C�R�����͎��̓��ۂ���̓I�Ɍ������Ȃ��܂܌��_�̂ݔF�߂����̂Ƃ��āA���̏�������舵�킴��Ȃ��Ȃ邪�A�퍐��́A�퍐�@����b�������{���e�ٌ����K�@�Ȃ��̂ł���Ƃ��ċ�̓I�Ȏ咣�����Ă���Ƃ���ł���A���̎咣�́A���ɔ퍐��C�R�����ɍٗʌ�������Ƃ���Ȃ�A���l�̍ٗʔ��f�Ɋ�Â��Ė{���e�������������̂ł���Ǝ咣���Ă�����̂ƑP���ł��邩��A�ȉ��̌����ɂ����ẮA�퍐��C�R�������퍐�@����b�Ɠ��l�̔��f�Ɋ�Â��Ė{���e�ޗߔ��t�������������̂Ƃ̑O��ōs�����ƂƂ���B
�Q�@���_�R�i�{���e�ޗߔ��t�����̓K�@���j
(1)�@�����W
���@�����̌o��
�@�����́A�P�X�U�R�N�i���a�R�W�N�j�W���Q�R���ɃC�����̃e�w�����Ő��܂�A�P�X�V�W�N�i���a�T�R�N�j�ɒ��w�𒆑ނ�����A���炭�����Ē��߂����ƕ�����̎؋��ɂ��A�m���̖D����Ђ�ݗ����o�c���s�������A�C�����C���N�푈���ɂ�萭��E�i�C���s����ƂȂ�A��Ђ��������Ȃ��Ȃ����B���̌�A�P�X�W�R�N����P�X�W�T�N�܂ŕ����ɕ����C�����C���N�푈�ɏ]�R�����B�����āA�P�X�W�U�N�ɂ́A�����Ȃƌ����������A���肵���E�邱�Ƃ�����A�����������o���������̂́A�������ꂵ���Ȃ������߁i���̓_�ɂ��ẮA����T���A��P�R���ؒ��ɂ́A���قȂ�����|�ɂ��ǂ߂�L�ڂ����邪�A�����̏؋��S�̂̎�|���f�e�؋��ɏƂ炷�ƁA��L�F��ɔ�������̂ł͂Ȃ��ƔF�߂�̂������ł���B�j�A���{�ɍs�������ƍl����悤�ɂȂ�A�����Q�N�T���ɗ��������B�����͂R�������x�̒Z���ԓ����A���������ł��������A�����������v���X�`�b�N��Ђŋ������ǂ���ɂ͎x�����Ȃ��������Ƃ�A���{�ŐE�Đ��������肷�邤���ɁA����ɓ��{�ɒ����������Ƃ����C���������������ƁA�܂��A�C�����ɖ߂��Ă��E���Ȃ����߁A�A������@��������A�s�@�c������Ɏ������B
�i���S�A�P�P�A�Q�R�A�Q�X�A�����v�{�l�j
���@������̐����̏�
�@�����v�́A���������A�Q�n�������s�̃v���X�`�b�N��ЂɋΖ����A���̌�A�ʂ̃v���X�`�b�N��Ђ�p�`���R������Г��ɋΖ������̂��A�����T�N�P������͓��c��ɂ����ĉ������z�ǍH�Ƃ��ĉғ����Ă������A�s�@�A�J�̔��o�����ꂽ�В�����̊��߂ɏ]���āA�����P�P�N�Q���ɓ��Ђ����߁A�S���g���Ă̐����Ƃ��n�߂�ƂƂ��ɁA���ɂ͓��c��̉����������A�{�����������ɂ͂P�T���~����Q�T���~�̌������������i�����P�O�N�ɂ����ĂR�O�R���O�S�O�O�~�̎����Ă���j�B������́A�����S�N�R�����납�畽���P�Q�N�S������܂ł̊ԁA�Q�n�������s�����Ԓn���̃A�p�[�g�ɋ��Z���Ă����B
�@�@�i�b�R�A�P�T�A���S�A�T�A�Q�R�j
�@�����v�́A���݁A�F�l�̂��ƂŃA���o�C�g�����A���ɂP�V�`�P�W���~�̎����Ă���A�����P�Q�N�T���ɌQ�n������S�������Ԓn�̖ؑ������Q�K���Ă̏Z��������A������S���Ő������Ă���B
�@�@�i�b�S�A�����v�{�l�j
�@���������́A�����V�N�S���A���Z�n�̗ג��ł���Q�n������S�����̂�����ꏬ�w�Z�ɓ��w���A�����P�R�N�S���ɂ́A�������������w�Z�ɓ��w���A���ݒ��w�Z�R�N���ɍ݊w���Ă���B���������́A�{�����������͂��Ƃ��A���݂������v�E�ȂƂ̉�b�����{��ōs���Ă���A�����v��Ȃ��b���y���V����𗝉����邱�Ƃ����ł�����̂́A�y���V�����b�����ƁA�������Ƃ͂ł��Ȃ��B���������Ǝ��������{��ʼn�b�����Ă���B���������́A�������C�����ł͒��p���邱�Ƃ��l�����Ȃ����{�̏��������镞�𒅗p���A�H�����J���[�A�����ȂǓ��{�̎q�����D�ސH�����D�݃C���������͍D�܂Ȃ����A��F�W��Ƒ��Ƃ̊W���C�����̏K���ɂ͂Ȃ���ł��炸�A���S�ɓ��{�̏K���ɂȂ���ł���A���������䂪���ɍݗ����A�w�𑱂��邱�Ƃ������]��ł���B
�@�@�i�b�T�A�Q�P�A�Q�Q�A�S�S�A���S�O�A�����v�{�l�A�٘_�̑S��|�j
�@�����v�y�ь����Ȃ́A���������E���������ɑ��ăC�X�������̂��F��̂��Ƃ���������A�f�H���s������A�R�[������ǂݕ�������Ƃ������@��������s���Ă͂�����̂́A�q���炪���ۂɏ@��������s�����Ƃ͂Ȃ��A�����炪���X�N�ɍs�����ƂȂǂ��Ȃ��B
�i�����v�{�l�j
�@�������Ƃ́A�����S�N����{�������̒��O�܂Ŗ�W�N�ԓ����s�ɂ����Ē�Z���A���̊ԁA�{���������R�ȊO�ɂ͖@�ɐG��邱�Ƃ��Ȃ������ɐ������Ă���A�����P�S�N�Q���ɂ́A�����v�y�эȂ��A���c�@�l���{���ۋ��狦��y�э��ی𗬊�������{�������{��\�͎����R���ɍ��i���A�܂��A���������E�����̊w�Z�E�ۈ牀�̍s�����ɂ͕K���Q������ȂǁA�n��ɂƂ��������𑗂��Ă���B
�i�b�P�V�A�P�W�A�����v�{�l�j
�@������Ƒ����Z�ތQ�n������S�����́A�l������P���Q�O�O�O�l�ł���A�����O���l�͂R�O�O�����x�ł���B�����ɂ���㕐��w�o�ϊw���ւ̗��w�����������A�ݗ����ʋ����C�����l���������Ă���B�������ی𗬋���A�����̓��{�ꋳ�����s���Ȃǂ��Ă���A���Ƃ��Ă��O���l�J���҂₻�̉Ƒ�������邱�ƂɂȂ�Ă���A��R�����Ȃ��A�g���u�������������Ă��Ȃ��B
�i�b�R�P�j
���@�C�����̏�
(��)�@�C�����ɂ����錴����̋�̓I��
�@�����v�̉Ƒ��́A���e�̂ق��ɌZ���P�l�A�o���Q�l�A�킪�R�l�C�����Ő������Ă���B���́A�{���e������̕����P�R�N�S�����ɖS���Ȃ����B���́A���O�A�e�w�����s���ŃX�[�p�[���o�c���Ă������A���݂͒�Q�l�����X�[�p�[���o�c���Ă���B
�i���S�A�����v�{�l�j
�@�����v�́A�����W�N����܂łɁA���{�~�ō��v�R�O�O���~���C�����ɂ��镃�ɑ������A������āA�C�����̕��̉Ƃ̋߂��ɒ��Â̏Z�����w�������B�������A���̏Z���́A�����v�����e����Ă���ԁA�����Ȃ�̐����������K�v�ƂȂ������߁A�����P�Q�N�V���ɔ��p����A���݁A������Ƒ��́A�C���������ɍ��Y��L���Ă��Ȃ��B
�i�b�P�V�A�P�W�A���S�A�T�A�P�R�A�����v�{�l�j
(��)�@�C�����̈�ʓI��
�@�C�����ɂ����ẮA�C�X�������Ɋ�Â��@���I�ȉ����Ɍ������K�肳�ꂽ����������A�������q���ɋ����鋳�{�Ɋ�Â��A�c���̂��납�������g�ɂ��邱�Ƃ����R�ƂȂ��Ă���B��̓I�ɂ́A�����́A�w�W���u�i�����ȕ����K��j���`���t�����A�������\���ɕ����A���ς͋֎~����A�ᔽ�������ꍇ�ɂ͔����A�ڑł����̌Y���Ȃ����A���R�ɒj���Ƙb�����Ƃ⎩�R�ɊO�o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ق��A�ƒ�y�э��Y���ɂ��Ė@����̍��ʂ�����Ă���B�܂��A�H�����ɂ��Ă��ؓ���H�ׂ邱�Ƃ��ւ���ꂽ��A���}�_���i�f�H�j�̏K��������Ȃǂ̒�߂�����B
�i���W�X�A�����v�{�l�j
�@�C�����̋��琧�x�́A���w�Z���T�N�A���w���R�N�A���Z���S�N�A��w���Q�N����S�N�Ƃ��������x�ƂȂ��Ă���A���w�Z�܂ł��`������Ƃ���Ă���B���Z�ɂ͂W�O�`�X�O�p�[�Z���g�̎҂����w���邪�A���̍ۂɂ͎���������B�ʏ�̊w�Z�ɂ����Ă̓y���V���ꂪ�ł��Ȃ��҂̂��߂̃N���X�Ȃǂ͗p�ӂ���Ă��炸�A��ʉƒ�ł͕��S���邱�Ƃ�����ȋ��z���x�����ē��ʎ��Ƃ���ق��Ȃ��B
�i���W�X�A�����v�{�l�j
�@�����v�́A������̒m�l�Ō��������Ɠ��N�̂d�����{����C�����ɋA��������A�w�Z�Ő搶�̘b�����t���킩�炸�A���Ƃ��S�R�����ł��Ȃ����߁A���ʂ̊w�Z�ɂ͒ʂ�Ȃ��Ȃ����ƕ������B
�i�b�Q�P�j
�@�����P�S�N�P���P�U���ɍ��ۘA���o�ϋy�юЉ��c�l���ψ���ɂ����Ă��ꂽ�C�����ɂ�����l���̕ɂ��A�C�������{�����̌����Ȕ��\�ł������P�R�N�R������V���ɂ����Ď��Ɨ����P�R�D�V�p�[�Z���g�Ƃ���A���N�U���̂���V���ɂ��G�ߘJ���҂�o�^����Ă��Ȃ����Ǝ҂��܂߂�Q�T�p�[�Z���g���Ă��邱�Ƃ��m���Ƃ̕�����A�x�d�Ȃ鋋�������̎��Ă�A��K�͂ȘJ���҂̈�ĉ��ٓ��̕�����Ă���B
�i�b�S�R�j
���@�W�c�o���̏�
�@������́A�����P�P�N�P�Q���Q�W���ɓ������ǂɏo�����A���Ȃ̕s�@�c�������̐\�����s�������̂ł��邪�A������͍ݗ����ʋ����擾���ׂ��A��čs���Ƃ��ďo�������O���[�v�ɎQ�����Ă�����̂ł���B���O���[�v�́A��P���o���҂Ƃ��ĂT�Ƒ��A�Q�P�g�҂̂Q�P�������N�X���P���ɓ������ǂɏo�����A��Q���o���҂Ƃ��ĂT�Ƒ��A�P�V���������P�P�N�P�Q���Q�W���ɏo�������B
�i�b�V�A�W�j
�@�����̉Ƒ����ɂ��ẮA�P�O�Ƒ��A�Q�P�g�҂̂����A�T�Ƒ��ɑ��čݗ����ʋ����F�߂��A�u��Z�v�̍ݗ����Ă���B�ݗ����ʋ������Ƒ��̍\���́A�P�Q�ˁi���w�Z�U�N���j�̏����ƂT�˂̒��j�����v�w��P�T�˂̒��j�����v�w��������A��������P�O�N�߂����{�ɂ����Đ������Ă�����̂ł������B
�i�b�V�A�W�j
(2)�@�{���ɂ������C�R�����̍ٗʂ̓K��
���@���f�̂�����|���ɍٗʊ�Ƃ̊W�ɂ���
�@�O�L�P(4)�Ő��������Ƃ���A��C�R�����̍ٗʂ̓K�ۂ́A�v����Ƃ���A���Y�O���l���ݗ����ʋ���^����ׂ��҂ɊY�����邩�ۂ��ɂ��Ă̔��f��������ƕ]�������邩�ۂ��ɂ�����Ƃ���A���̔��f���̂ɂ��ٗʂ��F�߂���ׂ����̂ł��邩��A�ٔ����Ƃ��ẮA��C�R�����̏�L�̓_�ɂ��Ă̔��f�͍ٗʌ��̈�E���p�����������ۂ��A���Ȃ킿�A������ɂ��ݗ����ʋ���^����ׂ��҂ɊY�����邩�ۂ��̔��f�ɓ�����A���R�ɏd�����ׂ�������s���Ɍy�����A���́A�{���d�����ׂ��łȂ�������s���ɏd�����邱�Ƃɂ��A���̔��f�����E���ꂽ���̂ƔF�߂��邩�ۂ��Ƃ����ϓ_����R�����s���A���ꂪ�m�肳���ꍇ�ɂ͖{���e�ޗߔ��t�������������ׂ����̂Ƃ���̂������ł���B
�@�����āA��C�R�������{���e�ޗߔ��t�����ɓ�����A�����Ȃ鎖�����d�����ׂ��ł���A�����Ȃ鎖�����d�����ׂ��łȂ����ɂ��ẮA�{���@�̎�|�Ɋ�Â��Č����ׂ����̂ł��邪�A�O���l�ɗL���ɍl�����ׂ������ɂ��āA������A�����I���َ͖��I�Ɋ���݂����A����Ɋ�Â��^�p������Ă���Ƃ��́A���������̗v�����炵�āA���i�̎���Ȃ�����A���̊�����邱�Ƃ͋�����Ȃ��̂ł���A���Y��ɂ����ē��R�l�����ׂ����̂Ƃ���Ă��鎖����l�������ɂ��ꂽ�����ɂ��ẮA���i�̎���Ȃ�����A�{���d�����ׂ�������s���Ɍy���������̂ƕ]��������Ȃ��B�퍐��́A���̓_�ɂ��āA�ٗʌ��̖{���������ɂ���ĕύX�������̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ��āA���s���̖�肪������ɂ����Ȃ��Ǝ咣���A�ߋ��̍ٔ���ɂ��������ʘ_�Ƃ��Đ���������̂����Ȃ��Ȃ����i�Ⴆ�A�ō��ّ�@�씻�����a�T�R�N�P�O���S�����W�R�Q���V���P�Q�R�P�Łj�A���̂悤�ȍl�����́A�s���ٗʈ�ʂ��K�����镽��������������̂ł����č̗p�ł��Ȃ��B
���@�����ԕ����ɍݗ����Ă��鎖���̕]��
(��)�@�{���̓����́A�O�L(1)�̎����W���炷��ƁA�������Ƃ��P�O�N�߂��ɂ킽���ĕ��������R�ƍݗ����p�����A���ɑP�ǂȈ�s���Ƃ��Đ����̊�Ղ�z���Ă��邱�Ƃɂ���B������́A���̓_���A�L���ɍl�����ׂ��d�v�Ȏ����ł���Ǝw�E����̂ɑ��A�퍐��́A����͌�����ɂƂ��ėL���Ȏ����ł͂Ȃ��A�ނ���A�����ԕs�@�ݗ����p�������_�ɂ����ĕs���v�Ȏ����ł���Ǝ咣����B���̂��Ƃ��炷��ƁA�{���e�����́A��L������������ɕs���v�Ȏ����ƕ]�����Ă��ꂽ���̂ƔF�߂���Ȃ��B
(��)�@�������A��L�̎����́A�ݗ����ʋ���^���邩�ۂ��̔��f�ɓ������āA�e�^�ґ��ɗL���Ȏ���̑��ɏグ�邱�Ƃ��A������A���Ȃ��Ƃ��َ��I�Ȋ�Ƃ��Ċm�����Ă�����̂ƔF�߂���B
�@���Ȃ킿�A���̂悤�ȍݗ����i�������Ȃ��܂ܒ����ɂ킽���čݗ����p������҂��������ɏ���Ă��邱�Ƃ͌��m�̎����ł��邪�A���̂悤�Ȏ��Ԃ͑����ȑO����p�����Ă���̂ł����āA���a�T�U�N�̖{�@�̑薼���܂ޑ�����̍ۂɂ��A���̉�������ŋc�_���ꂽ�Ƃ���ł���B�Ⴆ�A���a�T�U�N�T���P�T���̏O�c�@�@���ψ���ɂ����āA�e�ψ��������̎҂̂������̏��������҂ɓK�@�ȍݗ����i��^����ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ̗��ꂩ��A�u���������Ă���\�N�ȏキ�炢�������ҁA�����Ă��ܑ�b�̂��������悤�ɎЉ�����f�s���������������肵�Ă���҂ɂ��ẮA����\���������ꍇ�ɂ͌����ɒl����i�ݗ���F�߂邱�Ƃ���������ɒl����Ƃ̎�|�j�Ƃ����ӂ��Ȑ������Ƃ����Ă���̂ł����A�������ł����B�v�Ƃ̎���������̂ɑ��A�����̖@���ȓ����Ǘ��ǒ��́A�u�X�̎��Ăɂ��܂��ẮA���̕s�@�����҂̋��Z���A�Ƒ����A���ʂ̎����T�d�Ɍ������āA�l���I�z����v����ꍇ�ɂ͓��ɂ��̍ݗ���F�߂Ă���킯�ł������܂��B���������܂��āA�s�@�����҂��E������܂��ċ����ދ��̎葱���Ƃ�ꂽ��ł��A�@����b�̓��ʍݗ��������������ꍇ�ɂ͏o��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�v�Ƃ�����A����ɑ������ψ��̎���ɓ����āA�u���ݕs�@�����҂̂����ɂ́A�q�������悢��w��ɒB�����Ƃ��A�������������݂����疼�̂�o�āA�搶�̂������Ⴂ�܂��������鎩��\��������l������܂��B���������ꍇ�ɂ́A���ǂ��Ƃ������܂��ẮA���R�A�����l������ɓ�����܂��ăv���X�̍ޗ��ƍl���Ă���܂��B�v�Ɠ��ق��A����ɓ����̖@����b�́A�u���ʍݗ������邢�͉i�Z�������炦��̂͂ǂ������l�ł��邩�Ƃ���������x�̊�����炩�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���͂��܂̂悤�Ȃ��b���f���Ă��܂��Ƒ�Ȃ��Ƃ���Ȃ����ȂƎv���܂��B����܂ł���Ă������Ƃ�U��Ԃ��Ă݂āA�܂Ƃ߂�̂�����ȂƁA���܂��b���f���Ȃ���l�����킯�ł���܂��B����ɁA�X�̎��Ăɂ��ď�������ꍇ�ɂ��A�]���ȏ�ɐl���I�Ȕz���������Ă������Ƃ���̓]���ɂȂ��Ȃ����ȁA�����v���킯�ł������܂��āA���Ƃ��Ă͂ł������l���I�Ȕz���Ƃ������̂��d�����Ă��������ȁA�����v���Ă���܂��B�v�Ɠ��ق��Ă���̂ł���i�����t���O�c�@�@���ψ���c�^��P�S���R�Ȃ����S�Łj�B
�@�܂��A���̂Ƃ��̖@�����ɂ���Ė@�U�P���̂X�y�тP�O���V�݂���u�@����b�́A�o�����̌����ȊǗ���}�邽�߁A�O���l�̓����y�эݗ��̊Ǘ��Ɋւ���{��̊�{�ƂȂ�ׂ��v��i�o�����Ǘ���{�v��j���߂���̂Ƃ���B�v�A�u�@����b�́A�o�����Ǘ���{�v��Ɋ�Â��āA�O���l�̏o�����������ɊǗ�����悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƒ�߂��A����Ɋ�Â��Ė{���e�����O�̕����P�Q�N�R���Q�S���ɍ��肳�ꂽ�u�o�����Ǘ���{�v��i��Q���j�v�i�@���ȍ����P�S�X���j�V
�Q(2)�ɂ́A�u�ݗ����ʋ������O���l�̑����́A���{�l���Ƃ̖��ڂȐg���W��L���A�܂����ԂƂ��āA���܂��܂Ȗʂʼn䂪���ɏ����ɂ킽�鐶���̊�Ղ�z���Ă���悤�Ȑl�ł���B����̓I�ȗ�Ƃ��ẮA���{�l�ƍ������A���̍����̎��Ԃ�����ꍇ�ŁA���ǖ@�ȊO�̖@�߂Ɉᔽ���Ă��Ȃ��O���l����������B�@����b�́A���̍ݗ����ʋ��̔��f�ɓ������ẮA�X�̎��Ă��Ƃɍݗ�����]���闝�R�A���̊O���l�̉Ƒ��A�����A�f�s���̑��̎�����A���̊O���l�ɑ���l���I�Ȕz���̕K�v���Ƒ��̕s�@�؍ݎ҂ɋy�ڂ��e���Ƃ��܂߂đ����I�ɍl�����A��{�I�ɁA���̊O���l�Ɖ䂪���Љ�Ƃ̂Ȃ��肪�[���A���̊O���l��ދ��������邱�Ƃ��A�l���I�Ȋϓ_�������肪�傫���ƔF�߂���ꍇ�ɍݗ�����ʂɋ����Ă���B�v�Ɩ��L���Ă���B���̎�|�́A�䂪���ɂ����ď����ɂ킽�鐶���̊�Ղ�z���A�ݗ����̑f�s�ɖ�肪�Ȃ��A���̊O���l�Ɖ䂪���Љ�Ƃ̂Ȃ��肪�[�����Ƃ́A�ݗ����ʋ���^��������ɍl�����ׂ�����Ƃ��Ă�����̂ƔF�߂邱�Ƃ��ł��悤�B�����āA������Ɠ����ɓ��Ǔ��ǂɏo�������Ƒ��ɍݗ����ʋ����^�����Ă��邱�Ƃ��A��L������L���ɍl���������ʂł���ƍl������Ƃ���ł���B
�@�����ɂ��ƁA��L�̂悤�ɓK�@�ȍݗ����i�������Ȃ��O���l�������ԕ��������R�Ɖ䂪���ɍݗ����A���̊Ԃɑf�s�ɖ��Ȃ����łɑP�ǂȈ�s���Ƃ��Đ����̊�Ղ�z���Ă��邱�Ƃ��A���Y�O���l�ɍݗ����ʋ���^��������ɍl�����ׂ����̎��R�ł��邱�Ƃ́A�{���������܂łɖَ��I�ɂ��������m��������ł������ƔF�߂���̂ł���A�{�������́A������������肩�A�ނ���t�̌��_�����R�Ƃ��čl�����Ă���̂ł����āA���̂悤�Ȏ戵���𐳓���������i�̎�����������炸�A�������A���ꂪ������ɍł��L���Ȏ��R�ƍl������̂ł��邩��A���R�l�����ׂ����R���l�����Ȃ��������Ƃɂ��A���̔��f�����E���ꂽ���̂ƔF�߂���Ȃ��i���̂悤�ȏꍇ�ɁA���̓_��K�ɍl�������Ƃ��Ă��A���̎���Ƒ����l�������Ƃ��邱�Ƃɂ��A���Y�������q�ϓI�ɂ͓K�@�Ȃ��̂ƕ]��������ꍇ�����蓾��Ƃ���ł͂��邪�A���̂悤�Ȏ���͏����̓K�@�����咣����퍐��ɂ����āA�\���I�ɂ���咣�E�����ׂ����̂ł����āA�퍐�炪���̂悤�Ȏ咣�������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ٔ����Ƃ��ẮA����ϋɓI�ɂ����̓_��R�����f���邱�Ƃ͂ł����A���Y�������������āA�ēx���f������ق��Ȃ��B�j�B
(��)�@�ȏ�ɂ��ƁA�{���e�����́A��L�̎����̕]����������_�݂̂��炵�Ă��A�ٗʌ�����E���͗��p���Ă��ꂽ���̂Ƃ��Ď��������ׂ����̂ł��邪�A�퍐�炪�{�������̑������ɂ��ϋɓI�Ɏ咣���Ă���Q�̎��R�ɂ��Ă��A���̔��f���e�ɎЉ�ʔO�㒘�����s�����ȓ_������A�����̓_�͖{���e�ޗߔ��t�����̑���������b�t������̂Ƃ͍l����̂ŁA�O�̂��߁A���y�т��Ő�������ƂƂ��ɁA�{���e�ޗߔ��t�����́A��ጴ���̊ϓ_��������F�ł��Ȃ����Ƃ����ɂ����Đ�������B
�@�Ȃ��A�퍐��́A���a�T�S�N�̍ō��ٔ��������p���Ď咣���Ă��邪�A����������L�������O���l�ɗL���Ȏ���Ƃ��čl�����邱�Ƃ�ے肵�Ă�����̂ł͂Ȃ��Ɖ����ׂ��ł��邵�A���ɂ����łȂ��Ƃ��Ă��A���̔�����ɖَ��I�ɂ���ٗʊ���m�����Ă���ȏ�A���̔����͏�L�̔��f�ɉe�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ��B
���@�{���ɋA�������ꍇ�̌�����̐���
�@�퍐��́A�����v�y�ь����Ȃ̐e�Z�킪�{���C�����ɍݏZ���Ă��邱�ƁA�y�ь����v���`�̎����{���ɂ����čw�����Ă��邱�Ƃ̂Q�_�������Ƃ��Č����炪�{���ɋA�����Ă������Ɏx��͂Ȃ��Ǝ咣���Ă���B
�@�������A�����v�y�ь����Ȃ̐e�Z��̐E�Ƃ�������͖��炩�łȂ��A�A������������ɂǂ̒��x�����������邩�����炩�ł͂Ȃ��B�܂��A������݂��邱�Ƃ��瓖�ʋ��Z����ꏊ���m�ۂ�����Ɣ퍐��͔��f�����Ǝv���邪�A�����炪������r�ɂ��Ă͉���l���������Ă��炸�A�����炪���i�̋Z�\��L������̂ł��Ȃ��A�����v���{���������R�V�˂ł���A�P�O�N�߂����{���𗣂�Ă������ƁA�{���ɂ����Ă͎��Ɨ���������Ԃ������Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�ނ���A�����炪�{���ɋA�������ꍇ�ɂ́A���̐����ɂ͑����ȍ��������Ɨ\������̂��ʏ�l�̏펯�ɂ��Ȃ����̂ƔF�߂���B
�@��������ƁA�퍐��̏�L�w�E�́A�\���ȍ����Ɋ�Â��Ȃ��ƒf�ƕ]����������A�{�������̑���������b�t������̂Ƃ͍l����B
���@�A���ɂ�錴�������y�ь��������ւ̉e��
�@�퍐��́A�����q�炪�����Y���ɕx�ޔN��ł��邱�Ƃ������ɗ��e�ƂƂ��ɋA�����邱�Ƃ����̕������͍őP�̗��v�ɓK���Ǝ咣����B
�@�������A�퍐��̏�L�咣�̍����͋ɂ߂Ē��ۓI�Ȃ��̂ŁA�䂪���ŗc������߂����������q�炪�A����A�����y�яK����S���قɂ���C�����ɋA�������ꍇ�ɁA�ǂ̂悤�ȉe�����邩�ɂ��ċ�̓I���^���Ɍ����������̂Ƃ͓��ꂤ�������Ȃ��B���ɁA�䂪���ƃC�����Ƃɂ����鏗���̒n�ʂɂ́A�O�L�F��̂悤�ɒ��������ق�����A�C�����̏������@�������������j������������n�ʂɂ�����Ă��邱�Ƃ�ς�����̂́A�@�����瓙�ɂ��c�������炻�����ނȂ����̂Ƃ��Ď���Ă��邱�Ƃɂ��Ƃ��낪�傫���ƍl������̂ł���B����ɑ��A�����q��A���Ɍ��������́A�{�����������P�Q�˂ł���A���̔N��܂ň�т��ĉ䂪���Љ�ɂ����Ēj�q�ƑΓ��̐����𑱂��Ă����̂ł��邩��A�{���ɋA�������ۂɂ́A�����Ȑ��_�I�Ռ����A�ꍇ�ɂ���Ă͐��U���₷���Ƃ̍���Ȑ��_�I��ɂ��邱�Ƃ����蓾��ƍl����̂��A�ʏ�l�̏펯�ɓK�����̂ƔF�߂���B
�@��������ƁA�퍐��̏�L�咣���\���ȍ����Ɋ�Â��Ȃ��ƒf�ƕ]����������A�{�������̑���������b�t������̂Ƃ͍l����B
���@��ጴ���ᔽ
�@�@�́A�{�@�ɓ������A���͖{�@����o�����邷�ׂĂ̐l�̏o�����̌����ȊǗ���}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă�����̂ł���A�ދ������ߏ����A�����R�����̑ދ��������R�Y���̔F��ɕ������i�����R���̐��������Ȃ��|�L�ڂ��������ɏ��������j�ҁi�S�V���S���j�A�����R���ɂ����ē����R�����̂����F��Ɍ�肪�Ȃ��|�̓��ʐR�����̔���ɕ������ҁi�S�W���W���j�A�@����b�ɂ��@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��|�ٌ̍������ҁi�S�X���T���j�Ɍ����Ĕ��t����A�ދ��������R�ɊY������҂̑��҂��s���̂ɕs���Ȃ��̂ł��邱�Ƃɂ��݂�A�ދ������ߏ��̔��t�����́A�@���ړI�Ƃ���o�����̌����ȊǗ��̂��߂ɏd�v�Ȗ����������Ă�����̂ł���ƔF�߂��A�{���e�ދ������ߏ����t�������s���A�����ďo�����Ǘ��̓K����}��K�v��������Ƃ������ʂ͔ے肵���Ȃ��B
�@�������A������Ƒ��́A���{�ł́A�ݗ����i���Ȃ��ꂵ���̒��A�Ƒ��S�l�ł̐����̊�Ղ�z�������̂ł���A���̊�Ղ́A�ݗ����i���邱�Ƃɂ�肳��ɋ��łɂȂ邱�Ƃ��\������A�����̂₱��܂ł̋Ζ�����A�ݗ����i���邱�Ƃ������ɁA�����������A�����Ɏx������̐����z����Ă���B�܂��A���l��́A�@�ᔽ�ȊO�ɉ���̔ƍߓ����s�������Ƃ͂Ȃ��A�Љ�ɂ��ϋɓI�ɂƂ�����ł���Ƃ�����B�܂��A�����v�̍ݗ����Ԃ́A�������Ŗ�P�O�N�A���݂Ŗ�P�R�N�ƁA�{�M�ɒ����ݗ����Ă���ƕ]����������ԂɒB���Ă����A������Ƒ��́A�q������������w��ɒB���A�܂��A�ݗ����i��L���Ȃ����Ƃɂ��s���v���������Ƃ���A�Y���A��ނɂ�܂ꂸ����s�@�c�����������Ȑ\���������̂ł���A�O�L(2)���ɂ��A�����̎���́A�����̍ݗ����i�t�^�ɂƂ��ėL���Ȏ���Ƃ����ׂ��ł���B
�@�܂��A�O�L�F��̎����ɂ��A������Ƒ��́A�����v���������Ԏ��e����A���̌���{�i���W�����Ƃ̎�������邽�߁A���݁A�����v�̃A���o�C�g�ł̏\�����~�Ƃ��������ł̉Ƒ��S�l�̐������ێ�������Ȃ��ɂ��邽�߁A�C�����֑��҂����Ɠ����̔�p���܂��Ȃ������̒~�����Ȃ����Ƃ͗e�Ղɐ��F�ł���B�܂��A�C�����̈�ʓI�Ȍo�Ϗ⌴�����P�O�N�ȏ�C�����𗣂�Ă������Ɠ��ɂ��݂�A�����v�ɐE��������\���͒Ⴍ�A������́A�C���������ɗL���Ă�������������v�̎��e���̐�����ɏ[�Ă邽�߂ɔ��p�������Ƃ���i�b�P�U�j�A���Z�p�̕s���Y�����L���Ă��炸�A�܂��A�����v�̌Z��ɂ��x���̉\���͔ے肵���Ȃ����̂́A���̐���������݂�Α����̎x���͊��҂ł��Ȃ��Ƃ݂�̂����R�ł���A�A�������ۂɂ́A�����ɉƑ��S�l���H���ɖ����W�R��������Ƃ�����B
�@���ɁA�Q�̂Ƃ��ɗ������A�P�O�N�ȏ����{�ʼn߂��������������́A��L�̂Ƃ���A���̐����l����v�l�ߒ��A����������S�ɓ��{�l�Ɠ������Ă�����̂ł���A�C�����̐����l���������{�̐����l�����ƒ������������Ă��邱�Ƃ��l������A����͒P�ɕ����̈Ⴂ�ɋꂵ�ނƂ��������x�̂��̂ɂƂǂ܂炸�A���������̂���܂Œz���グ�Ă����l�i�≿�l�ϓ������ꂩ�畢�����̂Ƃ����ׂ��ł���A����́A�{�l�̓w�͂���͂̋��͓��݂̂ō������������̂ł͂Ȃ����Ƃ��e�Ղɐ��F�����B���������́A���݁A���{�̒��w�ŕw�ɗ�݁A���{�̐��k�Ƒ��F�̂Ȃ����т��C�߂Ă��邪�A�C�����ɋA�������ꍇ�ɂ́A�݊w���ێ����邱�Ƃɂ��瑊���ȍ�������A�A�E���ɍۂ��Ă��A���{�Ŕ|��ꂽ���l�ς��}�C�i�X�ɍ�p���邱�Ƃ��\���l������B
���������ɂ��ẮA�����������͔N���ł���A���ΓI�ɂ͓K���̉\���������Ƃ݂邱�Ƃ��ł���ł��낤���A���ꂪ�e�ՂłȂ����Ƃ����炩�Ƃ����ׂ��ł���B���̓_�ɂ����āA�f�ؐl�̓��{�Ő��܂ꂽ����{�ň�����C�X�������k�̎q�����A�C�X�����ɋA��Ƃ������Ƃ͎��˂ƌ����ɓ������Ƃ�����|�̏،��́A�\���X���ɒl������̂Ƃ����ׂ��ł���B�O�L�̎q�ǂ��̌������R���̓��e�ɂ��݂�A���̓_�́A�ދ������ߏ��̔��t�ɓ�����d�������ׂ�����ł���Ƃ�����B
�@�ȏ�ɂ��A�ދ������ߏ��̔��t�y�т��̎��s�����ꂽ�ꍇ�ɂ́A������Ƒ��̐����͑傫�ȕω��������邱�Ƃ��\�z����A���Ɍ��������ɐ����镉�S�͑z����₷����̂ł���A�����̎��Ԃ́A�l���ɔ�������̂Ƃ̕]�������邱�Ƃ��\���\�ł���B
�@�����āA�O�L�̂悤�ȕs�@�ݗ��O���l�̎����̕K�v�������邱�Ƃ͊m���ł͂��邪�A�s�@�c���ȊO�ɉ���̔ƍߍs�ד������Ă��Ȃ�������Ƒ��ɂ��A�ݗ����i��^�����Ƃ��Ă��A����ɂ�萶����x��́A����̎��Ăɂ��čݗ����i��t�^������Ȃ��Ȃ邱�Ɠ��A�o�����Ǘ��S�̂Ƃ����ϓ_�ɂ����Đ�����A����Β��ۓI�Ȃ��̂Ɍ����A������Ƒ��̍ݗ����i��F�߂邱�Ƃ��̂��̂ɂ���̓I�ɐ�����x��͔F�߂��Ȃ��B���ɁA������Ɠ��l�̏����̎҂ɍݗ����ʋ���^������Ȃ����Ԃ��������Ƃ��Ă��A������̂悤�ɒ����ɂ킽���čݗ����i��L���Ȃ��܂܍ݗ����p�����A���A�P�ǂȈ�s���Ƃ��Đ����̊�Ղ�z�����Ƃ͎���̋ƂƂ����ׂ����Ƃł��邩��A���̂悤�ȏ��������҂ɍݗ����ʋ���^���邱�Ƃɂǂ�قǂ̎x�Ⴊ�����邩�ɂ͑傢�ɋ^�₪����B�{���ɂ����Ă��A������̍ݗ����i�t�^�̗v�ۂɂ��āA�ݗ����Ԃ���̈��萫�A���Ȑ\���̗L���ɉ����A�C�����ɋA�������ꍇ�ǂ̂悤�Ȏ��Ԃ��\������邩�����l��������Ō������s���Ă�����̂ł���A���̎҂ɂ��Ă�����Ɠ��l�T�d�Ȕ��f���s�����ꍇ�ɂ́A�O�L�̂悤�ȏo�����Ǘ��S�̂Ƃ����ϓ_������������x��͐����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��낤�B���̂��Ƃ́A���ɁA�O�L�����̂Ƃ���A�퍐�@����b���A�����Ɠ��i�̎���̍��ق��F�߂��Ȃ��Ƒ��ɂ��āA�ݗ����ʋ����s���Ă���Ƃ��납�炵�Ă����炩�ł���B
�@�ȏ�ɂ��A������Ƒ����钘�����s���v�Ƃ̔�r�t�ʂɂ����āA�{�������ɂ��B������闘�v�͌����đ傫�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�{���e�ދ������ߏ����t�����́A��ጴ���ɔ�������@�Ȃ��̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̂悤�Ȍ����ɒ������s���v�������邱�Ƃ��\�������̒��A������ɂ��̂悤�ȕs���v���Î�Ƃ����ɂ́A�퍐���咣����悤�ɁA�s�@�ȍݗ��̌p���͈�@��Ԃ̌p���ɂق��Ȃ炸�A���ꂪ�����ԕ����Ɍp�����ꂽ����Ƃ����Ē����ɖ@�I�ی����؍����̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ̍l�����ɋ���ق��Ȃ����A���̂悤�ȍl���������p�ł��Ȃ����Ƃ͑O�L���ɐ��������Ƃ���ł���B�܂��A�ݗ����ʋ��̐��x�́A�ދ��������R�����݂���O���l�ɑ��A�ݗ����i��t�^���鐧�x�ł���A���̑ދ��������R����s�@�c����s�@���������O����Ă��邱�ƂȂǂ͂Ȃ��̂ł��邩��A�@�́A�s�@������s�@�c���̎҂ł����Ă��A���̎������ꍇ�ɂ͍ݗ����i��t�^���邱�Ƃ�\�肵�Ă�����̂Ƃ݂邱�Ƃ��ł��A�P���ɁA�s�@�ݗ��҂̖{�M�ł̐�������@��Ԃ̌p���ɂ����Ȃ��Ƃ��Ă����ی삳��Ȃ����̂Ƃ���̂͂��܂�Ɉ�ʓI�ł���A���Y�O���l�ɍ��Ȃ��̂ł���Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�ݗ����i��L���Ȃ����Ƃɂ�鑽���̕s���v�̒��A���Ȃ�Ƒ��̐����̈ێ��ɓw�߂Ȃ���A�A�����Ȃ���Ƃ����v���Ɩ{�M�ł̐����Ɋ��S�ɂƂ����݂Ȃ��琬�����Ă����q���̐������̋��ԂŒ����Ԃɂ킽�莩��̏�ԓ��ɔY�݂Ȃ��琶�����Ă��������v�y�эȂ̐S���͎@����ɂ��܂肠����̂ł���A���l��Ƃ��Ă���@��Ԃ�F�����Ȃ����������̕��@���̂蓾�Ȃ������Ƃ����̂������ȂƂ���ł���Ǝv����B����V�X���̂P�A�Q�A��X�O���̂P�A�Q�A��X�P���̂P�A�Q�ɂ��A���Ǔ��ǂƂ��Ă��s�@�؍݊O���l�̎���蓙���\�Ȍ���s���Ă��邱�Ƃ͔F�߂��邪�A�{���Ɍ����Ă݂Ă��O���l�o�^�̍ۂ⏬�w�Z�E���w�Z�ւ̓��w���ȂǁA�����炪���I�@�ւƐڐG�������Ă�����Ԃ͑�������A���̂悤�ȏ�ʂł̎���肪���x�����Ă��炸�A����肪�s���Ȃ��������ƂŒ����������ݗ��ɂ��āA���̔�����ׂČ����ɕ��킹��Ƃ����͖̂���������ƍl������B
(3)�@����
�@�ȏ�ɂ��A�{���e�ޗߔ��t�����́A�O�L(2)���̂Ƃ���A���Ɋm�������ٗʊ�ɂ����Č�����ɗL���ɍl�����ׂ��ŏd�v�̎��R�Ƃ���Ă��鎖�����A������ɗL���ɍl�����Ȃ����肩�A�t�ɕs���v�ɍl�����Č��_���Ă���_�ɂ����āA�ٗʌ��̈�E���͗��p������̂ł��邵�A�O�L(2)���y�т��Ƃ��肻�̑������̍����Ƃ��ĐϋɓI�Ɏ咣���ꂽ�_�́A��������\���ȍ����Ɋ�Â��Ȃ��ƒf�Ƃ��킴��Ȃ�����A���̑���������b�t���鎖�R���F�肷�邱�Ƃ��ł����A�������A�O�L(2)���̂Ƃ���A��ጴ���ɂ���������̂ł��邩��A������������ׂ����̂�
����ق��Ȃ��B
��T�@���_
�@�ȏ�ɂ��A������̔퍐�@����b�ɑ���i���͕s�K�@�ł��邩�炱����p�����邱�ƂƂ��A������̔퍐��C�R�����ɑ��鐿���͂���������R�����邩�炱���F�e���邱�ƂƂ��A�i�ה�p�̕��S�ɂ��A�퍐�@����b�͖{�i�ɂ����ď��i���Ă�����̂́A�퍐��C�R�����̖{�������������I�ɂ͎��O�Ɍ��ق��Ă�����̂Ƃ݂�ׂ����Ƃ��l�����A�s�������i�ז@�V���A�����i�ז@�U�P���A�U�Q���A�U�S�����������A�U�T����K�p���A�啶�̂Ƃ��蔻������B
������R��
�@�i�ٔ����ٔ����@���R��s�@�ٔ����@�A�V�@�@�ٔ����e�r�͂́A�]���̂��ߏ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ٔ����ٔ����@���R��s�j
- �����n���ٔ���
�����P�Q�N�i�s�E�j��Q�P�P��
�����P�T�N�O�X���P�X��
�啶
�P�@�퍐���������Ǘ��ǎ�C�R�����������P�Q�N�U���R�O���t���Ō����`�A���a�A���b�y�ѓ��c�ɑ��Ă����e�ދ������ߏ����t��������������������B
�Q�@������̔퍐�@����b�ɑ���e�i������������p������B
�R�@�i�ה�p�͔퍐��̕��S�Ƃ���B
�����y�ї��R
��P�@����
�P�@�啶��P�����|
�Q�@�퍐�@����b�������P�Q�N�U���R�O���t���Ō����`�A���a�A���b�y�ѓ��c�ɑ��Ă����A�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�S�X���P���Ɋ�Â��e�����ً̈c�\���o�͗��R���Ȃ��|�̊e�ٌ�����������������B
��Q�@���Ă̊T�v
�P�@���Ă̗v�|
�@�{���́A��������C�����E�C�X�������a���̍��Ђ�L���A�ݗ����Ԃ�k�߂��Ė{�M�ɂ�����ݗ��𑱂��邱�ƂƂȂ��������`�i�ȉ��u�����v�v�Ƃ����B�j�A���̍Ȃł��錴���a�i�ȉ��u�����ȁv�Ƃ����j�A���̎q�ł��錴���b�i�ȉ��u���������v�Ƃ����B�j�y�ь����c�i�ȉ��u���������v�Ƃ����B�j���A�퍐�@����b�������P�Q�N�U���R�O���Ɍ�����ɑ��Ă����o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�S�X���P���Ɋ�Â��e�����ً̈c�\���o�͗��R���Ȃ��|�̊e�ٌ��i�ȉ��u�{���e�ٌ��v�Ƃ����B�j�y�є퍐��C�R�����������ɍs�����e�ދ������ߏ����t�����i�ȉ��u�{���e�ޗߔ��t�����v�Ƃ����B�j�͂��������@�ł���Ƃ��Ă��̎���������߂���̂ł���B
�Q�@���f�̑O��ƂȂ鎖���i�F�荪�����f�L���Ȃ������͓����ҊԂɑ������Ȃ��B�j
(1)�@������
�@�����v�́A�P�X�U�R�N�W���Q�R�����܂�̃C�����E�C�X�������a���i�ȉ��A�P�Ɂu�C�����v�Ƃ����B�j���Ђ�L����j���ł���A�����ȂƂ����B�j�́A�P�X�U�U�N�P�Q���Q�Q�����܂�̓������Ђ�L���鏗���ł����āA���l�́A�v�w�ł���B���������i�P�X�W�W�N�T���V�����܂�j�y�ь��������i�P�X�X�U�N�X���X�����܂�j�́A������������v�ƌ����Ȃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�����ł���A�������Ђ�L����҂ł���B
(2)�@������̓����y�эݗ��̌o��
�A�@�����v�́A�����Q�N�T���Q�P���A�C�����̃e�w��������C�����q��@�Ő��c��`�ɓ������A�������ǐ��c�x�Ǔ����R�����ɑ��A�O���l�����L�^�̓n�q�ړI�̗��Ɂu�a�����������������v���ƁA���{�؍ݗ\����Ԃ̗��Ɂu�X�c�`�x�r�v�ƋL�ڂ��ď㗤�\�����s���A�������R��������o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i�������N�@����V�X���ɂ������O�̂��́B�ȉ��u���@�v�Ƃ����B�j�S���P���S���ɒ�߂�ݗ����i�y�эݗ����ԂX�O���̋����A�{�M�ɏ㗤�����B
�@�����v�́A�ݗ����i�̕ύX���͍ݗ����Ԃ̍X�V�̋��\�����s�����ƂȂ��A�ݗ������ł��镽���Q�N�W���P�X�����Ė{�M�ɕs�@�c��������Ɏ������B
�C�@�����Ȃ́A�����R�N�S���Q�U���A���������ƂƂ��ɃV���K�|�[������V���K�|�[���q��@�Ő��c��`�ɓ������A�������ǐ��c�x�ǐR�����ɑ��A�O���l�����L�^�̓n�q�ړI�̗��Ɂu�s�n�t�q�h�r�s�v�A���{�؍ݗ\����Ԃ̗��Ɂu�n�m�d�@�v�d�d�j�v�ƋL�ڂ��ď㗤�\�����s���A���ꂼ�ꓯ�����R��������o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j�ʕ\�P�ɋK�肷��ݗ����i�u�Z���؍݁v�y�эݗ����ԂX�O���̋����A�{�M�ɏ㗤�����B
�@�����ȋy�ь��������́A�ݗ����i�̕ύX���͍ݗ����Ԃ̍X�V�̋��\�����s�����ƂȂ��A�ݗ������ł��镽���R�N�V���Q�T�����Ė{�M�ɕs�@�c������Ɏ������B
�E�@�����ȋy�ь��������́A�����U�N�P���T���ɁA��ʌ��{���s���ɑ��A���Z�n����ʌ��{���s�����|���|���Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â��V�K�o�^�\�����s���A���N�P���Q�S���A�O���l�o�^�ؖ����̌�t�����B
�@�����v�́A�����V�N�S���P�P���ɍ�ʌ��{���s���ɑ��A���Z�n����ʌ��{���s�����|���|���Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â��V�K�o�^�\�����s���A���N�T���P�V���O���l�o�^�ؖ����̌�t�����B
�G�@���������́A�����W�N�X���X���A�Q�n�������s���݂̍��ݎY�w�l�ȏ����Ȉ�@�ɂ����āA�����v�y�ь����Ȃ̊Ԃɏo���������A�ݗ����i�̎擾�̐\�����s�����ƂȂ��o������U�O�����o�߂��������W�N�P�P���W�����Ė{�M�ɍݗ����A�s�@�c������Ɏ������B
�I�@���������́A�����X�N�T���Q�Q���ɌQ�n�������s���ɑ��A���Z�n���Q�n�������s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â��V�K�o�^�\�����s���A�����A�O���l�o�^�ؖ����̌�t�����B
�J�@�����Ȃ́A�����W�N�P�O���R�P���A�Q�n�������s���ɑ��A���Z�n���s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â����Z�n�ύX�o�^�������i���Q�O�j�B
�L�@�����v�́A�����P�P�N�P���P�R���y�ѓ��N�P�P���P�V���ɁA��ʌ��{���s���y�ьQ�n�������s���ɑ��A���Z�n�����ꂼ���ʌ��{���s�����|���|���y�ьQ�n�������s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â����Z�n�ύX�o�^�������B
�@���������́A�����P�P�N�P�P���Q�T���A�Q�n�������s���ɑ��A���Z�n���s�����Ƃ��āA�O���l�o�^�@�Ɋ�Â����Z�n�ύX�o�^�������i���R�W�j�B
(3)�@������̑ދ������葱�̌o��
�A�@������́A�����P�P�N�P�Q���Q�V���A�������Ǒ�Q���ɂɏo�����A�s�@�c�������ɂ��Đ\�������B
�C�@�������Ǔ����x�����́A�����P�Q�N�P���Q�V�������v�y�ь����Ȃɂ��āA���N�Q���P�T�������Ȃɂ��Ĉᔽ���������{�������ʁA�����炪�@�Q�S���S�����i�s�@�c���j�ɊY������Ƌ^���ɑ���鑊���̗��R������Ƃ��āA���N�Q���Q�Q���A������ɂ��A�퍐��C�R����������e�ߏ��̔��t���A�����Q�S���A���ߏ������s���āA������𓌋����ǎ��e��Ɏ��e���A�����v�y�эȂ�@�Q�S���S�����Y���e�^�҂Ƃ��ē������Ǔ����R�����Ɉ����n�����B�퍐��C�R�����́A�����A������ɑ��A�����Ɋ�Â������Ƃ��������B
�E�@�������Ǔ����R�����́A�����P�Q�N�Q���Q�S���y�ѓ��N�R���V�������v�ɂ��Ĉᔽ�R�������A���̌��ʁA���N�R���V���A�����v���@�Q�S���S�����ɊY������|�̔F������A�����v�ɂ����ʒm�����Ƃ���A�����v�́A�����A�������Ǔ��ʐR�����ɂ������R���𐿋������B
�G�@�������Ǔ����R�����́A�����P�Q�N�Q���Q�S���y�ѓ��N�R���P�T���A�����ȁA���������y�ь��������ɂ��Ĉᔽ�R�������A���̌��ʁA���N�R���P�T���A�O�L�e�������@�Q�S���S�����ɊY������|�̔F������A�O�L�e�����ɂ����ʒm�����Ƃ���A�O�L�e�����͓����A�������Ǔ��ʐR�����ɂ������R���𐿋������B
�I�@�������Ǔ��ʐR�����́A�����P�Q�N�S���Q�S���A�����v�ɂ��āA�����R�������A���̌��ʁA�����A�����R�����̑O�L�F��͌�肪�Ȃ��|���肵�A�����v�ɂ����ʒm�����Ƃ���A�����v�́A�����A�퍐�@����b�ɑ��A�ًc�̐\�o�������B�퍐�@����b�́A�����P�Q�N�U���Q�U���A�����v����ً̈c�̐\�o�ɂ��ẮA���R���Ȃ��|�ٌ����A���ٌ��̒ʒm�����퍐��C�R�����́A���N�U���R�O���A�����v�ɓ��ٌ������m����ƂƂ��ɁA�ދ������ߏ��t�����B
�J�@�������Ǔ��ʐR�����́A�����P�Q�N�S���Q�U���A�����ȁA���������y�ь��������ɂ��Č����R�������A���̌��ʁA�����A�����R�����̑O�L�F��͌�肪�Ȃ��|���肵�A��������ɂ����ʒm�����Ƃ���A��������́A�����A�퍐�@����b�ɑ��A�ًc�̐\�o�������B�퍐�@����b�́A�����P�Q�N�U���Q�U���A�����ȁA���������y�ь�����������̊e�ًc�̐\�o�ɂ��Ă͗��R���Ȃ��|�ٌ����A���ٌ��̒ʒm�����퍐��C�R�����́A���N�U���R�O���A��������ɓ��ٌ������m����ƂƂ��ɁA���ꂼ��ɑ��ދ������ߏ��t�����B
��R�@�����҂̎咣
�P�@�퍐
(1)�@�{���e�ٌ��̓K�@���ɂ���
�A�@������̑ދ��������R
�@�����v�A�ȋy�ь����������A���ꂼ��̍ݗ����Ԃ��ĕs�@�c���������Ƌy�ь����������A�{�M�ŏo���������̂́A�ݗ����i�̎擾�̐\�����s�����ƂȂ��A�o������U�O�����o�߂��������ĕs�@�c�����Ă������Ƃ͖��炩�ł���A�����炪�ދ��������R�ɊY�����邱�Ƃ�F�߂����ʐR�����̔���ɉ�����͂Ȃ��B
�C�@�ݗ����ʋ��ɌW��@����b�̔��f�̓K�@��
(�A)�@�@����b�̍L�͂ȍٗʌ�
�@�@����b�́A�ًc�̐\�o�ɑ���ٌ��ɓ������āA�ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��ƔF�߂�ꍇ�ł��A���ʂɍݗ��������ׂ��������ƔF�߂�Ƃ��́A���̎҂̍ݗ�����ʂɋ����邱�Ƃ��ł���Ƃ���i�@�T�O���P���R���j�A���̂悤�ȍݗ����ʋ��́A�ދ��������R�ɊY�����邱�Ƃ����炩�ŁA���R�ɖ{�M����̑ދ������������ׂ��҂ɑ��A���ʂɍݗ���F�߂鏈���ł����āA���̐����́A���b�I�Ȃ��̂ł���Ƃ����ׂ��ł���B�����āA�ݗ����ʋ��̔��f������ɓ������ẮA���Y�O���l�̌l�I����݂̂Ȃ炸�A���̎��X�̍����̐����E�o�ρE�Љ�̏�����A�O�𐭍�A���Y�O���l�̖{���Ƃ̊O���W���̏��ʂ̎���𑍍��I�ɍl�����ׂ����̂ł��邱�Ƃ���A�ݗ����ʋ��ɌW��@����b�̍ٗʂ͈̔͂͋ɂ߂čL�͂Ȃ��̂ł����āA���Y�ٗʌ��̍s�g����@�ƂȂ�̂́A�@����b�����̕t�^���ꂽ�����̎�|�ɖ��炩�ɔw���čٗʌ����s�g�������̂ƔF�ߓ���悤�ȓ��ʂ̎������ꍇ���A�ɂ߂ė�O�I�ȏꍇ�Ɍ�����B
(�C)�@�{���e�ٌ��ɍٗʌ��̈�E���͗��p���Ȃ�����
�@�����v�A�����ȋy�ь��������́A�C�����ŏo���E���炵�A��������܂ʼn䂪���Ƃ͉���̂������̂Ȃ��������̂ł��������A�n�q�ړI���U���Ė{�M�ɏ㗤���A�����v�y�ь����Ȃ́A���̌�Ԃ��Ȃ��s�@�A�J���J�n���Ă���Ƃ���A�s�@�c���Ɏ������o�܂͋ɂ߂Čv��I�ł����āA�s�@�A�J���s�������Ԃ������A�o�����Ǘ��s����ʼn߂�����̂�����B�����v�y�ь����Ȃ̐e�Z��́A�C�����{���ɍݏZ���A�{���e�ٌ������ɂ́A�s�@�A�J�œ������K�Ŗ{���Ɏ���܂ōw�����Ă���̂ł����āA�����炪�C�����ɋA�������Ƃ��Ă��{���ł̐����Ɏx��͂Ȃ����̂Ƃ����ق��Ȃ��B�܂��A�����q��́A�����Y���ɕx�ޔN��ɂ���A���ɓ����͌������K���̖ʂő����̍���������邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��i���n�ł̐������o�����邱�Ƃ��������K����g�ɂ���őP�̕��@�ł���A���e�Ƃ̖{�M����̑ދ�����ނȂ����̂ł���ȏ�A���̔N��ɂ��݂�ƁA�ꍏ�������A�����]�܂��Ƃ����ׂ��ł���B�j�A���e�ƂƂ��ɋA������̂��q�̕������͍őP�̗��v�ɓK���Ƃ���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A���̐e���̍ݏZ����C�����ł̐����Ɋ���e���ނ��Ƃ͏\���ɉ\�ł���ƌ����܂��̂ł����āA������ɂ��āA�{�M�ւ̍ݗ���F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ʂȎ�����݂���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@�m���ɁA������́A�{�M�ɕs�@�Ɏc������ԂɈ��̈��肵��������Ԃ��`���������̂Ƃ����Ȃ����Ȃ����A�ō��ُ��a�T�S�N�P�O���Q�R����R���@�씻���́A��P�O�N�O�ɕs�@���������O���l�j���A��P�R�N�O�ɕs�@�������������l�����y�і{�M�ɂ����ďo�����������Ԃ̎q��Q���ɑ��A�@����b���ݗ����ʋ���^���Ȃ��������Ăɂ��āu�{�M�ɕs�@�������A���̂܂܍ݗ����p������O���l�́A�o�����Ǘ��߂X���R���̋K��ɂ�茈�肳�ꂽ�ݗ����i�������čݗ�������̂ł͂Ȃ��̂ŁA���̍ݗ��̌p���͈�@��Ԃ̌p���ɂق��Ȃ炸�A���ꂪ�����ԕ����Ɍp�����ꂽ����Ƃ����Ē����ɖ@�I�ی����؍����̂��̂ł͂Ȃ��v�Ɣ������Ă���A����́A�{���ɂ����Ă����Ă͂܂���̂Ƃ�����B���������s�@�c���́A�����̑ΏۂƂȂ��@�s�ׂł���A�����v�y�ь����Ȃ��{�M�ɂ����Ē����ԕs�@�A�J�������s�����Ƃ��������́A��@�s�ׂ������Ԃɋy���Ƃ��Ӗ�������̂ł��邩��A�퍐�@����b��������̍ݗ����ʋ��̉ۂf�����ŁA���Y������L���Ȏ���Ɖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͂Ȃ��̂ł���A�ނ���A�����ɂ킽��s�@�c��������s�@�A�J���������ݗ����ʋ��̔��f�ɂ����ď��ɓI�v�f�Ƃ��ĕ]�������ׂ����̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ȏ�������l������A�@����b���{���e�ٌ��ɓ������ĕt�^���ꂽ�����̎�|�ɖ��炩�ɔw���čٗʌ����s�g�������̂ƔF�ߓ���悤�ȓ��ʂ̎�����݂���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
(�E)�@�����̎咣�ɑ��锽�_
���@������̏o�g���ł���C�����̋���╟�����ɌW����݂Ă��A�����̐������i�̖�肪����ƔF�߂�ꂸ�A�����q��𑗊҂��邱�Ƃ��ݗ����ʋ��̌�����@����b�ɔF�߂���|�ɔ������l���I�Ȃ��̂ł���Ƃ���������͉��瑶���Ȃ����肩�A�C�����Ɏ�����w�����������܂ł́A�C�����ɋA������ӎv��L���Ă������A�������w�Z�Q�N���ł����������������A����������Ȃ��������߁A���̂܂ܕs�@�c�����p������Ɏ������|���q���Ă���A�A����O��Ƃ��������v�����Ă����Ƃ����ׂ��ł���B
���@���ۘA���́A�����Q�N�P�Q���P�W���u���ׂĂ̈ڏZ�J���҂Ƃ��̉Ƒ��\�����̌����ی�Ɋւ��鍑�ۏ��v���̑����A���̂R�O���́A�ڏZ�J���҂̎q�������w�Z�ŋ�����錠����L���邱�Ƃ��߁A���̂悤�Ȍ����́A�ڏZ�J���҂ł��闼�e���͂��̑؍݂��K�@�łȂ����Ƃ𗝗R�ɋ��ۖ��͐�������Ȃ��|�̋K��������Ă��邪�A�����ɂ��Ă͎��ꍑ���̌��O�������A�̑�����P�O�N�ȏ�o�߂��������P�S�N���ɂ����Ă��A������y�����Q�O�J���ɒB���Ă��Ȃ����ߌ��͂̔����ɂ������Ă��炸�A�������A���̂悤�ȏ��ł����A��L�R�O���̂悤�ȋK��͕s�@�ɑ؍݂��邱�̍ݗ��̓K�@���Ɋւ��錠�����܂ނ��̂Ɖ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���̂ł��邩��i�����R�T���j�A���ۓI�ɂ��s�@�A�J�҂̎q����������̍��ɂ����ċ�����闘�v�Ă���Ƃ��Ă��A������̍�������𗝗R�ɓ��Y�s�@�A�J�ҋy�т��̎q���̍ݗ���K�@�����ׂ��ł���ȂǂƂ������ӂ�����Ă�������݂��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
���@�C�X�����Љ�ɂ����Ă��A�j���̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A�����̐���؏��i��������j���C�X�������k�̋`���Ƃ��錩���͂��������ł���A��������͖k���A�t���J�A���A�t���J�A�A���r�A������}���[�V�A�̈ꕔ�ȂǂɌ��肳�ꂽ�K���ł���Ƃ���A�C�����̍�����Ɋւ���p���ږ��ǂ̕��́A�u�����̋s�҂ɂ��Ēm��ꂽ�ތ^�͂Ȃ��v�Ƃ��A��������ɂ��ĉ���G��Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�C�����ɂ����ď������炪�@�I���͎Љ�I�ɋ`���Ƃ���Ă��������Ƃ͔F�ߓ�B
���@������Ɠ��l�A�o���\���������w���������q��L����s�@�c���O���l�̉Ƒ��ɂ��čݗ����ʋ������ꂽ��͂��邪�A�����A������ƂƂ��ɁA�����P�P�N�P�Q���Q�V���ɓ������ǂɏo���\�������s�@�c�����̃C�����l�T�Ƒ��ɂ��Ă͌�������܂ނS�Ƒ����ݗ����ʋ����邱�ƂȂ��ދ������ߏ����t�������Ă���B
�@���������A�ݗ����ʋ��͏��ʂ̎���𑍍��I�ɍl��������ŌʓI�Ɍ��肳���ׂ����b�I�[�u�ł����āA���̋��ۂ��S������s�����Ȃ�����`�I�A�Œ�I��Ȃ���̂͑��݂��Ȃ��̂ł����āA�{���e�ٌ�����@�ɂȂ�Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A���ɁA�{���e�ٌ��������ɔ�������̂ł���Ƃ��Ă��A�O�L(�A)�̍ٗʂ̖{���������ɂ���ĕύX�������̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ��ē��s���̖�肪������ɂ����Ȃ��B
���@�s�@�c���҂𒆐S�Ƃ���s�@�A�J�҂��䂪���ɑ������݂���͎̂����ł��邪�A����͑����̕s�@�A�J�҂��V���ɔ����������Ă��錋�ʂł����āA�s�@�A�J�������䂪���̎Љ�ɗe�F����Ă��邩��ł��Ȃ���A���i�Ȏ���肪�s���Ă��Ȃ�����ł��Ȃ��B������̋��Z�n�ł���Q�n���ł��s�@�A�J�������e�F����Ă���ȂǂƂ��������͂Ȃ��A�����P�Q�N�̌Q�n���c��ɂ����Ắu��ʂ̕s�@�؍ݎ҂����݂���Ƃ������Ƃ́A�����O���l�ɂ��ƍ߂̉����ƂȂ��Ă���B�v�u�����Ǘ��ǂƂ̍��������Ƃ������Ƃɏd�_��u���āv����Ƃ��āA�����P�P�N�ɂ͂S�P�l���P�Q�N�ɂ͂P�P�����܂łɂR�U�U�l��E�����ĕs�@�؍ݎ҂̒蒅���̑j�~�ƌ�����}���Ă��邱�Ƃ�����Ă���A�����P�Q�N�ɑS���Ōx�@�Ɍ������ꂽ�@�ᔽ�҂͂T�W�U�Q�l�ł���B�Q�n���ɂ����Ė@�ᔽ�҂̓E�����ϋɓI�ɍs���Ă��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�܂��A�����P�Q�N�ɑދ������葱���̂����s�@�A�J�҂S���S�P�X�O�l���A�Q�n���ʼnғ����Ă������̂͂P�V�U�X�l�A�����P�R�N�ɑދ������葱���̂����s�@�A�J�҂R���R�T�O�W�l���A�Q�n���ʼnғ����Ă����҂͂P�S�S�W�l�ƂȂ��Ă���A��������S���s���{�����W�ʂƂȂ��Ă���B����ɁA�����P�S�N�P�P���ɑS���̒n�������Ǘ��������s�����@�ᔽ�O���l�̈�ēE���ɂ����ēE�����ꂽ�@�ᔽ�҂W�T�T�����A�Q�n���œE�����ꂽ�҂͂T�W���ł���A����́A���A�����A��ʂɂ��đS���s���{�����S�ʂƂ����������ʂƂȂ��Ă���̂ł���A������ƁE���Ƃ𒆐S�Ɂu�P���J���ҁv��]�ސ��������A���{���{�͌��i�Ȍ`�ŊO���l�J���҂ɂ��s�@�A�J�̎������s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
(�G)�@�ȏ�̂Ƃ���A�@����b���{���e�ٌ��ɓ������ĕt�^���ꂽ�����̎�|�ɖ��炩�ɔw���čٗʌ����s�g�������̂ƔF�߂���悤�ȓ��ʂ̎�����݂���Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�{���e�ٌ��ɉ���̈�@���͂Ȃ��B
(2)�@�{���e�ޗߔ��t�����̓K�@���ɂ���
�@�ދ������葱�ɂ����āA�@����b����u�ًc�̐\�o�͗��R���Ȃ��v�Ƃٌ̍��������|�̒ʒm�����ꍇ�A��C�R�����́A�ދ������ߏ��t����ɂ��ٗʂ̗]�n�͂Ȃ�����A�{���e�ٌ�����@�ł���Ƃ����Ȃ��ȏ�A�{���e�ޗߔ��t�������K�@�ł���B
�@�ݗ����ʋ��̔��f������ɓ������ẮA���Y�O���l�̌l�I����݂̂Ȃ炸�A���̎��X�̍����̐����E�o�ρE�Љ�̏�����A�O�𐭍�A���Y�O���l�̖{���Ƃ̊O���W���̏��ʂ̎���𑍍��I�ɍl�����ׂ����̂ł��邱�Ƃ͑O�L�̂Ƃ���ł��邩��A�@����b����u�ًc�̐\�o�͗��R���Ȃ��v�Ƃٌ̍��������|�̒ʒm������C�R�����́A���@���킷�邱�ƂȂ��A���₩�ɑދ������ߏ����t���������Ȃ���Ȃ炸�A�����ł��邩�炱���A�@�S�X���T�����u���݂₩�ɓ��Y�e�^�҂ɑ��v�E�E�E�u�ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����̂ł����āA�ދ������ߏ��̔��t�����ɂ��Ď�C�R�����ɍٗʌ�������Ƃ͂����Ȃ��B
�@�@�́A�@����b���ݗ����ʋ��̌������s�g���邩�ۂ��̔��f���s���ߒ��ɂ����Ă̂݁A�ދ��������R�ɊY������O���l�̍ݗ����O�I�ɔF�߂�ٗʂ�F�߂Ă���A�ًc�̐\�o�����@����b���A�ݗ����ʋ��Ɋւ��錠���������A�ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��Ƃٌ̍����s�����ꍇ�ɂ́A����͉䂪�������ƂƂ��ē��Y�O���l��ދ��������ׂ��Ƃ���ŏI�I�Ȉӎv������������Ƃ��Ӗ�������̂ł����āA�㋉�s���@�ւł���@����b�̈ӎv�����b�̎w���ē��鉺���s���@�ւł����C�R�������A���̓Ǝ��̔��f�Ɋ�Â��ĕ����A���邢�͂��̓K�p�������l���ł���Ƃ��邱�Ƃ͍s���g�D�@��̊ϓ_���炵�čl����ꂸ�A�@�����̂悤�ȗ��@������̗p���Ă���Ƃ͍l�����Ȃ��B�܂��A�@�́A�ݗ����i�̂Ȃ��O���l���{�M�ɓK�@�ɍݗ�����
���Ƃ́A�����Œ�߂�ꂽ��O�������ė\�肵�Ă��Ȃ��Ƃ���A��C�R�������ٗʂɂ��ދ������ߏ��t���Ȃ��ꍇ�ɁA���Y�O���l�����������{�M�ɍݗ����邽�߂̖@�I�n�ʂ��߂�葱�K��͑��݂��Ȃ��̂ł����āA�@�́A��C�R�����̍ٗʂɂ��ދ������ߏ��t���Ȃ��Ƃ������Ԃ�z�肵�Ă��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@���������āA��C�R�����ɑދ������ߏ��t���邩�ۂ��ɌW��ٗʌ���������|�̌�����̎咣�ɂ͗��R���Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�Q�@������
(1)�@�{���e�ٌ��̓K�@���ɂ��āi��ʓI�咣�j
�A�@�ٌ����̕s�쐬
�@�@�{�s�K���S�R���́A�u�@��S�X���R���ɋK�肷��@����b�ٌ̍��́A�ʋL��U�P���l���ɂ��ٌ����ɂ���čs�����̂Ƃ���B�v�ƒ�߂Ă���B�����́A�P�Ɍ����ōs��ꂽ�ٌ��̑��݂��m�F�E�L�^���邱�Ƃ����߂Ă���̂ł͂Ȃ��A�ٌ����ٌ����Ƃ������ʂɂ���Ă���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁA�܂�A�ٌ������ʂɂ��l���s�ׂł��邱�Ƃ��߂Ă���̂ł���B
�@�Ƃ���ƁA�ٌ������쐬����Ă��Ȃ��{���e�ٌ��ɂ͋ɂ߂ďd�傩�����Ȏ葱������r������A�{���e�ٌ��̎�����͖Ƃ�Ȃ��B
�C�@�{���e�ٌ��̍ٗʈᔽ
(�A)�@�@����b�̍ٗʌ��͈̔͂ɂ���
�@���{�����@�́A����������̍ō��@�ւƒ�߂Ă��邱�Ƃ���A���Ƃ̍ٗʂ́A���`�I�ɂ͍���ɑ�������̂Ƃ��ė��@�ٗʂɌ���邱�ƂƂȂ�B���̗��@�ٗʂ̌��ʂƂ��āA����̏ꍇ�ɂ͊O���l�ɓ����E�ݗ��������ׂ��s�����ɋ`���Â������邱�Ƃ�����A�s�����ɍٗʂ�^���A�����e�ɐ����t�����Ƃ�����B�����āA���@�̐��_��u�@���ɂ��s���̌����v���炷��A�s�����ɑS���̎��R�ٗʂ��t�^����邱�ƂȂǂ��蓾�Ȃ��̂ł����āA���̍ٗʌ����^����ꂽ�Ƃ��Ă��A���̍����ƂȂ�@���̖ړI�y�ю�|���ɂ�����J���ٗʂƂȂ�̂ł���B���̓_�A�@�́A�u�o�����̌����ȊǗ��v��ړI�Ƃ��Ă���i�P���j�A�u�o�����̌����ȊǗ��v�Ƃ́A�����̎�����J���s��̈���Ȃnj��v���тɍ��ۓI�Ȍ������A�Ó����̎����y�ь��@�A���A���ۊ��K�A�𗝓��ɂ��F�߂���O���l�̐����ȗ��v�̕ی���͂��邽�߂̊Ǘ����Ӗ�����B�@�T�O���P���̎�|���A���̌��v�ړI�ƊO���l�̐����Ȍ����E���v�̒�����}�邱�Ƃɂ���A�@����b�̍ٗʌ������̎�|�͈͓̔��ŔF�߂���ɂ����Ȃ��B
�@�퍐�̎咣�́A���̓_���ʼn߂��A���Ƃ̍ٗʌ��Ɩ@����b�̍ٗʌ��Ƃ������������̂Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�܂��A��L�̂Ƃ���A�@�̖ړI�y�і@�T�O���P���̎�|���J���������̂ł���A�@���������N�̖@�����ɂ���Ċe�ݗ����i�Ɋւ���R������ȗ߂Œ�߂Č�t���A�s���̍ٗʂ̕������������悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ł���A�ݗ����ʋ��̐��x�ɉ��b�I�Ȗʂ�����Ƃ��Ă��A��������@����b�́u�ɂ߂čL�͂ȍٗʌ��v�����������̂ł͂Ȃ��B
(�C)�@�{���ɂ�����ٗʈᔽ
���@�����v�́A�C�����ł̐������ێ�����̂�����ɂȂ�A��ނȂ������������̂ł���A�C�����͂��܂�������o�Ϗ��s����i�C���������̎��Ɨ��͂Q�T�����邱�Ƃ��m���ł���Ƃ����B�j�ł���A�������P�O�N�ȏ������Ă��������v�������ŐV���ȐE��̂͋ɂ߂č���ł���B�܂��A�����̎Љ�i�o������ł��铯���ɂ����āA�����Ȃ��E�邱�Ƃ͂���ɍ���ł����āA��������ƁA�������Ƃ͘H���ɖ������ƂƂȂ�B����ɁA���{�ŏ\���N�������������v�w���A�C�����ɋA�����ꍇ�ɃC�����̊��ɓK���ł��Ȃ��Ȃ��Ă���\��������B
�@�܂��A�C�����́A�P�X�V�X�N�̃C�X�����v���Ȍ�A�C�X�������̐��T�ł���R�[�������ō��@�K�ƂȂ�ȂǁA�C�X�����������Ƃ����䂪���Ƃ͂������ꂽ�����������A�C�X���������̒��ł����Ɍ��i�ȋK�����d�鍑�ł����āA��{�I�l���̕ۏ�ɂ����Ă��A���������݂��A���ɏ����͒j���Ɣ�r���č��ʂ��ꂽ�n�ʂɂ�����Ă���B����A���������͏o�������A�������������S�t���Ȃ��Q�˂̂Ƃ�����䂪���ɋ��Z�������A���{����g�p���A���{�̕����ɂȂ��l�i�`�����s���A�䂪���̌��@�ŕۏႳ�ꂽ�j�������A���a��`�A���R��`�Ɋ�Â�������Ă���Ƃ���ł���A����A�����K���A�������̓_�ʼn䂪���Ƃ��܂�ɂ��������ꂽ�C�����ł̐����ɂȂ��ނ��Ƃ����ɍ���ł��邱�Ƃ͖����ł���B���������́A���{���p�����w�K�ɂ��A���̋��琧�x�ɓK�����Ă��̒��ŗD�G�Ȑ��т��グ�A����ɂ͍���������邱�Ƃ�]�݁A���̏����ɂ����Ă͒ʖ̐E�ƂɏA�����Ƃ��v���`���Ă�����̂ł���A���������y�ю������C�����ɋA�������ꍇ�A��L�̂悤�ȍ���Ȏ��Ԃ������邽�߂ɁA�����������w�K���p�����邱�Ƃ͕s�\�ł���A���̂��߂Ɍ��������͐��_�I�Ɋ�@�I��Ԃɒu����A���E�̊댯�����������˂Ȃ��B
���@������̋��Z�̎��R�̐N�Q
�@�O���l�́A�䂪���ɍݗ����錠����ۏႳ�����̂ł͂Ȃ����A�O���l�ł����{���ɂ����Ă��̎匠�ɕ����Ă�����̂Ɍ����Ă͋��Z�E�ړ]�̎��R���y�Ԃ��̂Ƃ���i�ō��ُ��a�R�Q�N�U���P�X����@�씻���E�Y�W�P�P���U���P�U�U�R�Łj��̂ł��邩��A�ݗ����i��L���Ȃ��҂��A�ދ������̍������̔��f�Ȃ��ɜ��ӓI�ɏZ���̑I����W�Q����Ȃ����������@��ۏႳ��Ă���Ƃ����ׂ��ł���Ƃ���A�@����b�ɂ��{���e�ٌ��́A�����炪���{�ɐ����̊�Ղ�L���Ă��鎖�����l�������A���Z�̎��R��N�Q�����@�Ȃ��̂ł���A���̓_�ɍٗʌ��̗��p�Ȃ�����E������B
���@�����̌����Ɋւ�����i�ȉ��u�q�ǂ��̌������v�Ƃ����B�j�ᔽ
�@�q�ǂ��̌������R���́A�u�����Ɋւ��邷�ׂĂ̑[�u���̂�ɓ������ẮA���I�Ⴕ���͎��I�ȎЉ�{�݁A�ٔ����A�s�����ǖ��͗��@�@�ւ̂�����ɂ���čs������̂ł����Ă��A�����̍őP�̗��v����Ƃ��čl���������̂Ƃ���B�v�ƋK�肵�Ă��邱�Ƃ�A�O�L���̏ɂ��݂�A�䂪���ɍݗ����邱�Ƃ��u�őP�̗��v�v�ɂ��Ȃ����̂ł���A�{���e�ٌ��́A�q�ǂ��̌������R���Ɉᔽ������̂ƂȂ�B
���@������ɍݗ����i��F�߂邱�Ƃ����獑�v�Ȃ�Ȃ�����
�@���̓_�́A��L(2)�C(�C)(��)�ɋL�ڂ̂Ƃ���ł���B
���@���������ᔽ
�@������ɐ旧���A�����P�P�N�X���P�P���ɍݗ����ʋ������߂ďW�c�o�������O���l�Ƒ��̒��ɂ́A������Ɠ��l�A���w�U�N�ɍ݊w���̒����ƂT�˂̒��j���܂ރC�����l�Ƒ����܂܂�Ă���A���̉Ƒ��ɂ͕����P�Q�N�Q���ɔ퍐�@����b���ݗ����ʋ����t�^����Ă���Ƃ���A�Ƒ��\������{�ł̑؍݊��ԓ��������قړ����Ƒ��ɂ����ĈقȂ������f���������̂́A�����̌����ɔ�����Ƃ��킴��Ȃ��B
(2)�@�{���e�ޗߔ��t�����̓K�@���ɂ���
�A�@�{���e�ٌ��̈�@�����p���邱�Ƃɂ���@
�@�O�L�̂Ƃ���A�{���e�ٌ�����@�ł���ȏ�A����Ɋ�Â��Ă��ꂽ�{���ޗߔ��t��������@�Ȃ��̂Ƃ������ƂɂȂ�B
�C�@�{���e�ޗߔ��t�����Ǝ��̈�@���i�\���I�咣�j
(�A)�@�ދ������ߏ����t�������ٗʍs�ׂł��邱��
���@�@�Q�S���̋K��
�@�@�Q�S���́u���̊e���̂P�ɊY������O���l�ɂ��ẮA���͂ɋK�肷��葱�ɂ��A�{�M����̑ދ����������邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肵�A�����́A�P�ɑދ��������R������ɂ����Ȃ��Ɖ�����̂͑����łȂ��A��̓I�ȒS���s�����̌����s�g�̂�������������ɋK�肵�Ă���ƂƂ炦��ׂ��ł���B
�@�����āA�����̕������A�u���邱�Ƃ��ł���v�ƋK�肳��Ă��邱�Ƃɂ��A�ٗʂ̕��������Ȃ���̂��͂Ƃ������A�Q�S���e���ɊY������O���l�ɂ��āA�ދ������葱���J�n���ŏI�I�ɑދ����������t���邩�ɂ��ẮA���@�҂��s�����ɑ��Ĉ��̕��̌��ʍٗʂ�F�߂����̂Ƃ����ق��Ȃ��B�܂��A�{���e�ޗߔ��t�����̂悤�ɐN�Q�I�s���s�ׂł����āA����������O�҂ɑ���W�ł���v�I�ȑ��ʂ������Ȃ����̂ɂ��ẮA�ٗʂ͈͎̔��͓̂��Y�s���s�ׂ̖ړI���ɏ]���Ď����ƒ�܂�ɂ��Ă��A��L�̖@���̕������ٗʂ��������̂Ɖ����邱�Ƃɉ���x�Ⴊ�Ȃ��B
���@�s���@�̓`���I���߂���̐���
�@�s���@�̉��߂ɂ����ẮA�`���I�Ɍ��͔����v�����[������Ă���ꍇ�s�����͂�����s�g���Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ̍l�����i�s���X��`�j����ʓI�ł���A���ɁA�O���l�̏o�����Ǘ����܂ތx�@�@�̕���ɂ����ẮA��ʂɍs�����̌����s�g�̖ړI�͌����̈��S�ƒ������ێ����邱�Ƃɂ��邩��A���̌����s�g�͂�����ێ����邽�߂̕K�v�ŏ����x�ɂƂǂ܂�ׂ��ł���ƍl�����Ă���i�x�@���̌����j�Ƃ���ł���A�ދ������ߏ����t�ɂ��ĒS���s�����ɍٗʂ��^������Ƃ������Ƃ́A�`���I�ȉ��߂ɉ������̂ł���B
���@�ދ������ߏ����t�����ɂ��Ă̍ٗʂ̕K�v��
�@���ہA�ދ������ߏ��̔��t�ɍٗʌ���F�߂Ȃ��ƁA�{���y�юs�����̂��鍑�ɑ��҂��邱�Ƃ��ł����A��������O���ւ̓��������Ă��Ȃ��O���l�ȂǑދ������ߏ��t���Ă����s���s�\�ł��邱�Ƃ����炩�ȏꍇ�ɂ��A��C�R�����͑ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w������B
���@�葱�̎���
�@�@��T�͂̎葱�K�������ƁA��C�R�����̍s���ދ������ߏ��̔��t���A���Y�O���l���ދ������������ׂ����Ƃ��m�肷��s�������Ƃ��ċK�肳��Ă���i�@�S�V���S���A�S�W���W���A�S�X���T���j�A�ދ������ɂ��Ă̎��̋K��ł���@�Q�S���̔F�߂�ٗʂ́A��̓I�ɂ́A�ދ������Ɋւ����L�K�����Ď�C�R�����ɗ^�����Ă���Ƃ����ׂ��ł���B
���@���̋@�ւ̍ٗʂƂ̊W
�@�ދ������̊e�i�K�ŁA���v��u���~�����v��u���̑��v�Ƃ��������ނ�����鎖�Ă����݂���Ƃ���A�ދ������葱���J�n���ꂽ����Ƃ����āA�K�������ދ������ߏ����t�Ȃǖ@�̒�߂�I�Ǐ������s��Ȃ��Ă��悢�ꍇ������A�ᔽ�����̒i�K�A�ᔽ�R���̒i�K�A�����R���̒i�K�A�ٌ��̒i�K�Ƃ������ދ������葱�̊e�i�K�ɂ����āA���ꂼ��̒S���҂��ٗʌ���L���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�ދ������葱�ɂ����ẮA�ދ������̎��s���@��Ґ�̎w������߂čs���A�{�M����ދ����ׂ��`������̓I�Ɋm�肷����̂Ɖ������_�ŁA��A�̎葱�ɂ����Ė@���e�s�����ɑ��ė^�����ٗʂ��W�Ă�����̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����̎���ɂ��A�ދ������葱��i�s�����邩�ǂ����ɂ��ẮA���Ƃ̍ٗʌ�������A���̊e�i�K�ɂ����Ă��S���҂ɍٗʌ������邱�Ƃ���A���̍ŏI�i�K�ł���ދ������ߏ��̔��t�̒i�K�ł���C�R�����ɍٗʂ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B��C�R�����ɂ́A�ދ������ߏ��t���邩�ۂ��i���ʍٗʁj�A���t����Ƃ��Ă���������t���邩�i���̍ٗʁj�ɂ��A�ٗʂ��F�߂��Ă���A��ጴ���Ɉᔽ���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ̋K�͂��^�����Ă���̂ł���B
(�C)�@��ጴ���ᔽ
���@��ጴ��
�@��ጴ���ᔽ�́A�@�����ƌ����A��{���̕ۏᓙ�������Ƃ��錛�@��̖@�����ł���A�ߏ�ȍ��ƓI�N�Q���玄�l�̖@�v��h�䂷�邱�Ƃɂ���A�䂪���ł��A���̍����ɂ͏���������̂́A���͍s����ʂɂ��ēK�p����邱�Ƃɂ��Ă͈٘_���Ȃ��Ƃ���Ă���B��̓I�ɂ́A�K�����̌����i�ړI��B�����邽�߂̎�i���Ӑ}�����ړI�B���̌��ʂ��������邱�Ɓj�A�K�v���̌����i�ړI��B�����邽�߂̎�i�������҂ɂƂ��čł����S�̏��Ȃ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ����Ɓj�A���`�̔�ᐫ�i��i�ƖړI�Ƃ̋ύt�����Ă��邱�ƁA�v����ɁA���Y��i��p���邱�Ƃɂ���ē����闘�v�����Y��i�ɂ���đ��Ȃ��闘�v�������Ă��邱�Ɓj�������e�ƂȂ�B
���@�{���ɂ������ጴ���ᔽ
(��)�@�{���e�ޗߔ��t�����ɂ�葹�Ȃ��闘�v
�@�{���e�ޗߔ��t�����ɂ��A�O�L(1)�C(�C)���̂Ƃ���A�����炪�C�����ɋA��������Ȑ������������邱�ƁA���������E���������S�t���Ă��犵��e���䂪���̕����Ƃ͂������ꂽ�C�����ł̐������s�����ƂƂȂ邱�Ɠ��A�{���e�ޗߔ��t�����ɂ�葹�Ȃ��闘�v�͋ɂ߂đ傫���Ƃ��킴��Ȃ��B
(��)�@�{���e�ޗߔ��t�����ɂ�蓾���闘�v
�@������́A������A�{���e�ޗߔ��t�����̌����ƂȂ����@�ᔽ�ȊO�ɂ͉���@��Ƃ����Ƃ͂Ȃ��A�P�ǂȎs���Ƃ��Ēn��Љ�ɂƂ��������𑗂��Ă������̂ł���A������̖{�M�ɂ�����ݗ����i��F�߂邱�Ƃɂ��A���{�̑P�ǂȕ����E�����ɍD�e����^���邱�Ƃ�������A���e�����y�ڂ����Ƃ͑z�肵��B���Ȃ킿�A������͌`���I�ɂ͖@�ᔽ�Ƃ�����@����тт��s�ׂ��s���Ă͂�����̂́A�����I�Ȗ@�v�N�Q�ɋy�����͂Ȃ��A��������Ǘ��ǂɏo�����Ĉᔽ������\���������̂ł���A���̂悤�Ȏ҂ɍݗ����i��t�^���邱�Ǝ��̂������ɍݗ����e���x�̍�����h�邪���Ƃ͍l�����Ȃ��B�܂��A�O���l��������u�P���J���v���s���J���͂Ƃ��Ď����K�v���͍����A�A�����J�A�t�����X�A�C�^���A�Ƃ��������O�����K�؍ݎ҂̑�K�͂Ȑ��K�����s���Ă���Ƃ���ł���A������ɍݗ����i��F�߂Ȃ����Ƃɂ���ĕی삳���ׂ����̗��v�͉��瑶�݂��Ȃ��Ƃ�����B
(��)�@����
�@�ȏ�ɂ��A�{���e�ޗߔ��t�����ɂ���đ��Ȃ��闘�v�Ɠ����闘�v�Ƃ��r�t�ʂ���ƁA�O�҂̕����͂邩�ɑ傫���͖̂��炩�ł���A�{���e�ޗߔ��t�����ɂ͔�ጴ���ᔽ������Ƃ�����B
��S�@���_�y�т���Ɋւ���ٔ����̔��f
�@�{���̑��_�́A�q�P�r�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���ٌ��̏������y�ёދ������ߏ����t�����ɂ������C�R�����̍ٗʂ̑��ہA�q�Q�r�{���e�ٌ��ɂ�����ٗʌ��s�g�̗��p�E��E�̑��ہA�q�R�r�{���e�ޗߔ��t�����̈�@���̑��ۂł���B
�P�@���_�P�i�ٌ��̏������y�ёދ������ߏ����t�����ɂ������C�R�����̍ٗʂ̑��ہj
(1)�@�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���ٌ��̏�����
�A�@�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�����@����b�́A���ًc�̐\�o�ɗ��R�����邩�ǂ������ٌ����āA���̌��ʂ���C�R�����ɒʒm���Ȃ���Ȃ炸�i�@�S�X���R���j�A��C�R�����́A�@����b����ًc�̐\�o�����R����Ƃ����|�̒ʒm�����Ƃ��́A�����ɓ��Y�e�^�҂���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����Łi�����S���j�A�@����b����ًc�̐\�o�����R���Ȃ��ƍٌ������|�̒ʒm�����Ƃ��́A���₩�ɓ��Y�e�^�҂ɑ����̎|��m�点��ƂƂ��ɁA�@�T�P���̋K��ɂ��ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ���Ă���i�@�S�X���T���j�B
�@�����̋K��ɂ��A�@�́A�@����b�ɂ��ٌ��̌��ʂ́A�ًc�̐\�o�ɗ��R������ꍇ�y�ї��R���Ȃ��ꍇ�̂�����ɂ����Ă��A���Y�e�^�҂ɑ��Ăł͂Ȃ���C�R�����ɑ��Ēʒm���邱�ƂƂ��Ă����A�@����b���ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��ƍٌ������ꍇ�ɂ́A�@����b����ʒm������C�R���������Y�e�^�҂ɑ��Ă��̎|��ʒm���ׂ����ƂƂȂ��Ă��邪�A�@����b���ًc�̐\�o�ɗ��R������ƍٌ������ꍇ�ɂ́A���Y�e�^�҂ɑ����̎|�̒ʒm�����ׂ����Ƃ��K�肵�Ă��炸�A�P�Ɏ�C�R���������Y�e�^�҂���Ƃ��ׂ����Ƃ��߂�݂̂ł����āA������̏ꍇ���A�@����b�����̖��ɂ����Ĉًc�̐\�o���������Y�e�^�҂ɑ����ډ������邱�Ƃ͗\�肵�Ă��Ȃ��i�Ȃ��A�����P�R�N�@���ȗ߂V�U���ɂ�������̖@�{�s�K���S�R���Q���́A�@�S�X���T���ɋK�肷���C�R�����ɂ��e�^�҂ւ̒ʒm�́A�ʋL�U�P���̂Q�ɂ��ٌ��ʒm���ɂ���čs�����̂Ƃ���ƒ�߂Ă��邪�A���̋K��͂����܂Ŏ�C�R�������e�^�҂ɑ��Ēʒm����������߂����̂ɂ������A�@�̒�ߎ��̂ɕύX���Ȃ��ȏ�A���̋K�������������Ė@����b���e�^�҂ɒ��ډ������邱�ƂƂȂ����Ƃ͍l�����Ȃ��B�j�B���������@�̒�ߕ����炷��A�@�S�X���R���ٌ̍��́A���̈ʒu�Â��Ƃ��Ă͑ދ������葱��S������s���@�֓��̓����I���ٍs�ׂƉ�����̂������ł����āA�s�����ւ̕s���\���Ăɑ��鉞���s�ׂƂ��Ă̍s�������i�ז@�R���R���́u�ٌ��v�ɂ͓�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�C�@���̂��Ƃ́A�@�̉����̌o�܂ɏƂ炵�Ă����炩�ł���B���Ȃ킿�A�@��T�͂̒�߂�ދ������̎葱�́A�@�̑O�g�ł���o�����Ǘ��߁i���a�Q�U�N���߂R�P�X���j�̐���̍ۂɁA���̂���ɑO�g�ł���s�@�����ғ��ދ������葱�߁i���a�Q�U�N���ߑ�R�R���j�T���Ȃ����P�X���̋K�肷��葱���p�������̂ƍl�����A���葱�߂ɂ����ẮA�����R���������t�����ދ������ߏ��ɂ��Ēn���R����ɕs���\���Ă����邱�Ƃ��ł��i�X���j�A�n���R����̔���ɂ��s��������ꍇ�ɂ͒����R����ɕs���̐\���Ă����邱�Ƃ��ł��i�P�Q���j�A�����R����́A�s���̐\���Ăɗ��R�����邩�ǂ����肵�āA���̌��ʂ��o�����Ǘ��������i�ȉ��u�����v�Ƃ����B�j�ɕ��邱�ƂƂ���A���������́A�����R����̔�������F���邩�ǂ����𑬂₩�Ɍ��肵�A���̌��ʂɊ�Â��A�����̍��߂����͑ދ������ߏ��̔��t�����҂̑������ƎႵ���͑ދ������𖽂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���Ă����i�P�S���j���̂ŁA���̒����̏��F���A�@�S�X���R���ٌ̍��ɕς�������̂ƍl������B�����āA�����̏��F�́A�����R����̕��čs������̂Ƃ���Ă��āA�ދ������ߏ��̔��t�����҂������ɑ��ĕs����\�����Ă邱�Ƃ͉���\�肳��Ă��炸�A�����̏��F�E�s���F�́A�ދ������葱��S�����鑤�̓����I���ٍs�ׂɂق��Ȃ�Ȃ��B���������āA�����x���p�������̂ƍl������@�S�X���R���ٌ̍��ɂ��Ă��A�ދ������ߏ��̔��t�����҂ً̈c�\�o��O��Ƃ���_�ɂ����ĈقȂ���̂́A���̎҂ɑ��钼�ڂ̉����s�ׂ�\�肵�Ă��Ȃ��ȏ�A��{�I�ɂ͓��l�̐��i�̂��̂ƍl����̂����R�ȉ��߂Ƃ������Ƃ��ł���B
�E�@�܂��A��L�̉��߂́A�@�S�X���P�����A�s�����ɑ���s���\���Ăɂ��Ă̈�ʓI�Ȗ@�ߗp��ł���u�ًc�̐\���āv��p�����ɁA�u�ًc�̐\�o�v�Ƃ̗p���p���Ă��邱�Ƃ�������t������B���Ȃ킿�A���a�R�V�N�ɑi��@��p�~����ƂƂ��ɍs���s���R���@�i���a�R�V�N�@��P�U�O���j�����肳�ꂽ���A���@�́A�s�����ɑ���s���\���Ă��u�ًc�\���āv�A�u�R�������v�y�сu�ĐR�������v�̂R��ށi���@�R���P���j�ɓ��ꂵ�A����ɔ����A�s���s���R���@�̎{�s�ɔ����W�@���̐������Ɋւ���@���i���a�R�V�N�@����P�U�P���j�́A����܂Ŋe�s���@�K����߂Ă����s���\���Ă̂����A�s���s���R���@�ɂ�邱�ƂƂȂ����s�������ɑ���s���\���Ă͔p�~����ƂƂ��ɁA�s�������ȊO�̍s����p�ɑ���s���\���Ă͏�L�R��ވȊO�̖��̂ɉ��߁A�����������̂̈�Ƃ��āu�ًc�̐\�o�v��p���邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@�����A�@�̑ΏۂƂ���O���l�̏o�����ɂ��Ă̏����͍s���s���R���̑Ώۂ���͏��O����Ă���i���@�S���P���P�O���j�Ƃ͂����A��L�̂Ƃ���s���s���R���@�̐���ɍۂ��Čʂɕs���\���葱�ɂ��ċK�肷�鑽���̖@�߂ɂ��Ă��s���\���Ăɂ��Ă̖@�ߗp��̓��ꂪ�}��ꂽ�̂ɁA�@�S�X���P���Ɋւ��ẮA�]�O�ǂ���u�ًc�̐\�o�v�Ƃ̗p�ꂪ�p����ꂽ�܂܉��������ꂸ�A�@�ɂ��Ă͂��̌�������ɂ킽���ĉ��������ꂽ�ɂ�������炸�A��͂�@�S�X���P���́u�ًc�̐\�o�v�Ƃ̗p��ɂ��Ă͉���������Ȃ������B�����āA���݂ɂ����ẮA�@�ߗp��Ƃ��Ắu�ًc�̐\�o�v�Ɓu�ًc�̐\���āv�͒ʏ��ʂ��ėp�����A�u�ًc�̐\�o�v�ɑ��Ă͉����`�������Ȃ����A���͉����`���������Ă��\���l�ɕۏႳ��Ă���̂͌`���I�v���̕s���𗝗R�Ƃ��ĕs���ɐ\�o��r�˂���邱�ƂȂ����炩�̎��̔��f���邱�Ƃ����ł���ꍇ�ɗp������p��ł���̂ɑ��A�u�ًc�̐\���āv�́A���e�I�ɂ��K�@�ȉ�������n�ʁA���Ȃ킿�葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂƂ��Ă̐\�����Ȃ����\������F�߂�ꍇ�ɗp������p��Ƃ��Ē蒅���Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B���������āA�����ɂ킽��������o�Ă��Ȃ��u�ًc�̐\�o�v�̗p�ꂪ�p�����Ă���@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�́A����ɂ��A�@����b���ދ������葱�Ɋւ���ē������邱�Ƃ𑣂��r��Ă�����̂ł͂��邪�A���ًc�̐\�o���̂ɑ��ẮA�퍐�̉����`�����Ȃ����A���́A�����`���������Ă��A�`���I�v���̕s���𗝗R�Ƃ��ĕs���ɐ\�o��r�˂���邱�ƂȂ����炩�̎��̔��f���邱�Ƃ��ۏႳ��邾���ł���A�\�o�l�Ɏ葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂƂ��Ă̐\�����Ȃ����\�������F�߂��Ă�����̂Ƃ͉�����Ȃ��i�ō��ّ�P���@�씻�����a�U�P�N�Q���P�R�����W�S�O���P���P�ł́A�y�n���ǖ@�X�U���̂Q��T���y�тX���P���ɋK�肷��ًc�̐\�o�ɂ��A���|�̔��������Ă���B�j�B
�@����āA�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ��Ă����@�S�X���R���́u�ٌ��v�́A�s���\���l�ɂ��������葱�I�����Ȃ����n�ʂ����邱�Ƃ�O��Ƃ���u�R�������A�ًc�\���Ă��̑��̕s���\���āv�ɑ���s�����ٌ̍��A���肻�̑��̍s�ׂɂ͊Y�������A�s�������i�ז@�R���R���ٌ̍��̎���̑i���̑ΏۂƂȂ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�G�@����ɁA�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɂ��ẮA��L�̂Ƃ���A�\�o�l�ɑ��Ė@�̋K��ɂ��葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂƂ��Ă̐\�����Ȃ����\�������F�߂��Ă�����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��邩��A�ًc�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��|�ٌ̍������������葱��̌����Ȃ����@�I�n�ʂɕϓ�����������̂Ƃ������Ƃ͂ł����A���ٌ����s�������i�ז@�R���Q���́u�����v�ɓ�����Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��i�O�L�E�̍łP�����Q�ƁB�j�B
�I�@�ȏ�ɂ��A�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���@����b�ٌ̍��͓����I���ٍs�ׂƂ����ׂ����̂ł���A�s�������i�ז@�R���P���ɂ��������͂̍s�g�ɂ͊Y�����Ȃ��Ƃ����ׂ����̂ł���B�퍐�́A���ٌ��ɂ��čٌ������쐬����Ă��Ȃ����Ƃ�F�߂Ă���Ƃ���ł���A���̂悤�Ȏ����戵�����O�L�̋K�������Ɏ���܂Œ��N�ɂ킽���Čp������Ă������Ƃ́A���ٔ����Ɍ����Ȏ����ł���Ƃ���A���̓_���A�ٌ����������ٍs�ׂł��邱�Ƃ���b�t������̂Ƃ�����i�ނ���A��L���߂Ƃ͋t�ɍٌ����s�������i�ז@�R���P���ɂ��������͂̍s�g�ł���Ɨ��������ꍇ�A�ٌ����s�쐬�̓_��K�@�Ƃ���͍̂���ł���Ƃ��킴��Ȃ��B�j�B
(2)�@�ދ������ߏ����t�����ɂ������C�R�����̍ٗ�
�@�@�Q�S���́A�����e���̒�߂�ދ��������R�ɊY������O���l�ɂ��ẮA�@��T�͂ɋK�肷��葱�ɂ��A�u�{�M����̑ދ����������邱�Ƃ��ł���v�ƒ�߂Ă���B�����āA�����Ȃ�ꍇ�ɂ����čs�����ɍٗʂ��F�߂��邩�̔��f�ɂ����āA�@���̋K�肪�d�v�Ȕ��f�����ƂȂ邱�ƂɈ٘_�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�@���̕������s��������̂Ƃ��āu�E�E�E���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ̋K��������Ă���ۂɂ́A���̍ٗʂ̓��e�͂Ƃ������A���@�҂��s�����ɂ��镝�̌��ʍٗʂ�F�߂��|�ł���Ɖ����ׂ����̂ł����āA�������ދ������Ɋւ�����̋K��Ƃ��āA�ދ��������R�ɊY������O���l�ɑ��đދ����������邩�ۂ��ɂ��Ă͂����S������s�����ɍٗʂ����邱�Ƃ��K�肵�Ă���͖̂��炩�ł���A�@��T�͂̎葱�K��ɂ����ẮA��C�R�����̍s���ދ������ߏ��̔��t���A���Y�O���l���ދ������������ׂ����Ƃ��m�肷��s�������Ƃ��ċK�肳��Ă���i�@�S�V���S���A�S�W���W���A�S�X���T���j�Ɖ�����邱�Ƃ��炷��A�ދ������ɂ��Ď��̋K��ł���@�Q�S���̔F�߂�ٗʂ́A��̓I�ɂ́A�ދ������Ɋւ����L�葱�K�����Ď�C�R�����ɗ^�����A���̌��ʁA��C�R�����ɂ́A�ދ������ߏ��t���邩�ۂ��i���ʍٗʁj�A���t����Ƃ��Ă���������t���邩�i���̍ٗʁj�ɂ��A�ٗʂ��F�߂��Ă���Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̂悤�ȉ��߂́A�s���@�̉��߂ɂ����ē`���I�ɔF�߂���s���X��`�A���Ȃ킿���͔����v�����[������Ă���ꍇ�ɂ��s�����͂�����s�g���Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ̍l������A�x�@���̌����A���Ȃ킿�A�x�@�@����ɂ����ẮA��ʂɍs�����̌����s�g�̖ړI�͌����̈��S�ƒ������ێ����邱�Ƃɂ���A���̌����s�g�͂�����ێ����邽�ߕK�v�ŏ����Ȃ��̂ɂƂǂ܂�ׂ��ł���Ƃ̍l�������肩�A���@�P�R���̎�|���Ɋ�Â��A���͓I�s����ʂɔ�ጴ����F�߂�l�����ɂ���Ă��m�肳���ׂ����̂ł���B
�@���̂悤�Ɏ�C�R�����ɍٗʌ���F�߂邱�Ƃɑ��A�퍐�́A�@�S�V���S���A�S�W���W���y�тS�X���T�����A��������u��C�R�����́E�E�E�i�����j�E�E�E�ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�Ă��邱�Ƃɔ�����|�咣����B�������A�ދ������葱�́A�����Ƃ��ėe�^�҂ł���O���l�̐g�������e�ߏ��ɂ��S�����Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă��邽�߁A���̎葱��S������҂����̍l�����Ȃ��܂܂Ɏ葱�𒆒f���A���u���邱�Ƃ������Ȃ��悤�ɁA�@�S�V���P���A�S�W���U���y�тS�X���S���ɂ����āA���ꂼ��e�^�҂��ދ��������R�ɊY�����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�Ɂu�����ɂ��̎҂���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���Ƃ��߂�ƂƂ��ɁA�@�S�V���S���A�S�W���W���y�тS�X���T���ɂ����ẮA�ދ������Ɍ����Ď葱��i�߂�ꍇ�ɂ����Ă��A�u�ދ������ߏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ď�C�R�����̋`���Ƃ��ċK������������̂Ɖ�����A�����̋K��Ɩ@�Q�S�������킹�ĉ��߂���A���̋K��ł���@�Q�S���ɂ����đދ������ɂ��đO�L���ʍٗʋy�ю��̍ٗʂ�F�߂Ă���ȏ�A��C�R�����ɂ����āA���������ٗʂ̔��f�v�f�ɂ��ď\���l�����Ă��Ȃ��ދ������葱��i�߂�ׂ��ł���Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A���Ɩ��͑ދ��Ɏ���Ȃ��܂葱����u�����A�@�̒�߂鎟�̎葱�ɐi�ށi�ދ������ߏ��t����j�ׂ����Ƃ��߂����̂Ɖ����ׂ��ł���A���̂悤�ɖ@�̊e�K������̈ʒu�Â��ɉ����ĉ��߂���A��C�R�����ɑދ������ߏ����t�ɂ��Ă̍ٗʂ�F�߂邱�Ƃ́A�@�S�V���S���A�S�W���W���y�тS�X���T���̊e�K��Ɖ��疵��������̂ł͂Ȃ��B
�@�܂��A�퍐�́A�㋉�s���@�ւł���@����b�̈ӎv�����b�̎w���ē��鉺���s���@�ւł����C�R�������A���̓Ǝ��̔��f�Ɋ�Â��ĕ����A���邢�͂��̓K�p�������l���ł���Ƃ��邱�Ƃ͍s���g�D�@��̊ϓ_����l�����Ȃ��|�̎咣�����邪�A�O�L�̂Ƃ���ٌ����s�������ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�s���@�֓����ɂ����錈�َ葱�ɂ����Ȃ��Ɖ����ׂ��ł��邩��A���̌��ق̎�|���ދ������ߏ��̔��t�𖽂����|�ł���Ƃ��Ă��A����͑g�D�@��̋`����������ɂƂǂ܂�A����ɂ�蓖�Y���t�������K�@�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��A�q�ϓI�ɍٗʈᔽ�Ȃ�����ጴ���ᔽ�̎���������ꍇ�ɂ͓��Y�����͈�@�Ƃ��킴��Ȃ��B���̂��Ƃ͏����������O�ɏ㋉�s�����̌��ق��čs�������������ꍇ��ʂɐ����邱�Ƃł���A���̂悤�Ȍ��ق��s��ꂽ�Ƃ��Ă��A�ٗʌ��s�g�̎�̂́A�����܂ł����Y�s���������s���s�����ł���A�㋉�s�����ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��̂ł���B
(3)�@�ȏ��O��Ƃ���A�@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɑ���ٌ��ɂ����̎���������߂�i�ׂ́A�Ώۂ̏������������s�K�@�Ȃ��̂Ƃ��킴��Ȃ����ƂƂȂ�A��L(2)�̂Ƃ���A�ދ������ߏ����t�����ɂ����ʍٗʁA���̍ٗʂ��F�߂��Ă��邱�Ƃɂ��A�ދ������ߏ����t�����̎���������߂�i�ׂɂ����āA�ދ��������R�̗L���ɉ����A���̍ٗʂ̈�E���p�ɂ��Ă��������̈�@���R�Ƃ��Ď咣�����邱�ƂƂ��ׂ��ł���Ɖ����ׂ��ł���B���̂悤�ȉ��߂ɂ��A�O�L�����̉��߂ɂ��@�S�X���R���̖@����b�ٌ̍��ɂ��Ɨ����ēK�@�Ɏ���i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ邪�A�@�S�X���R���ٌ̍��̎���i�ׂŖ��Ƃ��ꂽ�@����b�̍ٗʌ��s�g�̓K�ۂ́A�ދ������ߏ����t�ɂ������C�R�����̍ٗʌ��s�g�̓K�ۂɂ����Ă��قړ���̓��e�ŐR���̑ΏۂƂȂ�ׂ����̂ł����āA�O���l���ދ�����������邱�Ƃ𑈂��@������߂���̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�ނ���A�ݗ����ʋ������邩�ۂ��̔��f�����܂��ܖ@�S�X���ٌ̍��ɓ������Ă����Ƃ̐��x���̗p����Ă��邱�Ƃ݂̂𑨂��A�{���S���ʌ̐��x�ł���ݗ����ʋ��̔��f�i�@�T�O���R���́A�ݗ����ʋ����A���ދ��������R�ɊY�����邩�ۂ��f���Ă����@�S�X���ٌ̍��Ƃ͖{���I�ɈقȂ鐧�x�ł��邱�Ƃ���A�ݗ����ʋ������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����āA�����@�S�X���S���̓K�p�ɂ��ًc�̐\�o�ɗ��R������|�ٌ̍��Ƃ݂Ȃ��|���߂Ă���B�j�̓��ۂ�@�S�X���R���ٌ̍��̈�@���R�Ƃ��Ď咣�����邱�Ƃ�F�߂�Ƃ��������̂�����߂��̗p����K�v���Ȃ��Ȃ���̂ł���B
(4)�@����
�@�ȏ�ɂ��A�{���i���̂����A�����炪�퍐�@����b�������{���e�ٌ��̎���������߂镔���͑Ώۂ̏������������s�K�@�Ȃ��̂Ƃ����ׂ��ł���B�����āA�����ł���ȏ�A���_�Q�ɂ��Ă̔��f�͕s�v�Ƃ������ƂɂȂ�A�ȉ��A���_�R�i�ދ������ߏ����t�����̓K�@���j�ɂ��Ĕ��f���邱�ƂƂȂ邪�A�@�́A��C�R�����̍s���ׂ���̓I�ȍٗʊ���߂Ă��Ȃ����A����܂ł̎����ɂ����Ă͔퍐�炪�咣����Ƃ����C�R�����ɂ͑S���ٗʂ̗]�n���Ȃ��Ƃ̍l�������Ƃ��Ă����̂ł��邩��A�s���������ɂ����Ă��ٗʊ���͍��肳��Ă��Ȃ��B�����Ƃ��A�@�́A�ދ��������R�̂���҂�K�@�ɍݗ�������B��̐��x�Ƃ��čݗ����ʋ��Ƃ������x��݂��Ă���̂ł��邩��A���̎�|���炷��ƁA��C�R�����͍ݗ����ʋ������ׂ��҂ɂ��đދ������ߏ��t���邱�Ƃ͋�����Ȃ����ʁA�ދ������ߏ��t���Ȃ����Ƃ��������͍̂ݗ����ʋ������ׂ��҂Ɍ�����Ɖ����ׂ��ł���B��������ƁA���_�R�ɂ��Ă̔��f���e�́A���_�Q�ɂ��Ĕ��f�����ꍇ�̔��f���e�ƑS����v���邱�ƂƂȂ�B�܂��A�퍐��́A��C�R�����ɂ͍ٗʌ����Ȃ��Ƃ̎咣�����Ă��邽�߁A�{���e�ޗߔ��t�����ɓ������Ăǂ̂悤�ȍٗʔ��f�����ꂽ�̂����咣���Ȃ��B������`���I�Ɏ�舵���ƁA�퍐��C�R�����͎��̓��ۂ���̓I�Ɍ������Ȃ��܂܌��_�̂ݔF�߂����̂Ƃ��āA���̏�������舵�킴��Ȃ��Ȃ邪�A�퍐��́A�퍐�@����b�������{���e�ٌ����K�@�Ȃ��̂ł���Ƃ��ċ�̓I�Ȏ咣�����Ă���Ƃ���ł���A���̎咣�́A���ɔ퍐��C�R�����ɍٗʌ�������Ƃ���Ȃ�A���l�̍ٗʔ��f�Ɋ�Â��Ė{���e�������������̂ł���Ǝ咣���Ă�����̂ƑP���ł��邩��A�ȉ��̌����ɂ����ẮA�퍐��C�R�������퍐�@����b�Ɠ��l�̔��f�Ɋ�Â��Ė{���e�ޗߔ��t�������������̂Ƃ̑O��ōs�����ƂƂ���B
�Q�@���_�R�i�{���e�ޗߔ��t�����̓K�@���j
(1)�@�����W
���@�����̌o��
�@�����́A�P�X�U�R�N�i���a�R�W�N�j�W���Q�R���ɃC�����̃e�w�����Ő��܂�A�P�X�V�W�N�i���a�T�R�N�j�ɒ��w�𒆑ނ�����A���炭�����Ē��߂����ƕ�����̎؋��ɂ��A�m���̖D����Ђ�ݗ����o�c���s�������A�C�����C���N�푈���ɂ�萭��E�i�C���s����ƂȂ�A��Ђ��������Ȃ��Ȃ����B���̌�A�P�X�W�R�N����P�X�W�T�N�܂ŕ����ɕ����C�����C���N�푈�ɏ]�R�����B�����āA�P�X�W�U�N�ɂ́A�����Ȃƌ����������A���肵���E�邱�Ƃ�����A�����������o���������̂́A�������ꂵ���Ȃ������߁i���̓_�ɂ��ẮA����T���A��P�R���ؒ��ɂ́A���قȂ�����|�ɂ��ǂ߂�L�ڂ����邪�A�����̏؋��S�̂̎�|���f�e�؋��ɏƂ炷�ƁA��L�F��ɔ�������̂ł͂Ȃ��ƔF�߂�̂������ł���B�j�A���{�ɍs�������ƍl����悤�ɂȂ�A�����Q�N�T���ɗ��������B�����͂R�������x�̒Z���ԓ����A���������ł��������A�����������v���X�`�b�N��Ђŋ������ǂ���ɂ͎x�����Ȃ��������Ƃ�A���{�ŐE�Đ��������肷�邤���ɁA����ɓ��{�ɒ����������Ƃ����C���������������ƁA�܂��A�C�����ɖ߂��Ă��E���Ȃ����߁A�A������@��������A�s�@�c������Ɏ������B
�i���S�A�P�P�A�Q�R�A�Q�X�A�����v�{�l�j
���@������̐����̏�
�@�����v�́A���������A�Q�n�������s�̃v���X�`�b�N��ЂɋΖ����A���̌�A�ʂ̃v���X�`�b�N��Ђ�p�`���R������Г��ɋΖ������̂��A�����T�N�P������͓��c��ɂ����ĉ������z�ǍH�Ƃ��ĉғ����Ă������A�s�@�A�J�̔��o�����ꂽ�В�����̊��߂ɏ]���āA�����P�P�N�Q���ɓ��Ђ����߁A�S���g���Ă̐����Ƃ��n�߂�ƂƂ��ɁA���ɂ͓��c��̉����������A�{�����������ɂ͂P�T���~����Q�T���~�̌������������i�����P�O�N�ɂ����ĂR�O�R���O�S�O�O�~�̎����Ă���j�B������́A�����S�N�R�����납�畽���P�Q�N�S������܂ł̊ԁA�Q�n�������s�����Ԓn���̃A�p�[�g�ɋ��Z���Ă����B
�@�@�i�b�R�A�P�T�A���S�A�T�A�Q�R�j
�@�����v�́A���݁A�F�l�̂��ƂŃA���o�C�g�����A���ɂP�V�`�P�W���~�̎����Ă���A�����P�Q�N�T���ɌQ�n������S�������Ԓn�̖ؑ������Q�K���Ă̏Z��������A������S���Ő������Ă���B
�@�@�i�b�S�A�����v�{�l�j
�@���������́A�����V�N�S���A���Z�n�̗ג��ł���Q�n������S�����̂�����ꏬ�w�Z�ɓ��w���A�����P�R�N�S���ɂ́A�������������w�Z�ɓ��w���A���ݒ��w�Z�R�N���ɍ݊w���Ă���B���������́A�{�����������͂��Ƃ��A���݂������v�E�ȂƂ̉�b�����{��ōs���Ă���A�����v��Ȃ��b���y���V����𗝉����邱�Ƃ����ł�����̂́A�y���V�����b�����ƁA�������Ƃ͂ł��Ȃ��B���������Ǝ��������{��ʼn�b�����Ă���B���������́A�������C�����ł͒��p���邱�Ƃ��l�����Ȃ����{�̏��������镞�𒅗p���A�H�����J���[�A�����ȂǓ��{�̎q�����D�ސH�����D�݃C���������͍D�܂Ȃ����A��F�W��Ƒ��Ƃ̊W���C�����̏K���ɂ͂Ȃ���ł��炸�A���S�ɓ��{�̏K���ɂȂ���ł���A���������䂪���ɍݗ����A�w�𑱂��邱�Ƃ������]��ł���B
�@�@�i�b�T�A�Q�P�A�Q�Q�A�S�S�A���S�O�A�����v�{�l�A�٘_�̑S��|�j
�@�����v�y�ь����Ȃ́A���������E���������ɑ��ăC�X�������̂��F��̂��Ƃ���������A�f�H���s������A�R�[������ǂݕ�������Ƃ������@��������s���Ă͂�����̂́A�q���炪���ۂɏ@��������s�����Ƃ͂Ȃ��A�����炪���X�N�ɍs�����ƂȂǂ��Ȃ��B
�i�����v�{�l�j
�@�������Ƃ́A�����S�N����{�������̒��O�܂Ŗ�W�N�ԓ����s�ɂ����Ē�Z���A���̊ԁA�{���������R�ȊO�ɂ͖@�ɐG��邱�Ƃ��Ȃ������ɐ������Ă���A�����P�S�N�Q���ɂ́A�����v�y�эȂ��A���c�@�l���{���ۋ��狦��y�э��ی𗬊�������{�������{��\�͎����R���ɍ��i���A�܂��A���������E�����̊w�Z�E�ۈ牀�̍s�����ɂ͕K���Q������ȂǁA�n��ɂƂ��������𑗂��Ă���B
�i�b�P�V�A�P�W�A�����v�{�l�j
�@������Ƒ����Z�ތQ�n������S�����́A�l������P���Q�O�O�O�l�ł���A�����O���l�͂R�O�O�����x�ł���B�����ɂ���㕐��w�o�ϊw���ւ̗��w�����������A�ݗ����ʋ����C�����l���������Ă���B�������ی𗬋���A�����̓��{�ꋳ�����s���Ȃǂ��Ă���A���Ƃ��Ă��O���l�J���҂₻�̉Ƒ�������邱�ƂɂȂ�Ă���A��R�����Ȃ��A�g���u�������������Ă��Ȃ��B
�i�b�R�P�j
���@�C�����̏�
(��)�@�C�����ɂ����錴����̋�̓I��
�@�����v�̉Ƒ��́A���e�̂ق��ɌZ���P�l�A�o���Q�l�A�킪�R�l�C�����Ő������Ă���B���́A�{���e������̕����P�R�N�S�����ɖS���Ȃ����B���́A���O�A�e�w�����s���ŃX�[�p�[���o�c���Ă������A���݂͒�Q�l�����X�[�p�[���o�c���Ă���B
�i���S�A�����v�{�l�j
�@�����v�́A�����W�N����܂łɁA���{�~�ō��v�R�O�O���~���C�����ɂ��镃�ɑ������A������āA�C�����̕��̉Ƃ̋߂��ɒ��Â̏Z�����w�������B�������A���̏Z���́A�����v�����e����Ă���ԁA�����Ȃ�̐����������K�v�ƂȂ������߁A�����P�Q�N�V���ɔ��p����A���݁A������Ƒ��́A�C���������ɍ��Y��L���Ă��Ȃ��B
�i�b�P�V�A�P�W�A���S�A�T�A�P�R�A�����v�{�l�j
(��)�@�C�����̈�ʓI��
�@�C�����ɂ����ẮA�C�X�������Ɋ�Â��@���I�ȉ����Ɍ������K�肳�ꂽ����������A�������q���ɋ����鋳�{�Ɋ�Â��A�c���̂��납�������g�ɂ��邱�Ƃ����R�ƂȂ��Ă���B��̓I�ɂ́A�����́A�w�W���u�i�����ȕ����K��j���`���t�����A�������\���ɕ����A���ς͋֎~����A�ᔽ�������ꍇ�ɂ͔����A�ڑł����̌Y���Ȃ����A���R�ɒj���Ƙb�����Ƃ⎩�R�ɊO�o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ق��A�ƒ�y�э��Y���ɂ��Ė@����̍��ʂ�����Ă���B�܂��A�H�����ɂ��Ă��ؓ���H�ׂ邱�Ƃ��ւ���ꂽ��A���}�_���i�f�H�j�̏K��������Ȃǂ̒�߂�����B
�i���W�X�A�����v�{�l�j
�@�C�����̋��琧�x�́A���w�Z���T�N�A���w���R�N�A���Z���S�N�A��w���Q�N����S�N�Ƃ��������x�ƂȂ��Ă���A���w�Z�܂ł��`������Ƃ���Ă���B���Z�ɂ͂W�O�`�X�O�p�[�Z���g�̎҂����w���邪�A���̍ۂɂ͎���������B�ʏ�̊w�Z�ɂ����Ă̓y���V���ꂪ�ł��Ȃ��҂̂��߂̃N���X�Ȃǂ͗p�ӂ���Ă��炸�A��ʉƒ�ł͕��S���邱�Ƃ�����ȋ��z���x�����ē��ʎ��Ƃ���ق��Ȃ��B
�i���W�X�A�����v�{�l�j
�@�����v�́A������̒m�l�Ō��������Ɠ��N�̂d�����{����C�����ɋA��������A�w�Z�Ő搶�̘b�����t���킩�炸�A���Ƃ��S�R�����ł��Ȃ����߁A���ʂ̊w�Z�ɂ͒ʂ�Ȃ��Ȃ����ƕ������B
�i�b�Q�P�j
�@�����P�S�N�P���P�U���ɍ��ۘA���o�ϋy�юЉ��c�l���ψ���ɂ����Ă��ꂽ�C�����ɂ�����l���̕ɂ��A�C�������{�����̌����Ȕ��\�ł������P�R�N�R������V���ɂ����Ď��Ɨ����P�R�D�V�p�[�Z���g�Ƃ���A���N�U���̂���V���ɂ��G�ߘJ���҂�o�^����Ă��Ȃ����Ǝ҂��܂߂�Q�T�p�[�Z���g���Ă��邱�Ƃ��m���Ƃ̕�����A�x�d�Ȃ鋋�������̎��Ă�A��K�͂ȘJ���҂̈�ĉ��ٓ��̕�����Ă���B
�i�b�S�R�j
���@�W�c�o���̏�
�@������́A�����P�P�N�P�Q���Q�W���ɓ������ǂɏo�����A���Ȃ̕s�@�c�������̐\�����s�������̂ł��邪�A������͍ݗ����ʋ����擾���ׂ��A��čs���Ƃ��ďo�������O���[�v�ɎQ�����Ă�����̂ł���B���O���[�v�́A��P���o���҂Ƃ��ĂT�Ƒ��A�Q�P�g�҂̂Q�P�������N�X���P���ɓ������ǂɏo�����A��Q���o���҂Ƃ��ĂT�Ƒ��A�P�V���������P�P�N�P�Q���Q�W���ɏo�������B
�i�b�V�A�W�j
�@�����̉Ƒ����ɂ��ẮA�P�O�Ƒ��A�Q�P�g�҂̂����A�T�Ƒ��ɑ��čݗ����ʋ����F�߂��A�u��Z�v�̍ݗ����Ă���B�ݗ����ʋ������Ƒ��̍\���́A�P�Q�ˁi���w�Z�U�N���j�̏����ƂT�˂̒��j�����v�w��P�T�˂̒��j�����v�w��������A��������P�O�N�߂����{�ɂ����Đ������Ă�����̂ł������B
�i�b�V�A�W�j
(2)�@�{���ɂ������C�R�����̍ٗʂ̓K��
���@���f�̂�����|���ɍٗʊ�Ƃ̊W�ɂ���
�@�O�L�P(4)�Ő��������Ƃ���A��C�R�����̍ٗʂ̓K�ۂ́A�v����Ƃ���A���Y�O���l���ݗ����ʋ���^����ׂ��҂ɊY�����邩�ۂ��ɂ��Ă̔��f��������ƕ]�������邩�ۂ��ɂ�����Ƃ���A���̔��f���̂ɂ��ٗʂ��F�߂���ׂ����̂ł��邩��A�ٔ����Ƃ��ẮA��C�R�����̏�L�̓_�ɂ��Ă̔��f�͍ٗʌ��̈�E���p�����������ۂ��A���Ȃ킿�A������ɂ��ݗ����ʋ���^����ׂ��҂ɊY�����邩�ۂ��̔��f�ɓ�����A���R�ɏd�����ׂ�������s���Ɍy�����A���́A�{���d�����ׂ��łȂ�������s���ɏd�����邱�Ƃɂ��A���̔��f�����E���ꂽ���̂ƔF�߂��邩�ۂ��Ƃ����ϓ_����R�����s���A���ꂪ�m�肳���ꍇ�ɂ͖{���e�ޗߔ��t�������������ׂ����̂Ƃ���̂������ł���B
�@�����āA��C�R�������{���e�ޗߔ��t�����ɓ�����A�����Ȃ鎖�����d�����ׂ��ł���A�����Ȃ鎖�����d�����ׂ��łȂ����ɂ��ẮA�{���@�̎�|�Ɋ�Â��Č����ׂ����̂ł��邪�A�O���l�ɗL���ɍl�����ׂ������ɂ��āA������A�����I���َ͖��I�Ɋ���݂����A����Ɋ�Â��^�p������Ă���Ƃ��́A���������̗v�����炵�āA���i�̎���Ȃ�����A���̊�����邱�Ƃ͋�����Ȃ��̂ł���A���Y��ɂ����ē��R�l�����ׂ����̂Ƃ���Ă��鎖����l�������ɂ��ꂽ�����ɂ��ẮA���i�̎���Ȃ�����A�{���d�����ׂ�������s���Ɍy���������̂ƕ]��������Ȃ��B�퍐��́A���̓_�ɂ��āA�ٗʌ��̖{���������ɂ���ĕύX�������̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ��āA���s���̖�肪������ɂ����Ȃ��Ǝ咣���A�ߋ��̍ٔ���ɂ��������ʘ_�Ƃ��Đ���������̂����Ȃ��Ȃ����i�Ⴆ�A�ō��ّ�@�씻�����a�T�R�N�P�O���S�����W�R�Q���V���P�Q�R�P�Łj�A���̂悤�ȍl�����́A�s���ٗʈ�ʂ��K�����镽��������������̂ł����č̗p�ł��Ȃ��B
���@�����ԕ����ɍݗ����Ă��鎖���̕]��
(��)�@�{���̓����́A�O�L(1)�̎����W���炷��ƁA�������Ƃ��P�O�N�߂��ɂ킽���ĕ��������R�ƍݗ����p�����A���ɑP�ǂȈ�s���Ƃ��Đ����̊�Ղ�z���Ă��邱�Ƃɂ���B������́A���̓_���A�L���ɍl�����ׂ��d�v�Ȏ����ł���Ǝw�E����̂ɑ��A�퍐��́A����͌�����ɂƂ��ėL���Ȏ����ł͂Ȃ��A�ނ���A�����ԕs�@�ݗ����p�������_�ɂ����ĕs���v�Ȏ����ł���Ǝ咣����B���̂��Ƃ��炷��ƁA�{���e�����́A��L������������ɕs���v�Ȏ����ƕ]�����Ă��ꂽ���̂ƔF�߂���Ȃ��B
(��)�@�������A��L�̎����́A�ݗ����ʋ���^���邩�ۂ��̔��f�ɓ������āA�e�^�ґ��ɗL���Ȏ���̑��ɏグ�邱�Ƃ��A������A���Ȃ��Ƃ��َ��I�Ȋ�Ƃ��Ċm�����Ă�����̂ƔF�߂���B
�@���Ȃ킿�A���̂悤�ȍݗ����i�������Ȃ��܂ܒ����ɂ킽���čݗ����p������҂��������ɏ���Ă��邱�Ƃ͌��m�̎����ł��邪�A���̂悤�Ȏ��Ԃ͑����ȑO����p�����Ă���̂ł����āA���a�T�U�N�̖{�@�̑薼���܂ޑ�����̍ۂɂ��A���̉�������ŋc�_���ꂽ�Ƃ���ł���B�Ⴆ�A���a�T�U�N�T���P�T���̏O�c�@�@���ψ���ɂ����āA�e�ψ��������̎҂̂������̏��������҂ɓK�@�ȍݗ����i��^����ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ̗��ꂩ��A�u���������Ă���\�N�ȏキ�炢�������ҁA�����Ă��ܑ�b�̂��������悤�ɎЉ�����f�s���������������肵�Ă���҂ɂ��ẮA����\���������ꍇ�ɂ͌����ɒl����i�ݗ���F�߂邱�Ƃ���������ɒl����Ƃ̎�|�j�Ƃ����ӂ��Ȑ������Ƃ����Ă���̂ł����A�������ł����B�v�Ƃ̎���������̂ɑ��A�����̖@���ȓ����Ǘ��ǒ��́A�u�X�̎��Ăɂ��܂��ẮA���̕s�@�����҂̋��Z���A�Ƒ����A���ʂ̎����T�d�Ɍ������āA�l���I�z����v����ꍇ�ɂ͓��ɂ��̍ݗ���F�߂Ă���킯�ł������܂��B���������܂��āA�s�@�����҂��E������܂��ċ����ދ��̎葱���Ƃ�ꂽ��ł��A�@����b�̓��ʍݗ��������������ꍇ�ɂ͏o��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�v�Ƃ�����A����ɑ������ψ��̎���ɓ����āA�u���ݕs�@�����҂̂����ɂ́A�q�������悢��w��ɒB�����Ƃ��A�������������݂����疼�̂�o�āA�搶�̂������Ⴂ�܂��������鎩��\��������l������܂��B���������ꍇ�ɂ́A���ǂ��Ƃ������܂��ẮA���R�A�����l������ɓ�����܂��ăv���X�̍ޗ��ƍl���Ă���܂��B�v�Ɠ��ق��A����ɓ����̖@����b�́A�u���ʍݗ������邢�͉i�Z�������炦��̂͂ǂ������l�ł��邩�Ƃ���������x�̊�����炩�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���͂��܂̂悤�Ȃ��b���f���Ă��܂��Ƒ�Ȃ��Ƃ���Ȃ����ȂƎv���܂��B����܂ł���Ă������Ƃ�U��Ԃ��Ă݂āA�܂Ƃ߂�̂�����ȂƁA���܂��b���f���Ȃ���l�����킯�ł���܂��B����ɁA�X�̎��Ăɂ��ď�������ꍇ�ɂ��A�]���ȏ�ɐl���I�Ȕz���������Ă������Ƃ���̓]���ɂȂ��Ȃ����ȁA�����v���킯�ł������܂��āA���Ƃ��Ă͂ł������l���I�Ȕz���Ƃ������̂��d�����Ă��������ȁA�����v���Ă���܂��B�v�Ɠ��ق��Ă���̂ł���i�����t���O�c�@�@���ψ���c�^��P�S���R�Ȃ����S�Łj�B
�@�܂��A���̂Ƃ��̖@�����ɂ���Ė@�U�P���̂X�y�тP�O���V�݂���u�@����b�́A�o�����̌����ȊǗ���}�邽�߁A�O���l�̓����y�эݗ��̊Ǘ��Ɋւ���{��̊�{�ƂȂ�ׂ��v��i�o�����Ǘ���{�v��j���߂���̂Ƃ���B�v�A�u�@����b�́A�o�����Ǘ���{�v��Ɋ�Â��āA�O���l�̏o�����������ɊǗ�����悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƒ�߂��A����Ɋ�Â��Ė{���e�����O�̕����P�Q�N�R���Q�S���ɍ��肳�ꂽ�u�o�����Ǘ���{�v��i��Q���j�v�i�@���ȍ����P�S�X���j�V
�Q(2)�ɂ́A�u�ݗ����ʋ������O���l�̑����́A���{�l���Ƃ̖��ڂȐg���W��L���A�܂����ԂƂ��āA���܂��܂Ȗʂʼn䂪���ɏ����ɂ킽�鐶���̊�Ղ�z���Ă���悤�Ȑl�ł���B����̓I�ȗ�Ƃ��ẮA���{�l�ƍ������A���̍����̎��Ԃ�����ꍇ�ŁA���ǖ@�ȊO�̖@�߂Ɉᔽ���Ă��Ȃ��O���l����������B�@����b�́A���̍ݗ����ʋ��̔��f�ɓ������ẮA�X�̎��Ă��Ƃɍݗ�����]���闝�R�A���̊O���l�̉Ƒ��A�����A�f�s���̑��̎�����A���̊O���l�ɑ���l���I�Ȕz���̕K�v���Ƒ��̕s�@�؍ݎ҂ɋy�ڂ��e���Ƃ��܂߂đ����I�ɍl�����A��{�I�ɁA���̊O���l�Ɖ䂪���Љ�Ƃ̂Ȃ��肪�[���A���̊O���l��ދ��������邱�Ƃ��A�l���I�Ȋϓ_�������肪�傫���ƔF�߂���ꍇ�ɍݗ�����ʂɋ����Ă���B�v�Ɩ��L���Ă���B���̎�|�́A�䂪���ɂ����ď����ɂ킽�鐶���̊�Ղ�z���A�ݗ����̑f�s�ɖ�肪�Ȃ��A���̊O���l�Ɖ䂪���Љ�Ƃ̂Ȃ��肪�[�����Ƃ́A�ݗ����ʋ���^��������ɍl�����ׂ�����Ƃ��Ă�����̂ƔF�߂邱�Ƃ��ł��悤�B�����āA������Ɠ����ɓ��Ǔ��ǂɏo�������Ƒ��ɍݗ����ʋ����^�����Ă��邱�Ƃ��A��L������L���ɍl���������ʂł���ƍl������Ƃ���ł���B
�@�����ɂ��ƁA��L�̂悤�ɓK�@�ȍݗ����i�������Ȃ��O���l�������ԕ��������R�Ɖ䂪���ɍݗ����A���̊Ԃɑf�s�ɖ��Ȃ����łɑP�ǂȈ�s���Ƃ��Đ����̊�Ղ�z���Ă��邱�Ƃ��A���Y�O���l�ɍݗ����ʋ���^��������ɍl�����ׂ����̎��R�ł��邱�Ƃ́A�{���������܂łɖَ��I�ɂ��������m��������ł������ƔF�߂���̂ł���A�{�������́A������������肩�A�ނ���t�̌��_�����R�Ƃ��čl�����Ă���̂ł����āA���̂悤�Ȏ戵���𐳓���������i�̎�����������炸�A�������A���ꂪ������ɍł��L���Ȏ��R�ƍl������̂ł��邩��A���R�l�����ׂ����R���l�����Ȃ��������Ƃɂ��A���̔��f�����E���ꂽ���̂ƔF�߂���Ȃ��i���̂悤�ȏꍇ�ɁA���̓_��K�ɍl�������Ƃ��Ă��A���̎���Ƒ����l�������Ƃ��邱�Ƃɂ��A���Y�������q�ϓI�ɂ͓K�@�Ȃ��̂ƕ]��������ꍇ�����蓾��Ƃ���ł͂��邪�A���̂悤�Ȏ���͏����̓K�@�����咣����퍐��ɂ����āA�\���I�ɂ���咣�E�����ׂ����̂ł����āA�퍐�炪���̂悤�Ȏ咣�������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ٔ����Ƃ��ẮA����ϋɓI�ɂ����̓_��R�����f���邱�Ƃ͂ł����A���Y�������������āA�ēx���f������ق��Ȃ��B�j�B
(��)�@�ȏ�ɂ��ƁA�{���e�����́A��L�̎����̕]����������_�݂̂��炵�Ă��A�ٗʌ�����E���͗��p���Ă��ꂽ���̂Ƃ��Ď��������ׂ����̂ł��邪�A�퍐�炪�{�������̑������ɂ��ϋɓI�Ɏ咣���Ă���Q�̎��R�ɂ��Ă��A���̔��f���e�ɎЉ�ʔO�㒘�����s�����ȓ_������A�����̓_�͖{���e�ޗߔ��t�����̑���������b�t������̂Ƃ͍l����̂ŁA�O�̂��߁A���y�т��Ő�������ƂƂ��ɁA�{���e�ޗߔ��t�����́A��ጴ���̊ϓ_��������F�ł��Ȃ����Ƃ����ɂ����Đ�������B
�@�Ȃ��A�퍐��́A���a�T�S�N�̍ō��ٔ��������p���Ď咣���Ă��邪�A����������L�������O���l�ɗL���Ȏ���Ƃ��čl�����邱�Ƃ�ے肵�Ă�����̂ł͂Ȃ��Ɖ����ׂ��ł��邵�A���ɂ����łȂ��Ƃ��Ă��A���̔�����ɖَ��I�ɂ���ٗʊ���m�����Ă���ȏ�A���̔����͏�L�̔��f�ɉe�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ��B
���@�{���ɋA�������ꍇ�̌�����̐���
�@�퍐��́A�����v�y�ь����Ȃ̐e�Z�킪�{���C�����ɍݏZ���Ă��邱�ƁA�y�ь����v���`�̎����{���ɂ����čw�����Ă��邱�Ƃ̂Q�_�������Ƃ��Č����炪�{���ɋA�����Ă������Ɏx��͂Ȃ��Ǝ咣���Ă���B
�@�������A�����v�y�ь����Ȃ̐e�Z��̐E�Ƃ�������͖��炩�łȂ��A�A������������ɂǂ̒��x�����������邩�����炩�ł͂Ȃ��B�܂��A������݂��邱�Ƃ��瓖�ʋ��Z����ꏊ���m�ۂ�����Ɣ퍐��͔��f�����Ǝv���邪�A�����炪������r�ɂ��Ă͉���l���������Ă��炸�A�����炪���i�̋Z�\��L������̂ł��Ȃ��A�����v���{���������R�V�˂ł���A�P�O�N�߂����{���𗣂�Ă������ƁA�{���ɂ����Ă͎��Ɨ���������Ԃ������Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�ނ���A�����炪�{���ɋA�������ꍇ�ɂ́A���̐����ɂ͑����ȍ��������Ɨ\������̂��ʏ�l�̏펯�ɂ��Ȃ����̂ƔF�߂���B
�@��������ƁA�퍐��̏�L�w�E�́A�\���ȍ����Ɋ�Â��Ȃ��ƒf�ƕ]����������A�{�������̑���������b�t������̂Ƃ͍l����B
���@�A���ɂ�錴�������y�ь��������ւ̉e��
�@�퍐��́A�����q�炪�����Y���ɕx�ޔN��ł��邱�Ƃ������ɗ��e�ƂƂ��ɋA�����邱�Ƃ����̕������͍őP�̗��v�ɓK���Ǝ咣����B
�@�������A�퍐��̏�L�咣�̍����͋ɂ߂Ē��ۓI�Ȃ��̂ŁA�䂪���ŗc������߂����������q�炪�A����A�����y�яK����S���قɂ���C�����ɋA�������ꍇ�ɁA�ǂ̂悤�ȉe�����邩�ɂ��ċ�̓I���^���Ɍ����������̂Ƃ͓��ꂤ�������Ȃ��B���ɁA�䂪���ƃC�����Ƃɂ����鏗���̒n�ʂɂ́A�O�L�F��̂悤�ɒ��������ق�����A�C�����̏������@�������������j������������n�ʂɂ�����Ă��邱�Ƃ�ς�����̂́A�@�����瓙�ɂ��c�������炻�����ނȂ����̂Ƃ��Ď���Ă��邱�Ƃɂ��Ƃ��낪�傫���ƍl������̂ł���B����ɑ��A�����q��A���Ɍ��������́A�{�����������P�Q�˂ł���A���̔N��܂ň�т��ĉ䂪���Љ�ɂ����Ēj�q�ƑΓ��̐����𑱂��Ă����̂ł��邩��A�{���ɋA�������ۂɂ́A�����Ȑ��_�I�Ռ����A�ꍇ�ɂ���Ă͐��U���₷���Ƃ̍���Ȑ��_�I��ɂ��邱�Ƃ����蓾��ƍl����̂��A�ʏ�l�̏펯�ɓK�����̂ƔF�߂���B
�@��������ƁA�퍐��̏�L�咣���\���ȍ����Ɋ�Â��Ȃ��ƒf�ƕ]����������A�{�������̑���������b�t������̂Ƃ͍l����B
���@��ጴ���ᔽ
�@�@�́A�{�@�ɓ������A���͖{�@����o�����邷�ׂĂ̐l�̏o�����̌����ȊǗ���}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă�����̂ł���A�ދ������ߏ����A�����R�����̑ދ��������R�Y���̔F��ɕ������i�����R���̐��������Ȃ��|�L�ڂ��������ɏ��������j�ҁi�S�V���S���j�A�����R���ɂ����ē����R�����̂����F��Ɍ�肪�Ȃ��|�̓��ʐR�����̔���ɕ������ҁi�S�W���W���j�A�@����b�ɂ��@�S�X���P���ً̈c�̐\�o�ɗ��R���Ȃ��|�ٌ̍������ҁi�S�X���T���j�Ɍ����Ĕ��t����A�ދ��������R�ɊY������҂̑��҂��s���̂ɕs���Ȃ��̂ł��邱�Ƃɂ��݂�A�ދ������ߏ��̔��t�����́A�@���ړI�Ƃ���o�����̌����ȊǗ��̂��߂ɏd�v�Ȗ����������Ă�����̂ł���ƔF�߂��A�{���e�ދ������ߏ����t�������s���A�����ďo�����Ǘ��̓K����}��K�v��������Ƃ������ʂ͔ے肵���Ȃ��B
�@�������A������Ƒ��́A���{�ł́A�ݗ����i���Ȃ��ꂵ���̒��A�Ƒ��S�l�ł̐����̊�Ղ�z�������̂ł���A���̊�Ղ́A�ݗ����i���邱�Ƃɂ�肳��ɋ��łɂȂ邱�Ƃ��\������A�����̂₱��܂ł̋Ζ�����A�ݗ����i���邱�Ƃ������ɁA�����������A�����Ɏx������̐����z����Ă���B�܂��A���l��́A�@�ᔽ�ȊO�ɉ���̔ƍߓ����s�������Ƃ͂Ȃ��A�Љ�ɂ��ϋɓI�ɂƂ�����ł���Ƃ�����B�܂��A�����v�̍ݗ����Ԃ́A�������Ŗ�P�O�N�A���݂Ŗ�P�R�N�ƁA�{�M�ɒ����ݗ����Ă���ƕ]����������ԂɒB���Ă����A������Ƒ��́A�q������������w��ɒB���A�܂��A�ݗ����i��L���Ȃ����Ƃɂ��s���v���������Ƃ���A�Y���A��ނɂ�܂ꂸ����s�@�c�����������Ȑ\���������̂ł���A�O�L(2)���ɂ��A�����̎���́A�����̍ݗ����i�t�^�ɂƂ��ėL���Ȏ���Ƃ����ׂ��ł���B
�@�܂��A�O�L�F��̎����ɂ��A������Ƒ��́A�����v���������Ԏ��e����A���̌���{�i���W�����Ƃ̎�������邽�߁A���݁A�����v�̃A���o�C�g�ł̏\�����~�Ƃ��������ł̉Ƒ��S�l�̐������ێ�������Ȃ��ɂ��邽�߁A�C�����֑��҂����Ɠ����̔�p���܂��Ȃ������̒~�����Ȃ����Ƃ͗e�Ղɐ��F�ł���B�܂��A�C�����̈�ʓI�Ȍo�Ϗ⌴�����P�O�N�ȏ�C�����𗣂�Ă������Ɠ��ɂ��݂�A�����v�ɐE��������\���͒Ⴍ�A������́A�C���������ɗL���Ă�������������v�̎��e���̐�����ɏ[�Ă邽�߂ɔ��p�������Ƃ���i�b�P�U�j�A���Z�p�̕s���Y�����L���Ă��炸�A�܂��A�����v�̌Z��ɂ��x���̉\���͔ے肵���Ȃ����̂́A���̐���������݂�Α����̎x���͊��҂ł��Ȃ��Ƃ݂�̂����R�ł���A�A�������ۂɂ́A�����ɉƑ��S�l���H���ɖ����W�R��������Ƃ�����B
�@���ɁA�Q�̂Ƃ��ɗ������A�P�O�N�ȏ����{�ʼn߂��������������́A��L�̂Ƃ���A���̐����l����v�l�ߒ��A����������S�ɓ��{�l�Ɠ������Ă�����̂ł���A�C�����̐����l���������{�̐����l�����ƒ������������Ă��邱�Ƃ��l������A����͒P�ɕ����̈Ⴂ�ɋꂵ�ނƂ��������x�̂��̂ɂƂǂ܂炸�A���������̂���܂Œz���グ�Ă����l�i�≿�l�ϓ������ꂩ�畢�����̂Ƃ����ׂ��ł���A����́A�{�l�̓w�͂���͂̋��͓��݂̂ō������������̂ł͂Ȃ����Ƃ��e�Ղɐ��F�����B���������́A���݁A���{�̒��w�ŕw�ɗ�݁A���{�̐��k�Ƒ��F�̂Ȃ����т��C�߂Ă��邪�A�C�����ɋA�������ꍇ�ɂ́A�݊w���ێ����邱�Ƃɂ��瑊���ȍ�������A�A�E���ɍۂ��Ă��A���{�Ŕ|��ꂽ���l�ς��}�C�i�X�ɍ�p���邱�Ƃ��\���l������B
���������ɂ��ẮA�����������͔N���ł���A���ΓI�ɂ͓K���̉\���������Ƃ݂邱�Ƃ��ł���ł��낤���A���ꂪ�e�ՂłȂ����Ƃ����炩�Ƃ����ׂ��ł���B���̓_�ɂ����āA�f�ؐl�̓��{�Ő��܂ꂽ����{�ň�����C�X�������k�̎q�����A�C�X�����ɋA��Ƃ������Ƃ͎��˂ƌ����ɓ������Ƃ�����|�̏،��́A�\���X���ɒl������̂Ƃ����ׂ��ł���B�O�L�̎q�ǂ��̌������R���̓��e�ɂ��݂�A���̓_�́A�ދ������ߏ��̔��t�ɓ�����d�������ׂ�����ł���Ƃ�����B
�@�ȏ�ɂ��A�ދ������ߏ��̔��t�y�т��̎��s�����ꂽ�ꍇ�ɂ́A������Ƒ��̐����͑傫�ȕω��������邱�Ƃ��\�z����A���Ɍ��������ɐ����镉�S�͑z����₷����̂ł���A�����̎��Ԃ́A�l���ɔ�������̂Ƃ̕]�������邱�Ƃ��\���\�ł���B
�@�����āA�O�L�̂悤�ȕs�@�ݗ��O���l�̎����̕K�v�������邱�Ƃ͊m���ł͂��邪�A�s�@�c���ȊO�ɉ���̔ƍߍs�ד������Ă��Ȃ�������Ƒ��ɂ��A�ݗ����i��^�����Ƃ��Ă��A����ɂ�萶����x��́A����̎��Ăɂ��čݗ����i��t�^������Ȃ��Ȃ邱�Ɠ��A�o�����Ǘ��S�̂Ƃ����ϓ_�ɂ����Đ�����A����Β��ۓI�Ȃ��̂Ɍ����A������Ƒ��̍ݗ����i��F�߂邱�Ƃ��̂��̂ɂ���̓I�ɐ�����x��͔F�߂��Ȃ��B���ɁA������Ɠ��l�̏����̎҂ɍݗ����ʋ���^������Ȃ����Ԃ��������Ƃ��Ă��A������̂悤�ɒ����ɂ킽���čݗ����i��L���Ȃ��܂܍ݗ����p�����A���A�P�ǂȈ�s���Ƃ��Đ����̊�Ղ�z�����Ƃ͎���̋ƂƂ����ׂ����Ƃł��邩��A���̂悤�ȏ��������҂ɍݗ����ʋ���^���邱�Ƃɂǂ�قǂ̎x�Ⴊ�����邩�ɂ͑傢�ɋ^�₪����B�{���ɂ����Ă��A������̍ݗ����i�t�^�̗v�ۂɂ��āA�ݗ����Ԃ���̈��萫�A���Ȑ\���̗L���ɉ����A�C�����ɋA�������ꍇ�ǂ̂悤�Ȏ��Ԃ��\������邩�����l��������Ō������s���Ă�����̂ł���A���̎҂ɂ��Ă�����Ɠ��l�T�d�Ȕ��f���s�����ꍇ�ɂ́A�O�L�̂悤�ȏo�����Ǘ��S�̂Ƃ����ϓ_������������x��͐����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��낤�B���̂��Ƃ́A���ɁA�O�L�����̂Ƃ���A�퍐�@����b���A�����Ɠ��i�̎���̍��ق��F�߂��Ȃ��Ƒ��ɂ��āA�ݗ����ʋ����s���Ă���Ƃ��납�炵�Ă����炩�ł���B
�@�ȏ�ɂ��A������Ƒ����钘�����s���v�Ƃ̔�r�t�ʂɂ����āA�{�������ɂ��B������闘�v�͌����đ傫�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�{���e�ދ������ߏ����t�����́A��ጴ���ɔ�������@�Ȃ��̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̂悤�Ȍ����ɒ������s���v�������邱�Ƃ��\�������̒��A������ɂ��̂悤�ȕs���v���Î�Ƃ����ɂ́A�퍐���咣����悤�ɁA�s�@�ȍݗ��̌p���͈�@��Ԃ̌p���ɂق��Ȃ炸�A���ꂪ�����ԕ����Ɍp�����ꂽ����Ƃ����Ē����ɖ@�I�ی����؍����̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ̍l�����ɋ���ق��Ȃ����A���̂悤�ȍl���������p�ł��Ȃ����Ƃ͑O�L���ɐ��������Ƃ���ł���B�܂��A�ݗ����ʋ��̐��x�́A�ދ��������R�����݂���O���l�ɑ��A�ݗ����i��t�^���鐧�x�ł���A���̑ދ��������R����s�@�c����s�@���������O����Ă��邱�ƂȂǂ͂Ȃ��̂ł��邩��A�@�́A�s�@������s�@�c���̎҂ł����Ă��A���̎������ꍇ�ɂ͍ݗ����i��t�^���邱�Ƃ�\�肵�Ă�����̂Ƃ݂邱�Ƃ��ł��A�P���ɁA�s�@�ݗ��҂̖{�M�ł̐�������@��Ԃ̌p���ɂ����Ȃ��Ƃ��Ă����ی삳��Ȃ����̂Ƃ���̂͂��܂�Ɉ�ʓI�ł���A���Y�O���l�ɍ��Ȃ��̂ł���Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�ݗ����i��L���Ȃ����Ƃɂ�鑽���̕s���v�̒��A���Ȃ�Ƒ��̐����̈ێ��ɓw�߂Ȃ���A�A�����Ȃ���Ƃ����v���Ɩ{�M�ł̐����Ɋ��S�ɂƂ����݂Ȃ��琬�����Ă����q���̐������̋��ԂŒ����Ԃɂ킽�莩��̏�ԓ��ɔY�݂Ȃ��琶�����Ă��������v�y�эȂ̐S���͎@����ɂ��܂肠����̂ł���A���l��Ƃ��Ă���@��Ԃ�F�����Ȃ����������̕��@���̂蓾�Ȃ������Ƃ����̂������ȂƂ���ł���Ǝv����B����V�X���̂P�A�Q�A��X�O���̂P�A�Q�A��X�P���̂P�A�Q�ɂ��A���Ǔ��ǂƂ��Ă��s�@�؍݊O���l�̎���蓙���\�Ȍ���s���Ă��邱�Ƃ͔F�߂��邪�A�{���Ɍ����Ă݂Ă��O���l�o�^�̍ۂ⏬�w�Z�E���w�Z�ւ̓��w���ȂǁA�����炪���I�@�ւƐڐG�������Ă�����Ԃ͑�������A���̂悤�ȏ�ʂł̎���肪���x�����Ă��炸�A����肪�s���Ȃ��������ƂŒ����������ݗ��ɂ��āA���̔�����ׂČ����ɕ��킹��Ƃ����͖̂���������ƍl������B
(3)�@����
�@�ȏ�ɂ��A�{���e�ޗߔ��t�����́A�O�L(2)���̂Ƃ���A���Ɋm�������ٗʊ�ɂ����Č�����ɗL���ɍl�����ׂ��ŏd�v�̎��R�Ƃ���Ă��鎖�����A������ɗL���ɍl�����Ȃ����肩�A�t�ɕs���v�ɍl�����Č��_���Ă���_�ɂ����āA�ٗʌ��̈�E���͗��p������̂ł��邵�A�O�L(2)���y�т��Ƃ��肻�̑������̍����Ƃ��ĐϋɓI�Ɏ咣���ꂽ�_�́A��������\���ȍ����Ɋ�Â��Ȃ��ƒf�Ƃ��킴��Ȃ�����A���̑���������b�t���鎖�R���F�肷�邱�Ƃ��ł����A�������A�O�L(2)���̂Ƃ���A��ጴ���ɂ���������̂ł��邩��A������������ׂ����̂�
����ق��Ȃ��B
��T�@���_
�@�ȏ�ɂ��A������̔퍐�@����b�ɑ���i���͕s�K�@�ł��邩�炱����p�����邱�ƂƂ��A������̔퍐��C�R�����ɑ��鐿���͂���������R�����邩�炱���F�e���邱�ƂƂ��A�i�ה�p�̕��S�ɂ��A�퍐�@����b�͖{�i�ɂ����ď��i���Ă�����̂́A�퍐��C�R�����̖{�������������I�ɂ͎��O�Ɍ��ق��Ă�����̂Ƃ݂�ׂ����Ƃ��l�����A�s�������i�ז@�V���A�����i�ז@�U�P���A�U�Q���A�U�S�����������A�U�T����K�p���A�啶�̂Ƃ��蔻������B
������R��
�@�i�ٔ����ٔ����@���R��s�@�ٔ����@�A�V�@�@�ٔ����e�r�͂́A�]���̂��ߏ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ٔ����ٔ����@���R��s
|
|
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���y�[�W�̏㕔��